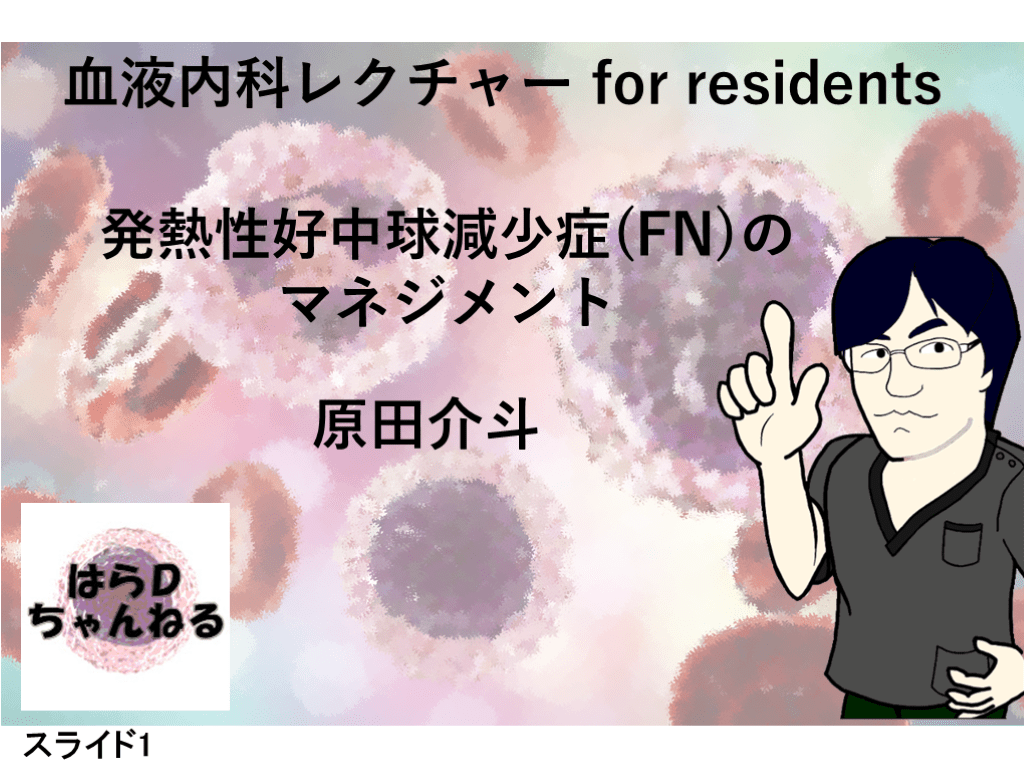テキスト全文
発熱性好中球減少症の定義と歴史的背景
#1. 血液内科レクチャー for residents 発熱性好中球減少症(FN)のマネジメント 原田介斗 スライド1
#2. 発熱性好中球減少症とは? 発熱: 口腔内 38.3 ℃または腋窩 37.5℃以上
好中球: 500/uL未満 / 48時間以内に500/uL未満へ減少 敗血症! 粘膜障害 カテーテル挿入 スライド2
#3. なぜ経験的(empiric)治療? 経験的治療がなされてなかった1960年代、GNR菌血症によるFNの死亡率はなんと90%を超えたという報告すらある!
2000年になって、empiric therapyが普及してきて、死亡率は10%程度
まで低下した。
しかし、今なお緑膿菌の死亡率は30-40%程度と高く、1-2日治療が遅くなると死亡率が30%も増加した。 Cancer. 2006 May;106(10):2258-66.
Arch Intern Med.1985;145:1621-9. 血培結果を待たずに、
抗緑膿菌活性を有する広域抗生剤を開始する! スライド3
FN発症時のリスク評価とガイドライン
#4. ①FN発症時のリスク評価 ようするに、全身状態不良、血行動態不安定、高齢者などがハイリスク MASCCスコア 他のリスクとしては
高度粘膜障害(化学療法の副作用)
意識障害
カテーテル感染
肺炎
深い(<100)neutropeniaが7日以上予想される スライド4
#6. ②初期抗菌薬 基本的にまずは単剤治療。ただし肺炎や血行動態不安定は併用考慮。
発熱から60分以内の抗菌薬投与が推奨されている
血培の迅速結果や過去の感染、監視培養結果も参考にする
発熱がなくとも、感染が疑わしければ治療を開始する 30分以内の方が死亡率減らせる
という報告も! Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:3799-803.
J Clin Oncol. 2016;34:2054-60. Clin Infect Dis. 2010;51:381-9. アミノグリコシドをかぶせるメリットは乏しい
(が、施設毎の感受性次第であろう) 色々報告はあるが、
CFPM/TAZPIPC/MEPMの優劣は
ついていない スライド6
初期抗菌薬の選択と使用法
#7. ②初期抗菌薬 抗MRSA薬を最初から投与すべきとき
・肺炎
・ショック
・カテ感染疑い
・SSTI
(・高度粘膜炎) 死亡率高い!(肺炎21倍、ショック11倍) GPCリスク高い 一般的なFNに対して
初期から抗MRSA薬併用は予後改善せず、副作用をふやす Antimicrob Agents Chemother.2019;63:e01250-19.
Cochrane Database Syst Rev.2017 Jun 3;6(6):CD003914. スライド7
#8. CVカテーテル感染のマネジメント
カテ感染の診断 →Differencial time to positivity
DTPがCV血培と末梢血培で2hr以上差があれば、CV感染が怪しい
黄色ブドウ球菌、緑膿菌、真菌(カンジダ)、抗酸菌などは即CV抜去
持続菌血症やseptic emboli、ショックなども即抜去
敗血症性血栓症をきたすと長期抗菌薬投与が望ましい
表皮ブドウ球菌による場合で、抗菌薬に速やかに反応し、かつ血液培養も速やかに陰転化すればカテーテル温存できるかも 黄色ブドウ球菌菌血症持続期間と死亡率 Clin Infect Dis. 2020;70:566–73.
Ann Med. 2014 May;46(3):163-8. カテーテル抜去有無での再燃率 スライド8
#9. 広域抗生剤の使い分け例 広域抗生剤の使い分け TAZ/PIPCとCFPMの違い5つ
※少し難易度高いので、抗生剤の勉強すこしかじってから
の方が良いです E. faeciumは
抗MRSA薬必要 ただし、
1st choiceはMEPM JAMA. 2018;320:984–94. スライド9
#10. 抗MRSA薬の長所短所 抗MRSA薬はVCMが一番エビデンスあり
しかし、特に移植時は腎障害を起こす薬を複数使用するため、VCMを使いづらい場合がしばしばある スライド10
抗菌薬の変更タイミングと継続期間
#11. 組み合わせによる副作用 Clin Infect Dis. 2017;64:116-123.
Clin Microbiol Infect. 2020;26:696-705. TAZ/PIPC+VCMはCFPM+VCMやMEPM+VCMよりも有意にAKIが多い スライド11
#12. ③抗菌薬の変更タイミング 臨床経過安定していても、発熱つづく場合はempiricalに変更する
抗MRSA薬は必須となる感染症が同定されなければ早めにoffも可
経過中に増悪していく場合は耐性GNRや嫌気性菌、真菌も考慮
発熱続いて熱源が同定されない場合抗真菌薬を考慮
3日以上発熱続く場合はあらためて熱源の探索をする スライド12
#13. ④抗菌薬の継続期間 熱源同定されてもされなくてもNeutropeniaから回復するまでは
抗菌薬を継続する
もし十分期間の抗菌薬が投与され、臨床経過も良好であれば
予防投与にde-escalationも可 Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 3;1(1):CD012184. スライド13
予防的抗真菌薬の適応と使用
#14. ⑤予防キノロンの適応
深い好中球減少 7日以上で考慮
(leukemiaのケモ、リンパ腫の救援化学療法、移植など)
7日以上血球下がらない場合は予防は"ルーチンには"不要
(高齢者リンパ腫や骨髄腫などで予防投与考慮すべきときもある)
抗MRSA薬や消化管滅菌によるGPCの予防は推奨されない
Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18;1(1):CD004386. キノロン内服は
感染症による死亡率を
0.51倍に減らした スライド14
#15. 馴染みがない抗真菌薬のまとめ ミカファンギン
キャスポファンギン ボリコナゾール フルコナゾール イトラコナゾール リポソーマル
アムホテリシンB
(アムビゾーム) po po Po/iv iv iv 副作用すくない 濃度上がるまで時間かかる、マズイ アゾール系→CYP3A4阻害で
カルシニューリン阻害剤の
血中濃度↑ 内服は濃度上がるまで時間かかる
ゆるくTDMする(2-5 µg/ml)
肝障害
点滴は保護成分による腎障害 腎障害
発熱
電解質(K Mgなど) 予防は50mg
治療は150-300mg
少し肝障害 Candida
albicans Aspergillus
fumigatus 耐性Aspergillus 耐性Candida Fusarium
Mucor 侵襲性アスペル
1st choice カンジダ血症
1st choice FN empiric治療で適応ある スライド15
#16. ⑥予防的抗真菌薬の適応
予防的抗真菌薬投与は長期好中球減少が予測される患者で
推奨されている (e.g. 白血病の化学療法、造血幹細胞移植など)
invasive fungal infection (IFI)の中でも、とりわけカンジダ血症の死亡を減らすことが目的
→FLCZ(200 or 400mg)をはじめとし、各種薬剤でエビデンスあり IFIによる
死亡率 IFI発生率 64のRCT結果のメタアナリシス (抗真菌薬あり vs なし) J Clin Oncol 2007;25:5471-89 ひし形が左によればよるほど予防群の結果がよい 白血病患者において、IFI死亡率を0.66倍に、IFI発症率を0.69倍に減らした スライド16
カンジダ血症のマネジメントと治療
#17. ⑥予防的抗真菌薬の適応
アスペルギルスのリスクとしては
・アスペルギルスの既往
・14日以上の深い好中球減少
→こういったリスクのある患者では抗アスペルギルス活性のある抗真菌薬(イトリゾール,ファンガード,ボリコナゾール)による予防を考慮する 抗アスペルギルス活性
あり vs フルコナ
(おもにイトリゾール vs フルコナ) Br J Cancer. 2012;106:1626-37. HEPAフィルターによる予防(クリーンルーム)もアスペルギルス予防 実臨床ではフルコナ/イトリゾールがよく使用されている
アゾール× or 内服×でMCFG(点滴)
アスペル既往ある患者の二次予防ではVRCZが多い スライド17
#18. ⑦抗真菌薬による治療開始 4-7日以上の持続するFNはempirical(経験的)に真菌も考慮する
状態安定していても、CTで結節ありやβDグルカン陽性などを参考にしてpreemptive(先制)治療も考慮
肺結節あり→ボリコナ or LアムホテリシンB
発熱のみ→ミカファンギン/キャスポファンギン が選択されやすい 1970年代はFNで死亡後、解剖で播種性カンジダが判明することが多かった N Engl J Med. 2002;346:225-34. 解熱しないFNの
ボリコナvsLアムホB
RCT 解熱しないFNの
キャスポファンギンvsリポアムホRCT N Engl J Med. 2004;351:1391-402. スライド18
#19. 特に危険なカンジダ血症 カンジダ血症の推奨項目
早期に有効抗真菌剤を投与
ショック/FNでは
キャンディン or Lアムホで治療開始
血液培養の陰性化確認
カテーテル抜去
眼科チェック
心エコー
IEや播種性の場合は長期治療
死亡率30%前後。
治療の遅れは死亡率上げる
Antimicrob Agents Chemother. 2005;49:3640.
Med Mycol. 2019 Aug 1;57(6):659-667. マネジメントの適切さが
死亡率を大きく左右する 適切な抗真菌薬投与
ソースコントロール進展確認 スライド19
初期治療に反応しないFNの対応
#20. ⑧予防的抗ウイルス薬の適応
HSV抗体やVZV抗体陽性の既感染移植患者は再活性化予防としてアシクロビル/バラシクロビル内服による予防を行う Ann Intern Med. 1984 Jun;100(6):823-8. Blood. 2006 Mar 1;107(5):1800-5. HSV再活性化freeの割合 VZV再活性化率 予防投与期間 予防投与期間 少なくとも1年は予防投与継続する
(最近は2年投与のエビデンスもある) スライド20
#21. 初期治療に反応しないFNのまとめ ・CTをとってなければCTとる
・感染源の再確認(カテは大丈夫?)→血液培養再検も考慮
・広げる余地があればGNR and/or GPCカバーを広げる
・真菌治療を開始する(フルコナゾール予防→ファンガードなど) ①2-4日解熱せず ②4-7日解熱せず ・感染源の再確認。unstableな状態であればCTをとる
(特に肺/副鼻腔。アスペルギルスのチェック)
・GNRカバーを広げる(ESBL考慮してセフェピム→メロペネムなど)
and/or GPCカバーを広げる(VCM/TEIC/DAPTなどの追加)
・血液培養などで菌が同定されればそれに対応した抗菌薬へ 基本は血球回復まで広域抗菌薬/抗真菌薬を継続
状態安定しているようであればde-escalationも可能かも?
発熱がさらに遷延したり、一度解熱した後再度発熱するようなら
しつこく血液培養をとる スライド21
FNの治療と予防に関するまとめ
#22. グラム陰性桿菌 (GNR) グラム陽性球菌 (GPC) ウイルス 真菌 ニューキノロン系
(レボフロキサシンなど) 予防はしていない
(副作用と死亡率のバランス) フルコナゾール
イトラコナゾール
ボリコナゾール
ミカファンギン アシクロビル
(HSV, VZV) ST合剤 FNリスク高の場合予防
(leukemiaのケモ、lymphomaの救援化学療法、移植など) 細胞性免疫の障害
(同種移植後の免疫抑制剤)
(±ALLケモ、lymphoma救援ケモ、濃厚な治療歴のmyelomaなど) 長期好中球減少
(leukemiaのケモ、移植)
長期間の細胞性免疫の障害
(同種移植後の免疫抑制剤) 血液内科医の
頭の中 治療
予防 治療 予防 予防 治療 治療 スライド22
#24. Take home message ・FNとは、好中球が500/ul未満の患者に起こる発熱のこと
早期に抗菌薬治療を開始しないと死亡リスク↑
・FNの治療 →まずは抗緑膿菌活性をもつ
セフェピム、タゾバクタム/ピペラシリン、メロペネム
のいずれかを開始する
・ショック、肺炎、カテ感染、SSTIのFNは抗MRSAカバーも
最初から加える
・解熱しないFNは経験的にescalationし、血培再検や画像チェック
4-7日以上の持続するFNは真菌も想定。
動画でのスライド解説もあります→
youtubeで「はらDちゃんねる」で検索
もしくは概要欄のリンクをチェック! スライド24