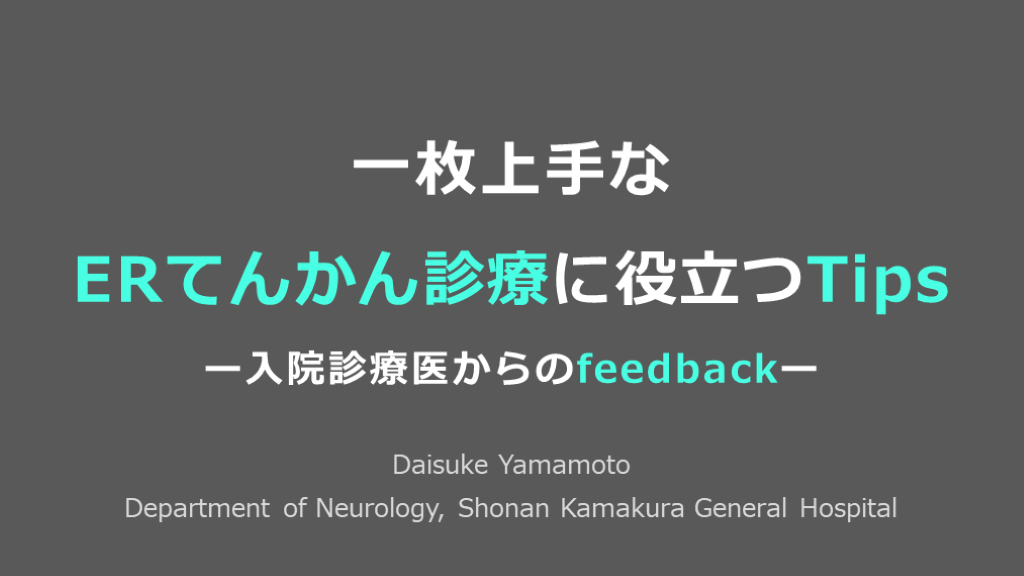
































































































関連テーマから出会おう。
閲覧履歴からのおすすめ
1/98
関連するスライド
Primary survey 気道(A)の異常【解剖・気道確保を中心に】
三谷雄己
185061
324
【デキレジ】けいれん - ERでの初期対応 -
やまて
823112
3308
一枚上手なERてんかん診療に役立つTips
山本大介
Award 2024 受賞者
医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院
148,486
545
概要
実臨床でてんかん診療において役に立つ知識が網羅的に学べます。ERから引き継いだ病棟診療医の立場から、是非押さえておいていただきたいポイントに言及しています。
■動画解説あり https://www.youtube.com/watch?v=HxEqYQuucaU
■「みんなの脳神経内科」もご参照下さい。https://www.amazon.co.jp/dp/4498328736
本スライドの対象者
研修医/専攻医/専門医
投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!
0 件のコメント
山本大介さんの他の投稿スライド
片頭痛診療、はじめの一歩。
山本大介
274,613
626
ミニマム!運動障害の患者さんに出会ったら
山本大介
151,356
290
Common diseaseである脳卒中後てんかんを学ぶ。
山本大介
123,990
347
このスライドと同じ診療科のスライド
【論文紹介】健忘患者の抗アミロイドβ抗体治療におけるMini-Mental State Examinationの閾値に対する改訂長谷川式簡易知能評価スケールのカットオフ値の検討
山上圭
1,611
7
抗アミロイドβ抗体薬(レカネマブ・ドナネマブ)の選び方/考え方
山本大介
2,369
20
みんなの振戦診療2025 振戦が得意になる!
山本大介
16,641
66
誰も教えてくれない!SKGH流神経診療100のTIPS!PART②
山本大介
10,232
41
頭痛診療レビュー ~救急対応から一次性頭痛の診断・管理まで~
花岡謙
14,895
54
地域包括ケアシステムにおける認知症診療
やまと診療所 AHC-ACADEMY OF HOME CARE-
2,389
7
テキスト全文
ER診療と入院診療の違いと目的
#1.
Daisuke Yamamoto Department of Neurology, Shonan Kamakura General Hospital 一枚上手な ERてんかん診療に役立つTips ー入院診療医からのfeedbackー
#2.
Introduction ER診療と入院・外来診療は求められるものもゴールも異なります。 ER診療とその後の診療は、お互いにフィードバックが存在することが望ましいですが、現実的にはその機会の乏しさもあります。 このプレゼンテーションでは、ERでのてんかん診療をレベルアップするために役立つTIPSを、入院治療医の立場からフィードバックさせていただき、よりよい診療を目指すことが目的です。
急性症候性発作の定義と理解
#3.
急性症候性発作 について
#4.
急性症候性発作の定義 「急性症候性発作」は、頻出する重要な定義であり、改めて理解し使えるようにする。 急性症候性発作について、ガイドラインの記載は以下のごとく。 「急性症候性発作とは、代謝性、中毒性、器質性、感染性、炎症性など 急性中枢神経障害と時間的に密接に関連して起こる発作である。」 急性症候性発作を、ERで「発作」を見たときに、てんかんによる発作と区別する時に意識的に使用してください。
#5.
前提となる 用語を理解する。 急性症候性発作(acute symptomatic seizure):頭部外傷や脳卒中、硬膜下血腫、脳外科手術、中枢神経感染症、脳炎などが原因の急性脳機能障害によって誘発されたてんかん発作。 急性症候性発作は、誘発性発作(provoked seizure)とも表現される。 対比される表現は、非誘発性発作である。 てんかんとは、“非誘発性発作”を反復しうる疾患である。 =>ER診療においては、その発作がてんかん(epilepsy)による発作なのか、 急性症候性発作/誘発性発作なのかを判別しようとする思考が重要です。
けいれん発作とてんかんの言葉の整理
#6.
けいれん発作、てんかんなどの言葉使いを整理! 1 けいれん(convulsion)は、脳由来ではない可能性も含んだ曖昧な表現であり、使用は 非推奨。 脳由来の異常電気放電による発作に対応する言葉は発作(seizure)。 これだとわかりにくい、と考えるなら、 けいれん発作(convulsive seizure) という表現を。 けいれん、けいれん発作は症候を指した言葉。 一方、てんかん(epilepsy)は、反復性のけいれん発作を起こしうる状態の、診断名。
#7.
けいれん発作、てんかんなどの言葉使いを整理! 1 けいれん → convulsion 曖昧表現である。 けいれん発作 → convulsive seizure 脳由来の「けいれん」 非けいれん性発作 → non-convulsive seizure 「けいれん」のない発作。 発作 → seizure つまり、convulsive+non-convulsive seizure。 てんかん → epilepsy seizureを反復しうる疾患のこと。 会話において誤解が起こりにくいよう、「けいれん」はなるべく使用しないのが望ましいです。ここではけいれん発作で説明していきます。
#8.
けいれん発作とてんかん けいれん発作 は、急性症候性発作かもしれず、必ずしも「てんかん」ではない。よって、一時的には抗てんかん薬治療が必要かもしれないが、永続的には必要ない。 てんかん (epilepsy)は、長期間の抗てんかん薬治療が必要である。 初発のけいれん発作を見たときには、それがてんかんによる発作かどうか?誘発性発作なのか?は、区別ができない。ただし、双方は治療方針・検査方針が異なるので、混同してはいけない。
#9.
けいれん発作は、結果である。 けいれん発作の原因について、調べる必要がある。 2 けいれん発作自体も問題だが、けいれん発作に至った原因を評価しなければならない。その原因を治療しなければならない可能性がある。 初発のけいれん発作を見たら、けいれん発作に至る原因は?と考えること。 すなわち、急性症候性発作としての可能性を検討する必要がある、と言い換えられる。
#10.
けいれん発作の原因は 大脳皮質にある。 大脳皮質の細胞障害や機能異常が、けいれん発作の誘因になりうる。 脳梗塞・ヘルペス脳炎による大脳皮質の破壊性刺激は、けいれん発作を引き起こす。 アルツハイマー病による、大脳皮質細胞変性も原因になる。 自己免疫性脳炎や、代謝性脳症による大脳皮質機能障害も原因になりうる。 大脳皮質の破壊、機能障害が、けいれん発作の誘因になる。
急性症候性発作の原因と重要疾患
#11.
急性症候性発作 の原因:以下を想起する。 頻度の高いもの: 脳卒中、低血糖、低Na血症、アルコール離脱 薬剤性: NSAIDs+LVFX、テオフィリン、ベンゾジアゼピン離脱 頻度は高くないが鑑別すべき重要なもの: 脳炎(感染性・自己免疫性)
#12.
急性症候性発作の原因疾患:てんかん診療ガイドライン2018
#13.
急性症候性発作の 可能性を十分考慮する。 けいれん発作をみたら、急性症候性発作をまずは想起しよう。原因のあるけいれん発作であれば、原因についての対応が もちろん必要である。 けいれん発作のみへの対応では足りない。 それがCriticalな病態の可能性がある。ヘルペス脳炎や自己免疫性脳炎など、クリティカルな疾患も混ざっている可能性がある。
#14.
急性症候性発作のうち、 まずは コモンな脳卒中を想起する。 脳卒中発症とともにけいれんを発症することがある。 新規発症のけいれん発作では、脳卒中をまずは検討すべき。 けいれん対応のみならず、その原因が脳卒中であった場合には、脳卒中の治療を行わなければならない。まず、脳卒中の可能性について検討すべく、MRI評価をする必要がある。
#15.
急性症候性発作の重要疾患 ①脳梗塞 脳梗塞の血栓回収療法・tPA療法の機会を逸しない。 ②単純ヘルペス脳炎 忘れがち。治療の遅延は大きな後遺症につながる。 =>治療の遅延が問題になる疾患はER的には留意が必要だろう。
MRI・髄液検査の適応と目的
#16.
急性症候性発作の原因薬剤 てんかん閾値を下げる薬物は上記のごとく。 これらが導入された後に発作を来した場合は、 これら薬剤が発作のきっかけになったかもしれない、と考えてみる。 てんかん診療ガイドライン2018
#17.
『●歳 男性、自己免疫疾患でステロイド内服中である。 今回、初発のけいれん発作を認め、救急搬送された。 採血では炎症反応上昇を認めている。項部硬直もあり。 中枢神経系感染症評価のため髄液検査を施行し、糖低下を伴う多形核球優位の 髄液細胞数増多あり。細菌性髄膜炎疑いで、ERで抗菌薬治療を開始している。 けいれん発作は「急性症候性発作」として理解している。』 以上の患者さんの、入院診療をお願いします。 入院診療医へのプレゼンテーション例 急性症候性発作を理解し、明確に伝える。
#18.
急性症候性発作という表現を意識的に使えるようになる。 急性症候性発作の原因病態と、原因薬剤、 除外すべき疾患について理解する。 TIPS 1
#19.
MRI・髄液検査の indicationについて
#20.
何を見たくてMRIを撮る? 検査の条件は? 初発けいれん発作であれば、いずれかのタイミングでMRI評価は行われる必要がある。 比較的高齢者であれば、脳卒中による急性症候性発作の鑑別目的で、ERでの頭部MRI施行は検討される。 発作後神経症状の残存があるならMRIは施行する。
中枢神経感染症の鑑別と対応
#21.
MRI評価。現実的には 脳梗塞>器質的病変>脳炎 繰り返しになるが、脳梗塞があるのかどうか?が第一の論点。 脳梗塞以外には、脳腫瘍/陳旧性病変など器質的病変の評価。 頻度は少ないが、脳炎を評価する目的。
#22.
発作の反復 × 脳炎 てんかん重積状態(status epilepticus:SE)が、急性脳炎に由来する可能性は高いわけではない。 SEは、急性脳炎の5-18%で認められた。 免疫介在性脳炎を疑うとき:①初回評価でSEの原因がはっきりしなかった場合、 ②特に一般的な治療介入によっても遷延性・難治性の発作を認めた場合。 Medicine 2016;95:30 Neurology 201;85:464-70. Epilepsy Currents 2014;14:43–49
#23.
MRIのindicationについて: ミニマムは脳梗塞の除外目的。 積極的なMRIの適応は、高齢者、反復する発作、 神経症状の残存する場合。 TIPS 2
#24.
何を見たくて髄液検査? 中枢神経感染症(細菌性髄膜炎、ヘルペス脳炎など) 自己免疫性脳炎 が鑑別になる場合には髄液検査を行う。 よって、免疫不全状態の患者では積極的に検査する。
#25.
中枢神経系感染症を 心配する場合は? 二つの代表疾患のキーワードは以下のごとく。 免疫不全のリスクに加えて、これらのキーワードを拾って対応するしかないか。 細菌性髄膜炎のコモンな症状:多い順(UPTODATE) 強い頭痛、発熱、項部硬直、意識障害(GCS<14)、悪心、けいれん発作 単純ヘルペス脳炎のコモンな症状:(UPTODATE) 発熱+意識障害、新規発症けいれん発作、脳神経障害、片麻痺、失語、構音障害 少なくとも、発熱がある場合には注意する必要があると思う。
HSV脳炎の重要性と対応
#26.
自己免疫性脳炎を 心配する場合は? 自己免疫性脳炎の診断で、 Grausの診断基準は有名。 ただし、これでもっても決め手には欠ける。 少なくとも、 髄液細胞数増多は客観的なヒントに なりうる。 神経治療 2018;35:231-236
#27.
何はなくとも ER的には、HSV脳炎。 HSV脳炎は成人において急性ウイルス脳炎の中で最も頻度が高く、起因ウイルスが判明したウイルス性脳炎の60%、脳炎全体の20%を占める。 治療介入の遅延が、シビアな神経後遺症につながる。 「脳炎」による急性症候性発作においては、HSV脳炎の可能性を追求すること。 Internal med 2000;39:894-900
#28.
脳炎について どのように考えて どう対応すべきか
#29.
脳炎/脳症の ER対応 Antaa slideで解説スライドあります。 解説が少ない領域です。 どのように整理して対応するかをご参照ください。 脳炎/脳症は、てんかん診療と密接な関係のある病態です。
#30.
単純ヘルペス脳炎のみ、最低限カバーできれば及第点としてよい。 ヘルペス脳炎は早期治療介入が必要である。 ヘルペス脳炎は、MRIで画像異常が得られる可能性が高い。 髄液異常も指摘できる可能性が高い。 ・・・・・ただし、所見に乏しいこともある。難しい。 脳炎→最低限は単純ヘルペス脳炎のカバー 自己免疫性脳炎の評価については、 ERではわからない。
てんかんの診断と症候の確認
#31.
単純ヘルペス脳炎を 疑うポイント 易感染性背景の場合。 基礎疾患あり。また、 アルコール多飲、高齢者など 特徴的なMRI所見、髄液異常 新規発症の 比較的難治性けいれんのとき 発熱、意識障害、 高次脳機能障害の合併
#32.
HSV脳炎の対応 →ガイドラインも参照。 疑った場合は、 髄液検査を施行する。 髄液一般+髄液HSV-DNA PCR 提出する。 アシクロビル 10mg/kg*3回/dayを投与する。 ヘルペス脳炎でなくても、 アシクロビルを投与することに問題はない。迷った場合、疑う場合は迷わず投与、というポリシーになっている。 処方例)アシクロビル500-750mg + NS 250ml 1回2時間で投与、1日3回 ※腎障害・脱水時には注意。
#33.
髄液検査のindicationについて: 目的① 中枢神経感染症の鑑別のため 目的② 脳炎の鑑別のため 特にHSV脳炎の可能性を追求する TIPS 3
#34.
てんかんの診断について
#35.
確認してほしい症候 =>共同偏視とけいれんの側 古典的だが、役に立つ。 共同偏視の側 X けいれん発作の側 の組み合わせにより、 急性症候性発作(破壊性障害) と てんかん発作(刺激性障害)が 区別できる。
てんかん重積状態のMRI所見と鑑別
#36.
共同偏視+けいれん発作 の組み合わせ 共同偏視の向きと、 けいれん発作の組み合わせから、 病態推測可能な、有用なルールがある。
#37.
たとえば、左大脳半球の 脳梗塞による急性症候性発作 の場合には、 左共同偏視+右半身のけいれん発作 となる。 たとえば、左大脳半球が焦点の てんかん発作の場合には、 右共同偏視+右半身のけいれん発作 となる。 このルールは、破壊性障害と刺激性障害 (急性症候性発作と純粋なてんかん発作)を 区別する時に有用である。
#38.
てんかんの診断の一助になることとは? 急性症候性発作とてんかん評価の参考になるどっち向いていたか問題は重要。 TIPS 4
#39.
てんかん重積状態で MRI信号変化があるのか? ERでけいれん発作疑いでMRIを施行した場合に知っておくべき知識である。 てんかん重積状態でのMRI所見を抑えておく。 MRI画像所見によって、てんかんを診断できることもある。
#40.
てんかん重積状態のMRI所見について てんかん重積状態でMRIでの信号変化を認める。 画像評価でてんかんを診断できるので役に立つ。 画像変化を来しやすい部位 大脳皮質 視床枕 小脳 そして、発作に関連して過還流と なる。MRAに注目すると、 発作側が血管描出が強調されている。 脳卒中 2017;39:446-450 大脳皮質のHIGH 視床枕のHIGH 右側MCAの過還流
SE・RSEの治療と管理のポイント
#41.
てんかん重積状態のMRI所見 脳卒中 2014;36:247-254 DWIでの大脳皮質の信号変化に注目する。 対側の小脳に信号変化も来し得る。 しかし、ここでもpit fallがあり・・・・ てんかん重積状態のみがこの信号変化を来すわけではない。
#42.
てんかん重積状態 VS 脳炎 VS 脳梗塞 大脳皮質の高信号変化の鑑別。 悩むところだが、臨床症状と髄液所見と合わせて評価するしかないだろう。 鑑別の可能性は、SE・脳炎・脳梗塞である。
#43.
てんかん重積状態 VS 脳炎 VS 脳梗塞 てんかん重積状態と、脳炎(特にHSV脳炎)の区別は画像のみでは困難かもしれない。信号変化がある場合には、髄液検査は必要だろう。 また、このような場合、念のためACV使用は検討される。 脳梗塞は画像的にある程度鑑別可能ではあろう。(時に難しいこともある。)
#44.
SEのMRI所見について: 大脳皮質の高信号変化を知る。 視床の信号変化を知る。 MRAでの過還流所見を知る。 DWIでの大脳皮質高信号の鑑別を知る。 TIPS 5
#45.
ERからの外来への紹介。 脳波オーダーがあると 嬉しい。 けいれん発作を認めた場合には、後日の専門外来への引継ぎはあってしかるべきです。 専門外来への受診スパンがあくなら、脳波オーダーしてから紹介していただけると嬉しい。 専門外来で行うこと=>脳波検査オーダー + 脳MRI オーダー となる。 また、発作後早期に検査を行えると、異常所見の検出力があがる。
入院の適応と専門外来への紹介
#46.
脳波の検出力の変化 Lancet 1998;352:1007-1011. 脳波検査で、発作間欠期にてんかん性の変化を捕まえることは容易ではない。 感度:発作間欠期てんかん性放電が、初回の脳波検査で20-55%のてんかん患者で検出される。 感度を上げるために:脳波検査のタイミングは検討される。発作と発作間欠期てんかん性放電の検出は時間的に関連している。 時間的な検出力の検討では、24時間以内で62%、24-48時間で51%、48-72時間で40%、72時間以降で31%の検出率であった。 =>ERから、フォロー外来までにオーダー入れてもらえるなら助かる! J Clin Neurophysiol. 2017;34:434.
#47.
脳波検査オーダーはありがたい。 脳波異常の検出力を高める。 てんかんで必要な検査の目的の意味を知る。 TIPS 6
#48.
入院のindication: 残存症状があるなら入院 発作後何も残存症状がないなら帰ってよい。 症状残存あるなら、入院経過観察もしくは、ERでの経過観察の継続でよい。 また、残存症状があるなら、急性症候性発作を検討する。つまり、脳梗塞や脳炎など疑う。 この場合には、MRIや髄液検査を追加することとなる。
#49.
Disposition 初発けいれん発作を帰宅対応とする場合は、必ず専門外来へ引き継ぐこと。 てんかん発作再燃なく、誘因に対して介入されており、神経症状の残存がないなら帰宅も検討。 神経症状の残存があるなら、必ず入院対応とする。 神経症状の残存があるなら、MRIや髄液検査施行などの追加検査を行う。
#50.
入院のindicationは? 残存症状がある場合。 発作の反復がある場合。 TIPS 7
抗てんかん薬の選択と特徴
#51.
SE・RSEについて
#52.
改めて、SEについて 理解する てんかん重積状態 = status epilepticus: SE てんかん発作が持続的に生じる状況である。 SEに関わる覚えるべき時間は二つで、5分と30分。 てんかん重積状態の2つの特徴 ①自然に終息しそうにない発作 5分続くと自然終息しなくなる。 ②神経後遺症を来す可能性のある発作 30分続くと神経後遺症をきたすリスクがある。
#53.
SEの 5分と30分 5分:5分発作が続くなら、自然とん挫は困難なので、点滴薬での発作抑制を行う必要がある。「SE」では救急対応が必要である。 30分:脳機能障害が生じないよう、発作抑制をなるべく早期に達成する必要がある。
#54.
SEについて知ること てんかん重積状態の定義は5分以上の発作、30分以上の発作。この場合は点滴薬での発作抑制が必要。救急要請のindicationの説明にも役に立つ知識。 TIPS 8
#55.
改めて、RSEについて 理解する 難治てんかん重積状態 = Refractory status epilepticus: RSE 1st line, 2nd line治療を行っても発作抑制できない状態がRSEである。 言葉として、SEとRSEを今一度区別しましょう。 RSEでは発作開始から60分程度で3rd line 治療が必要なこと、を抑える。
新規抗てんかん薬の利点と使用法
#56.
SE・RSE 治療整理 5分-30分-60分 何度も見慣れたガイドラインのフローチャートだが、要素を整理して改めて理解して下さい。 1st, 2nd, 3rd で使う薬剤は、それぞれのSEステージで異なります。 SEの5分、30分に加えて、RSEの60分も覚えてください。 60分以降にはRSEとして3rd line治療に移る必要があります。 神経治療 2019;36:457-460
#57.
RSEについて知ること 1st line+2nd line therapyでも発作抑制できない状態を指す。60分で判断する。 TIPS 9
#58.
改めて、 1st -2nd -3rd line therapy について理解する。 1st ベンゾジアゼピン 短時間作用のみ=>30分で効果切れる。足りないかもしれない。 2nd 抗てんかん薬 長時間作用あり=>次の発作を防ぐ。追加は時に過剰かもしれない。 3rd 静脈麻酔薬 1st , 2nd 治療でだめなら=>RSEの判断。判断は躊躇せず。
#59.
SEで使用する薬剤 1st line :ベンゾジアゼピン 抑制系を強化する。 2nd line :抗てんかん薬 興奮系を抑制する。 1st lineと2nd line 治療のロジックも大まかに理解しておく。 1st line:抑制系の強化 2nd line:興奮系の抑制 3rd line:抑制系の強化 SEでの発作抑制はGABA系へのアプローチが主軸になる。 抗てんかん薬は主軸でないことは知っておくことは重要。 3rd line :MDZ/プロポフォール/バルビツール系抑制系を強化する。 Emer-Log 2019;32:15-19
#60.
SE・RSEの治療について整理すること 1st line~3rd lineまで整理する。 2nd lineの意味、3rd lineの意味を理解する。 TIPS 10
AEDの使い分けと特徴の理解
#61.
RSEについて重要な知識 「発作が続けば続くほど、不利になる。」 発作を発症すると、シナプス膜上の抑制系GABA A受容体の減少、興奮系NMDA受容体、AMPA受容体の増加を来す。このため、時間経過とともに、GABA A受容体に作用するベンゾジアゼピンに対して、急速に抵抗性を生じる。 薬効は時間と共に急速に失われる。 発作抑制について、後手に回るのは悪手である。
#62.
RSEのマネジメント 中途半端な判断は控える。 発作抑制が達成できていないが、もう少しこのまま様子をみてみるか・・・・という判断は悪手になることが多い。 発作が続けば続くほど、発作抑制が困難になる。 ERにいるうちに、アクションを決めないと入院後困る。 入院してからRSE治療方針について考えよう、というのは不適である。
#63.
3rd line治療はためらわず。 悩むならやるしかない。 中途な対応としないことは重要である。 TIPS 11
#64.
抗てんかん薬について
#65.
AEDの抗菌薬に例えて 理解する。 わかりやすく伝える技術は重要です。 医師の共通言語としての、「抗菌薬」に例えて、抗てんかん薬(AED)を 説明してみましょう。 AEDのイメージを作りましょう。 レジデントやスタッフへのAEDのニュアンスを伝えましょう。
レベチラセタムとラコサミドの比較
#66.
「抗菌薬」に例えて説明。 Narrowか?Broadか? 抗菌薬に例える手法は非専門医の先生方に伝わりやすいので、好んでいます。 「CBZ(カルバマゼピン)はCEZ(セファゾリン)です」。 「LEV(レベチラセタム)はMEPM(メロペネム)です」。 など、抗菌薬に例えるとイメージがわきやすいです。また、抗てんかん薬と抗菌薬の特徴において、ニュアンスが類似しているところもあります。抗てんかん薬には 守備範囲があり、抗菌薬同様spectrum (Narrowか? Broadか?)で語られます。
#67.
Narrowとは? =焦点性てんかんに有効である、 ことを意味します。 <narrow spectrumのAED> 焦点性てんかんとは、脳の特定部位から異常放電を来たし、てんかん発作に至る、てんかん分類。 焦点性てんかんを考慮する場合には、narrow spectrumの抗てんかん薬が治療薬で選ばれます。 代表的な抗てんかん薬はCBZです。 抗菌薬に例えて、CEZと説明します。
#68.
Broadとは? =焦点性てんかん・全般性てんかん 双方に有効である、こと意味します。 <broad spectrumのAED> 全般性てんかんとは、脳全体に異常放電の発火を来し、てんかん発作に至る てんかん分類です。 発作分類が、焦点性か、全般性てんかんか区別しにくい場合もあります。 この場合は、双方に有効なbroad spectrumの抗てんかん薬を選びます。 代表薬剤はLEVです。 抗菌薬に例えてMEPMと説明します。
#69.
古典的抗てんかん薬について 従来薬=>CBZとVPAが代表薬 従来薬の代表薬は、カルバマゼピンとバルプロ酸です。 カルバマゼピンは=>昔からの、焦点性てんかんの第一選択薬 です。 バルプロ酸は =>昔からの、全般性てんかんの第一選択薬 です。 これら2剤は昔から現在までも、第1選択薬の位置づけです。新規AEDの出現で、使用頻度は減っています。その理由は、薬剤相互作用(併用薬の効果を変えてしまう)や薬剤の副作用によります。よって、従来薬の処方機会は減り、新規抗てんかん薬が選択されることが多くなっています。 (第1世代)
#70.
新規抗てんかん薬について 新規=>使いやすい 近年登場した抗てんかん薬は、新規抗てんかん薬として位置付けられます。 代表薬は、レベチラセタム。抗菌薬に例えるなら、カルバペネムをイメージします。 新規抗てんかん薬の特徴は、「副作用の少なさ」と言えるでしょう。 代表薬であるレベチラセタムは、ブロードスペクトラムで、副作用が少ない、となると、非専門医にとっては使用しやすい抗てんかん薬である、と言えるでしょう。 薬剤評価は私見です。 (第2-3世代)
AEDの特徴と選択基準の整理
#71.
新規と従来薬の それぞれの特徴のまとめ 副作用 薬物相互作用 薬価 新規抗てんかん薬 少ない 気にしない 高い 従来薬 多い 気にする 安い 新規抗てんかん薬は従来薬と比較し、使用しやすい薬剤と言えます。 しかしながら、新規抗てんかん薬の唯一の弱点は、薬価といえます。 コストについては、患者さんと相談する必要はあります。 (第1世代) (第2-3世代)
#72.
AEDの特徴まとめ Narrow spectrum? Broad spectrum?で区別される特徴がある。 新規? 従来薬?で区別される特徴がある。
#73.
AEDの使い分けのポイント いずれかの抗てんかん薬を選択する場合には、考慮する条件があります。 臨床で、よく出会うポイントについて列挙します。 抗てんかん薬の選択において、考慮されるポイント ▲薬剤相互作用を気にする場合。 ▲怒りっぽい症状が既に知られている。 ▲第1選択薬で眠気が問題になった。 ▲薬価が問題になる。
#74.
使い分けにおける薬剤特徴まとめ 薬物相互作用が少ない:新規抗てんかん薬 薬物相互作用が多い :CBZ 怒りっぽくなる :LEV 気分が落ち着く :CBZ, VPA, LTG 眠気がでやすい :LEV, CBZ 眠気がでにくい :LTG, LCM, VPA 薬価が高い :新規抗てんかん薬 薬価が安い :従来薬
#75.
AEDは抗菌薬に例えて説明しよう: Narrow spectrum =>CEZ =CBZ Broad spectrum =>MEPM =LEV 伝わりやすいし理解しやすい。 TIPS 12
AEDの総論とER診療のフィードバック
#76.
レベチラセタムについて知る。 LEVとは:汎用性の高いAED 最も頻用されるAEDが、レベチラセタムです。 今一度、LEVとはどんな抗てんかん薬かを理解しましょう。 LEVの特徴は使いやすさにつきます。
#77.
添付文書で示されている、一般的な使用量は1,000mg/day。 レベチラセタムのメリット、デメリットは以下。 メリット:薬剤相互作用が少ない。副作用が少ない。漸増の必要がなく、有効用量を最初から投与できる。つまり、急性期に使いやすい。点滴製剤がある。 デメリット:眠気が強く、使用継続できない症例がある。また、易怒性を誘発することがある。 レベチラセタム 新規抗てんかん薬で、使用しやすい抗てんかん薬の1つ。非専門医が習熟すべき、薬剤の1つ。
#78.
レベチラセタム ① 急性期使用に長じている。 長所 注射製剤もあり、かつ、最初からてんかん発作抑制に十分な有効用量を投与できる。 ERはじめ、急性期病院の現場での使い勝手のよさがある。 短所 眠気や易怒性の誘発は、少なからずあり。 副作用が問題になる場合には、他剤への変更を検討する。 成人てんかんにおいて、非専門医にとっては第1選択にしてもよい薬剤。
#79.
レベチラセタム ② オールマイティな特性。 レベチラセタムの強み:てんかん発作が焦点性てんかん であっても、全般てんかんであっても有効である。 焦点性てんかんか全般てんかんか、てんかん発作分類について診断に悩む場合にも、選択してよい薬剤。 レベチラセタムはすぐに効果が発揮できる、副作用の少ない薬剤で、使い勝手がよい(点滴投与可な)薬剤である。
#80.
LEVについて語れるようになろう。 最も汎用されるAEDである。その理由を知る。 点滴である、Braod spectrumである、副作用が少ない、薬物相互作用が少ない。 TIPS 13
#81.
ラコサミドについて知る。 LCMとは:成人用AED 近年頻用される薬剤です。 LEV同様、新しいAED(第3世代の位置づけ)です。 LEVと似たようなニュアンスもありながら、異なる特徴もあります。 ラコサミドのニュアンスも押さえておきましょう。
#82.
LCMは、成人てんかん 診療で役に立つ 成人てんかん診療では、焦点性てんかんを主にターゲットにすればいいです。 ということは、Narrow spectrumのAEDでよいわけです。 Broad spectrumのLEVでなくても良い訳です。 LEVは便利ですが、LEV以外の選択肢として、LCMは知っておく必要があります。
#83.
メリット :焦点性てんかんについて、有効性が高い薬剤。 デメリット:高価。心筋伝導障害の可能性もある。 焦点性てんかんでは使いやすく、効果も期待しやすい。 有効性はカルバマゼピンと同等。一方副作用は目立たない。 成人てんかん診療では、基本的に焦点性てんかんが対応できればよい、という考えからは、ラコサミドは成人てんかん診療での今後の第1選択薬になる薬剤と言える。 ラコサミド 焦点性てんかんに有効な新規抗てんかん薬。 副作用もあまり目立たず、非専門医でも使用しやすい薬剤。
#84.
ラコサミド 眠気少なく、効果もよい。 200mg/dayが維持量。 1週間での有効用量までの増量が可能であり、レベチラセタム同様急性期病院で使用しやすい薬剤。 眠気が問題になりにくい薬剤でもあり、第1選択薬で眠気が問題になり、継続できなかった症例で変更薬剤の選択肢になる。 高齢者でも比較的使いやすい薬剤。 副作用の心筋電導障害の報告はある。 あまり弱点がなく、焦点性てんかんでは頼りになる薬剤。
#85.
焦点性てんかんとして評価可能なら、選択しやすい薬剤である。 器質的病変が指摘可能なてんかん、高齢者てんかんで選択する。 例)高齢者、脳卒中後、脳腫瘍、外傷後などの症候性てんかん。 ラコサミドとは① 焦点性てんかん用AEDである。
#86.
忍容性の高さから、高齢者用AEDとして選択しやすい薬剤である。 ラコサミドとは② 高齢者てんかん用AEDである。
#87.
焦点性てんかんとして、理解しやすいのでよき適応である。 脳卒中を発症しうる高齢者である、という背景も考慮。 ラコサミドとは③ 脳卒中後てんかん用AEDである。
#88.
焦点性てんかんとして評価できるなら、発作抑制後の 【静注療法=>入院後の内服療法】への、シームレスな治療移行が 可能である。 ラコサミドとは④ 救急=>急性期用AEDである。
#89.
LCMについて語れるようになろう。 点滴がある、Narrow spectrumである、副作用が少ない、効果が高い。 TIPS 14
#90.
LCM VS LEV LEVとLCMの特徴について説明してきました。 いずれも使いやすい薬剤です。 頻出薬なので、それぞれの比較についてまとめてみます。
#91.
LEVとLCMの違いをまとめる てんかん発作分類についての違い 全般性てんかん+焦点性てんかん 幅広く推奨される LEV 焦点性てんかんのみ 推奨される LCM 併存症がある場合の違い LEV:幅広い併存症において、最も推奨されるAED。 脳腫瘍、全身癌、脂質異常症、急性期脳梗塞、薬剤多剤使用者、 肝疾患、心疾患、HIVなど。 ただし、精神疾患の併存症は除く。(うつ、不安症、精神病) LCM:幅広い併存症での推奨あるAED。 そして、精神疾患の併存でも推奨されている。 Epilepsy Behav. 2021.doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107540.
#92.
LEVとLCMについて AED選択肢は多い方がよいので、頻出薬双方を理解して下さい。
#93.
LCM VS LEV どちらも頻用される薬剤で押さえておいていただきたい。 TIPS 15
#94.
AEDの特徴と捉え方 その他AEDについても言及します。 抗菌薬に例えてイメージを作ってください。
#95.
頻出するAEDのとらえ方
#96.
AEDの総論的なイメージも理解する。 TIPS 16
#97.
