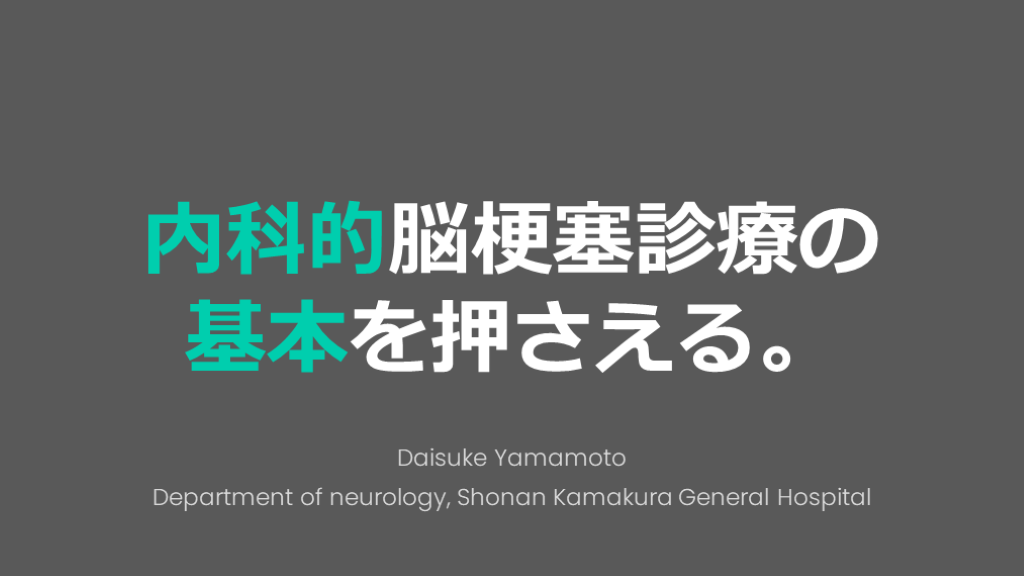














































関連テーマから出会おう。
閲覧履歴からのおすすめ
1/48
関連するスライド
Drゆみの Weekly Journal Scan vol.13
医療法人社団ゆみの
3415
0
頭痛診療レビュー ~救急対応から一次性頭痛の診断・管理まで~
花岡謙
14885
54
内科的脳梗塞診療の基本を押さえる。
山本大介
Award 2024 受賞者
医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院
679,987
1,765
投稿した先生からのメッセージ
脳梗塞の病棟診療が自分で始められます。解説動画あり。
概要
内科医として、病棟医として、脳梗塞診療についての基本的内容を学ぶためのスライドです。
■解説動画あり。ご参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=MiTD--XiB3c&t=156s
■書籍「みんなの脳神経内科」もご参考にして下さい。
本スライドの対象者
医学生/研修医/専攻医
投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!
0 件のコメント
山本大介さんの他の投稿スライド
片頭痛診療、はじめの一歩。
山本大介
274,613
626
ミニマム!運動障害の患者さんに出会ったら
山本大介
151,356
290
Common diseaseである脳卒中後てんかんを学ぶ。
山本大介
123,989
347
このスライドと同じ診療科のスライド
テキスト全文
内科的脳梗塞診療の基本
#1.
Daisuke Yamamoto Department of neurology, Shonan Kamakura General Hospital 内科的脳梗塞診療の 基本を押さえる。
#2.
Introduction 現在脳梗塞診療は、血管内治療が注目され、診療の花形であります。 ただし、血管内治療の適応外となる、内科的脳梗塞も存在し続けるわけです。 内科的脳梗塞を担う治療者へのニーズは、脳梗塞がより増える高齢社会においてはより一層高まるでしょう。 病棟診療を行う医師にとって、脳梗塞は比較的必修科目に近い領域です。 脳梗塞診療ができることを、ある程度要求される立場の医師も多いでしょう。 このスライドでは、実際の脳梗塞診療のエッセンスを、整理して学べます。 ある程度汎用性の高い内容を示していきます。 教科書ではつかみにくい、実際の診療の様子を学んでください。
脳梗塞の臨床病型と治療
#3.
診断:臨床病型 について 臨床病型を決めることからスタートする。
#4.
臨床病型が決まると、入院時の初期治療が決まります。 そして、臨床病型よって、再発予防薬が決まります。 臨床病型の仕方については別スライドを参照下さい。 →「まずはここから!脳梗塞の臨床病型診断入門」 この3つの病型が理解できれば、概ね診療が成立します。この3つで対応しきれない、ピットフォールになるような症例もありますが、それは専門医診療の領域と理解してよいです。 代表的臨床病型とは、 ラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症 の3つの病型です。
入院時の患者説明と治療方針
#5.
入院時患者説明 診療のテーマについて、 医療者・患者/家族双方で確認し、共有しよう。
#6.
1 脳梗塞の進行抑制のための急性期治療(点滴含め) 2 脳梗塞後の全身管理(感染コントロール・栄養管理) 3 脳梗塞の再発予防薬決定のための検査と、予防薬の開始 4 機能障害を回復するためのリハビリテーション 上記4つがテーマとまずは説明しましょう。まずは、悪化がないよう治療、全身管理。その後、脳梗塞再発予防のための予防薬の選定をすること。そして、機能障害の回復のためのリハビリを行う、と説明しましょう。 脳梗塞入院加療の目的について説明しましょう。 入院のテーマは主に4つです。 最初に明示すると、相互理解がいいでしょう。
#7.
まずは、入院後の脳梗塞急性期治療と全身管理。それと並行して、検査を追加して、再発予防薬の選定を行う。障害による機能回復はリハビリテーションによる。直接自宅退院が困難な場合には、リハビリ治療継続のための、リハビリ病院への転院方針となる。ある程度の入院経過でその説明をしていくことになる。 「障害の回復は、リハビリによって得られます。点滴や内服薬で回復するわけではありません。必要に応じて、リハビリ病院への転院加療も検討されることになります。」という中期的ゴールも説明しておいてもいいでしょう。 入院診療経過のイメージ
脳梗塞の初期治療選択と注意点
#8.
以下を注意事項として、患者・家族に事前に説明しておく必要があります。 脳梗塞は、適切な治療介入を行ったとしても、進行・再発がありうることは ご理解しておいてください。 脳梗塞で入院後、色々なTroubleがありうることも知っておいてください。 具体的には、肺炎や尿路感染症などの感染の合併が多いです。 Excuseのように聞こえますが、実際には上記事項の変調がありうるので、入院時にきちんと伝えておくことが肝要です。 「入院時の注意」について、患者説明しよう 保守的だが、これらの起こりうるリスクについて、 最初に共有しておくことが重要です。
#9.
初期治療 入院後、まず行う治療について
#10.
初期治療選択について 治療選択は、臨床病型ごとに行われます。 複数選択肢がありえますが、ここではわかりやすい選択肢を提示します。 1 ラクナ梗塞 A) バイアスピリン200mg 投与(数日間) B) オザグレルNa(点滴) 2 アテローム血栓性脳梗塞 A)バイアスピリン200mg 投与(数日間) B)アルガトロバン(点滴) 3 心原性脳塞栓症 A)DOACを適切タイミングで開始 B)なにもしない 4 臨床病型が評価しがたく困ったとき A)バイアスピリン200mg 投与(数日間) B)なにもしない
ラクナ梗塞とアテロームの治療
#11.
1 ラクナ梗塞 A)バイアスピリン200mg 投与(数日間) B)オザグレルNa(点滴) ラクナ梗塞の初期治療では、アスピリンは、200mg/dayの投与量で選択してください。内服が困難な場合には、入院後も嚥下障害ですぐに経口摂取が再開できない可能性が高いので、胃管チューブを挿入して、初期治療からアスピリンで開始していく方針としてください。 内服がしにくいシチュエーション、胃管チューブを回避したいシチュエーションでは、オザグレルNaという点滴製剤があります。1日2回投与で、これを選択してください。 最もシンプルな選択としては、アスピリン2錠投与で。PPIも併用しましょう。
#12.
2 アテローム血栓性脳梗塞 A)バイアスピリン200mg 投与(数日間) B)アルガトロバン(点滴) アテロームの場合も、ラクナ同様、血栓性機序であり、アスピリン投与でよいです。 アルガトロバンも選択肢です。 アルガトロバンを使い慣れない場合には、アスピリン選択でよいです。 シンプルな選択肢→アスピリン+PPIで。
#13.
アスピリン160-300mg/日の経口投与は、発症早期(48時間以内)の脳梗塞患者の治療法として勧められる。 推奨度 A エビデンスレベル 高 脳卒中ガイドライン2021 急性期のアスピリン 最もシンプルな治療選択肢。 ラクナ梗塞・アテローム血栓性脳梗塞と評価し、 48時間以内の発症であれば、これを選ぶ。
軽症脳梗塞のDAPTと治療法
#14.
抗血小板薬2剤併用(アスピリンとクロピドグレル)投与は、発症早期の軽症非心原性脳梗塞患者の、亜急性期(1カ月以内を目安)までの治療として勧められる 推奨度 A エビデンスレベル 高 脳卒中ガイドライン2021 急性期のDAPT 発症24時間以内の軽症非心原性脳梗塞(NIHSS3点以下)もしくはTIA患者で、 クロピドグレル初回300mg=>以後75mg アスピリン初回75-300mg =>以後75mg で有効かつ安全に治療ができる(CHANCE試験)。 ガイドラインでは、軽症+24時間以内なら、 DAPTもよい、とされている。
#15.
GLでは、「軽症(NIHSS≦3点)」の記載はあるものの・・・・・ ①アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞での24時間以内の急性期治療については、DAPTが選択されることも多い。 ②UPTODATEでは、NIHSS≦5点を軽症として定義していいのでは、と記載あり。ただし、NIHSSスコアが高ければ/梗塞範囲が広ければ、出血リスクも高まるので留意は必要。画像での梗塞範囲とも合わせて考慮。 ③現実的には、出血リスクを勘案してDAPTが検討されている。 実際的なDAPTの考え方
#16.
シンプルにアスピリンでの対応 A:アスピリン(バイアスピリン錠®)(100mg) 1回2錠 1日1回 朝食後 エソメプラゾール(ネキシウムカプセル®)(20mg) 1回1カプセル 1日1回 朝食後 DAPTでの対応 B:アスピリン(バイアスピリン錠®)(100mg) 1回2錠 1日1回 朝食後 クロピドグレル硫酸塩(プラビックス錠®)(75mg) 1回4錠 1日1回 朝食後 2日目以降は1回1錠 1日1回 朝食後 ラクナ・アテロームの 抗血小板療法 処方例
心原性脳塞栓症の治療とガイドライン
#17.
3 心原性脳塞栓症 A)DOACを適切なタイミングで開始 B)なにもしない 心原性脳塞栓症にヘパリン静注を行うかどうか?については行わない、という考え方でよいです。DOACの開始タイミングとしては、1-3-6-12 daysルールを参考に、DOAC開始としてください。 ひとまず、入院時指示としては、B)DOACを開始せずに何もしない、はありです。 発症機序が決められず、どうしても方針に悩む場合には、アスピリン200mg投与でも許容されると思われます。
#18.
脳梗塞急性期に、未分化ヘパリン、低分子ヘパリン(保険適用外)、へパリノイド(保険適用外)を使用することを考慮してもよい。 推奨度 C エビデンスレベル 中 脳卒中ガイドライン2021 急性期のヘパリン 脳梗塞急性期のヘパリン投与問題は、ガイドラインでは 上記記載となっています。結局どう考えればいいのでしょうか? 「心原性脳塞栓症の再発防止」が目的にはなりますが、 静注療法の至適開始時期は不明です。
#19.
海外のガイドラインではヘパリン投与について否定的である。 本邦では、低用量のヘパリン使用で目立った問題なく対応できていることから、ヘパリン使用が継続されてきた。 DOACの選択肢がなかった時代には、ヘパリン静注=>ワルファリン導入の流れの簡便さもあったと思われる。 現状、ワルファリンを使用する機会も減っている。 心原性脳塞栓症発症後に、ヘパリン投与なく、直接DOACを導入する流れも一般的になっている。 ヘパリンの考え方
#20.
DOAC時代においては、海外のガイドライン推奨に準じて、心原性脳塞栓症に対するヘパリン投与は行わない、というスタンスでもよかろう。 心原性脳塞栓症の入院加療(抗凝固療法) =>ヘパリン静注なし =>1-3-6-12 days ルール でDOAC導入 ヘパリンの考え方
入院時指示と安静度制限
#21.
非弁膜症性心房細動を伴う急性期脳梗塞患者に、出血性梗塞のリスクを考慮した適切な時期に、DOACを投与することを考慮しても良い。 推奨度 C エビデンスレベル 低 脳卒中ガイドライン2021 DOAC開始のタイミング 梗塞サイズは、脳出血のリスクと関連している。 梗塞サイズが大きいと脳出血リスクが高い。 NIHSSスコアを脳梗塞サイズの代用として用いることもできる。 よって、NIHSSスコアをもとに、出血リスクを勘案してDOAC開始を検討する方法が紹介されている=>1-3-6-12 day ルール(欧州GL)。
#22.
DOAC開始タイミング(発症から) TIA :1日後 軽症脳梗塞 :3日後以降 軽症とは =>NIHSS <8 中等症 :6日以降 中等症とは =>NIHSS 8-15 重症例 :12日以降 重症とは =>NIHSS ≧16 一方、より早期にDOACを開始してもよいともいわれている。 保守的に対応するなら、このルールでいいのかもしれない。 1-3-6-12 dayルール
#23.
4 臨床病型が評価しがたく困ったとき A)バイアスピリン200mg 投与 B)なにもしない 専門医でないと、なんとも判別しがたい症例がありえます。また、専門医でも決められない症例もあります。 決めかねる場合は、血栓性機序の可能性を重んじてのアスピリン投与は許容されると思います。 わからなくて悩む場合には、また、出血リスクなどで不安要素がある場合には、 抗血栓薬は投与しない、というのも選択肢になりえます。
#24.
入院時指示について シンプルな病棟指示
入院中の検査と治療計画
#25.
安静度制限:入院初日は「ベッド上安静で、飲水時のみベッドアップ可。」としてください。当直医であれば、この指示で対応し、翌日の専門医へ引き継いでください。 入院担当医として管理していく場合には、入院翌日から離床指示を出してください。どのスピードで安静解除を進めていいか?については明確な指針はありません。麻痺の進行がある場合、症状の動揺性を認める場合には、安静度制限をしながら、様子をみて、少しずつ安静度制限の解除を行っていくしかないです。 以下は一般的指示として例を示します。 (一般的指示) 初日:ベッド上 →2日目:車椅子 →3日目:制限なし 安静度制限: 明確な指針がなく、悩ましいところです。
#26.
入院中の検査 について ルーチンで行う、検査オーダーについて
#27.
頸動脈エコー :ルーチンでオーダーして下さい。 経胸壁心エコー :心原性を疑う場合に施行 ホルター心電図 :心原性を疑う場合に施行(Af未指摘の場合) Dダイマー :心原性脳塞栓症を考慮するヒントになります。 BNP :心原性脳塞栓症を考慮するヒントになります。 CRP :感染性心内膜炎を考慮するヒントになります。 動脈硬化のリスク評価:TG・LDL・HbA1C 検査忘れがないよう、一通り採血検査は行うようにしてください。 CRP高値の場合は、感染性心内膜炎の可能性を忘れないよう。ピットフォールです。 検査オーダー 以下検査をオーダーして下さい。 検査は、臨床病型の決定のために行います。
#28.
心房細動が指摘できない場合には、必要に応じてホルター心電図の追加をする。 ホルター心電図 退院のゴール設定について、 本人家族と相談。 自宅退院?リハ病院への転院? 面談 内頚動脈狭窄症チェック 頸動脈エコー 新規開始薬剤の副作用確認をする。感染のチェック。 採血 治療後の出血病変の確認をCTで行う。 頭部CT・採血 最終的な梗塞病変の確認をCTで行う。 頭部CT MRI:入院時の診断目的 採血:コレステロール・HbA1C・CRP MRI・採血 心原性脳塞栓症を考慮するなら、弁膜症の有無や心機能評価でやっておく。 心エコー 04 02 08 06 03 01 07 05 検査スケジュール例
脳梗塞の再発予防薬とその選定
#29.
再発予防薬について 脳梗塞の再発予防薬を導入することが 入院の4つのテーマのうちの一つ。
#30.
ラクナ梗塞 :クロピドグレル・シロスタゾール アテローム血栓性脳梗塞:クロピドグレル 心原性脳塞栓症 :DOACs OR ワルファリン 原因不明の塞栓症 :アスピリン 上記で対応します。 再発予防薬について 脳梗塞の再発予防薬(二次予防薬)は以下のごとくです。
#31.
抗血小板薬:クロピドグレル・シロスタゾール・アスピリン 抗凝固薬 :ワルファリン・DOACs 抗血栓薬 :抗血小板薬+抗凝固薬 この3つのtermの使い分けをしっかりしましょう。重要。 血栓性機序の脳梗塞の予防→抗血小板薬 (※ラクナ+アテローム) 心原性脳塞栓症の予防 →抗凝固薬 この使い分けもおさらいしましょう。重要。 タームの整理をしましょう。 抗血栓薬の使い方の整理をしましょう。 このページが最も理解すべきミニマムの知識です。
#32.
いずれの薬でも、1ジャンル1剤の使い慣れが、まずは重要でしょう。DOACsで1剤覚えるなら、エリキュースがおすすめです。 DOACsはいずれも腎排泄で、腎障害のある患者では使用しにくいです。高齢者を想定した投薬では、腎障害が悪化しても長期間使用可能な薬剤であり、出血合併症の安全性が高いとされる薬剤がよいでしょう。DOACsでは、エリキュースを使い慣れることから始めてみて下さい。 DOACsで1剤使い慣れるなら→エリキュースがおすすめ 理由:腎機能が悪くても、長期間使える 出血リスクが低いので、高齢者向け
原因不明の塞栓症と評価方法
#33.
先述した抗血栓薬の選定を行うことと同時に、動脈硬化のリスクがある場合にはそれに介入することが内科的にできることです。これらのリスクを指摘し、適切なレベルまでコントロールすることが、内科的治療で行うことです。 1.2は医療で介入できることとして説明、残り3は、患者自身ができることとして説明して下さい。 再発予防について、3通りのアプローチを説明しよう。 1:抗血栓薬を導入すること 2:動脈硬化のリスクに介入すること(DM・HT・脂質異常症) 3:患者自身による運動療法・食事療法
#34.
原因不明の塞栓症 について 脳梗塞診療で悩むテーマ
#35.
塞栓性機序の脳梗塞で、塞栓源が不明な場合、ここまで述べた型どおりの診療ができません。施設によっては、十分な塞栓源の評価ができない場合もあるでしょう。 最低限の評価としては、感染性心内膜炎の除外を行ってください。Criticalな感染性心内膜炎は、取りこぼしなく対応したいものです。感染症による脳梗塞、という発想は忘れがちです。塞栓性梗塞であった場合に、入院時、発熱があったり、炎症反応の上昇がある場合には、いつも想起して下さい。CRPはこれを忘れずに想起するために、ルーチンで施行して下さい。 原因不明の塞栓症について 脳梗塞診療で問題になるテーマです。 ミニマムでは、どのような評価をするべきか???
#36.
もう一つの想起すべき疾患は、Trousseau症候群(トルソー症候群)です。 悪性腫瘍に合併する脳梗塞です。 脳梗塞を繰り返し、経過不良の可能性がありうること、 悪性腫瘍の治療という全く違うアプローチになる可能性があることから、 忘れずに想起したい病態の一つです。 炎症反応高値、Dダイマー上昇、再発性脳梗塞 がヒントになります。 原因不明の塞栓症について 脳梗塞診療で問題になるテーマです。 ミニマムでは、どのような評価をするべきか???
ラクナ梗塞の具体例と治療方針
#37.
最後に、具体例で 知識のおさらい ラクナ梗塞のケースで学ぼう。
#38.
75歳男性 右片麻痺と構音障害 来院2日前からの右手の巧緻運動障害あり。来院前日に少し増悪、その後構音障害と右片麻痺の顕在化あり、ERを受診した。
#39.
75歳男性 右片麻痺と構音障害 当直医A 「まずは、CT。特に所見なければMRIを施行しよう。心房細動がないかECGをチェック。脳梗塞かもしれないから採血はそのつもりで一通り。」 採血→ HbA1C、コレステロール、D dimmer、CRP、BNP
#40.
75歳男性 右片麻痺と構音障害 当直医A 「MRIでは、左内包部分の脳梗塞。血栓性機序の脳梗塞で、臨床病型はラクナ梗塞の診断だな。ラクナ梗塞なので、初期治療はアスピリンにしよう。」
患者への説明と退院計画
#41.
75歳男性 右片麻痺と構音障害 オーダー 初期治療:バイアスピリン200mg 投与 絶食・維持輸液管理。 安静度:ベッド上安静、飲水内服時のみベッドアップ可。
#42.
75歳男性 右片麻痺と構音障害 患者説明① 入院治療のテーマについて 当直医A 「脳梗塞の診断で入院です。入院後、脳梗塞の少しでも進行がないように、血液サラサラにする薬を飲んでもらいます。脳梗塞入院では、4つのテーマがあります。一つは脳梗塞の進行抑制、また全身管理をします。もう一つは脳梗塞の再発予防のための投薬調整、4つ目は、機能回復のためのリハビリです。」
#43.
75歳男性 右片麻痺と構音障害 患者説明② 入院時の注意について 当直医A 「脳梗塞で入院する方には、みなさん注意を説明しています。一つは、治療を開始しても脳梗塞自体が進行する可能性がありうることです。もう一つは、入院後に感染症の合併など、脳梗塞以外の問題が起こりうることです。これらのことは、理解しておいてください。」
#44.
心房細動が指摘できない場合には、必要に応じてホルター心電図の追加をする。 ホルター心電図 退院のゴール設定について、 本人家族と相談。 自宅退院?リハ病院への転院? 面談 内頚動脈狭窄症チェック 頸動脈エコー 新規開始薬剤の副作用確認をする。感染のチェック。 採血 治療後の出血病変の確認をCTで行う。 頭部CT・採血 最終的な梗塞病変の確認をCTで行う。 頭部CT MRI:入院時の診断目的 採血:コレステロール・HbA1C・CRP MRI・採血 心原性脳塞栓症を考慮するなら、弁膜症の有無や心機能評価でやっておく。 心エコー 04 02 08 06 03 01 07 05 検査スケジュール例
脳梗塞診療の重要性とまとめ
#45.
75歳男性 右片麻痺と構音障害 再発予防薬の選定 診断 :ラクナ梗塞 抗血栓薬 :クロピドグレル 75mg/day リスク介入:スタチン追加 入院担当医A 「脳梗塞予防のために、抗血小板薬内服と、動脈硬化のリスクへの介入をします。」 「これらの薬剤は、永続的な内服方針となります。今後も高血圧症はじめ、動脈硬化のリスク管理を継続していく必要があります。また、御自分でできる事として、運動・食事療法も頑張って継続して下さい。」
#46.
75歳男性 右片麻痺と構音障害 患者説明② 担当医A 「脳梗塞の残存症状については、投薬での改善が得られる訳ではありません。 リハビリを継続することで改善が得られます。集中的なリハビリ治療を行うため、 その後の生活の再検討を行うため、リハビリテーション病院への転院を 相談しましょう。」 入院後麻痺の進行あり。入院リハを行ったが、自立して自宅退院は困難な状態であった。自宅退院を目標としたリハビリ継続ための、転院加療を検討することとなった。
#47.
