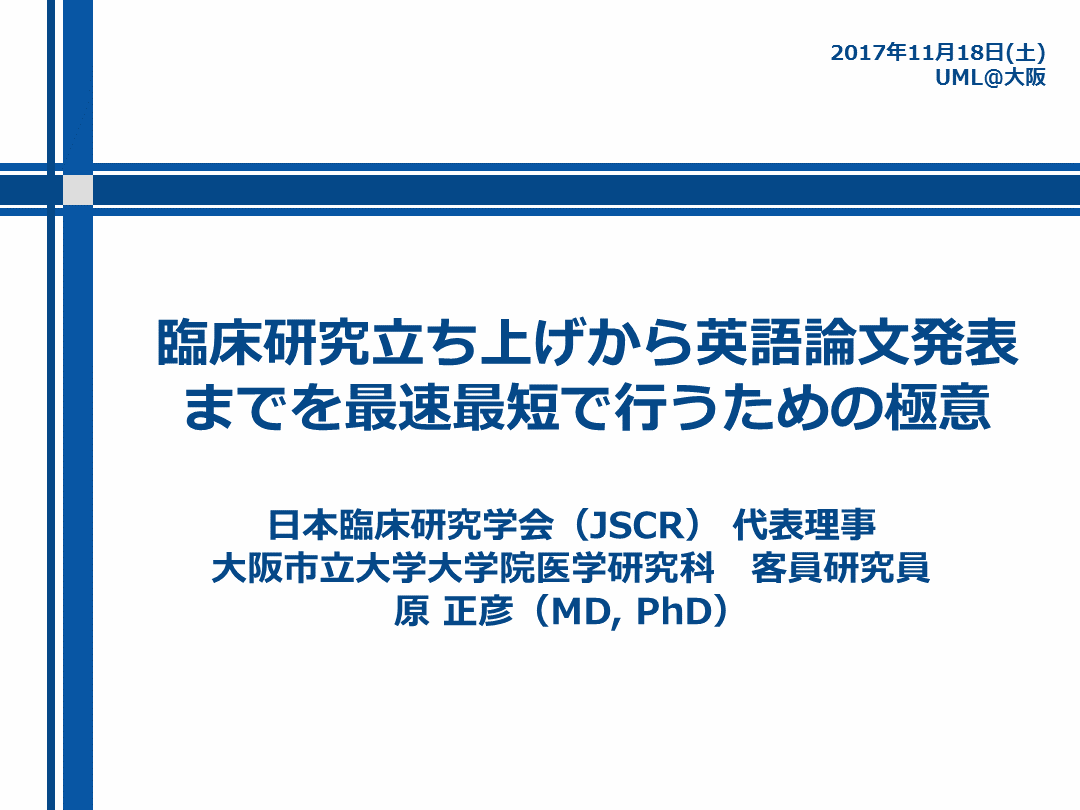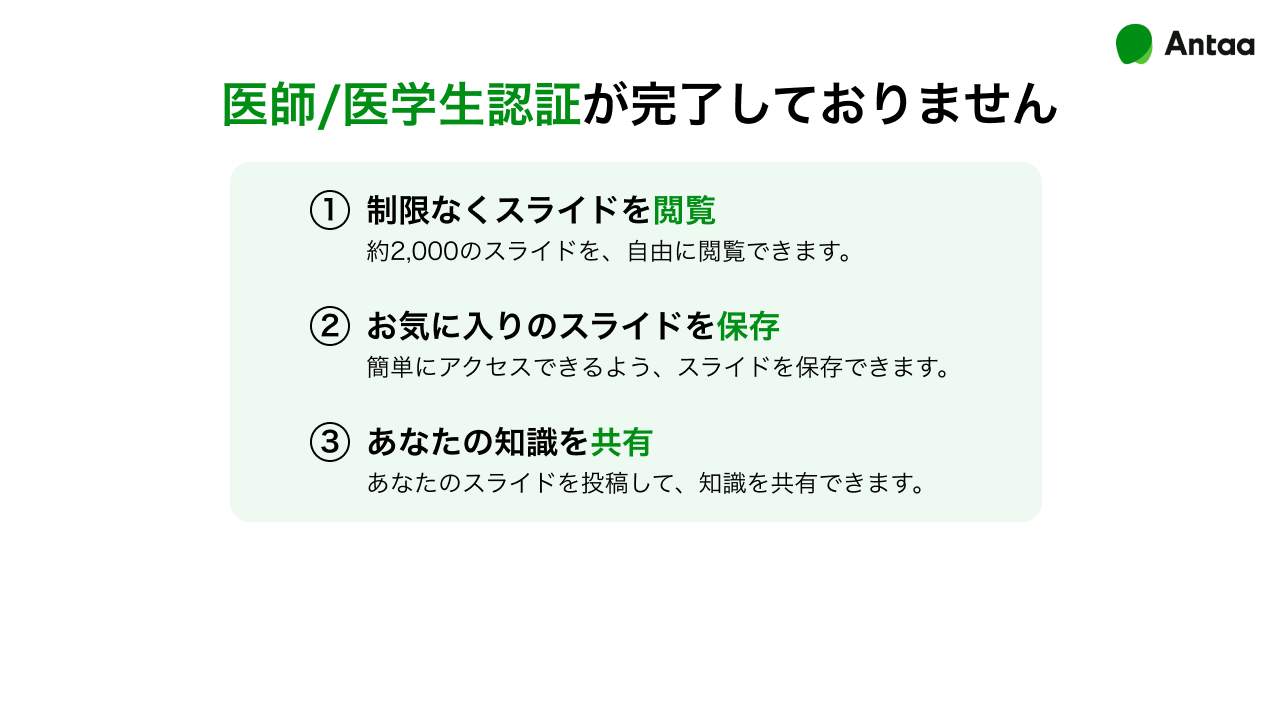このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/29
関連するスライド
30代のキャリアチェンジ 〜スペシャリストかジェネラリストか?〜
大向功祐
41451
61
④診療所経営って、結局なに?
石黒謙一郎
59199
41
臨床研究立上げから英語論文発表までを最短最速で行うための極意
18,697
125
原正彦さんの他の投稿スライド
脳再プログラミング療法で激変する神経内科・脳外科・小児科医の役割
原正彦
5,989
28
Somato-cognitive coordination therapy using VR for advanced severe Parkinson’s disease
原正彦
2,623
10
臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短で行うための極意
原正彦
33,686
172
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。