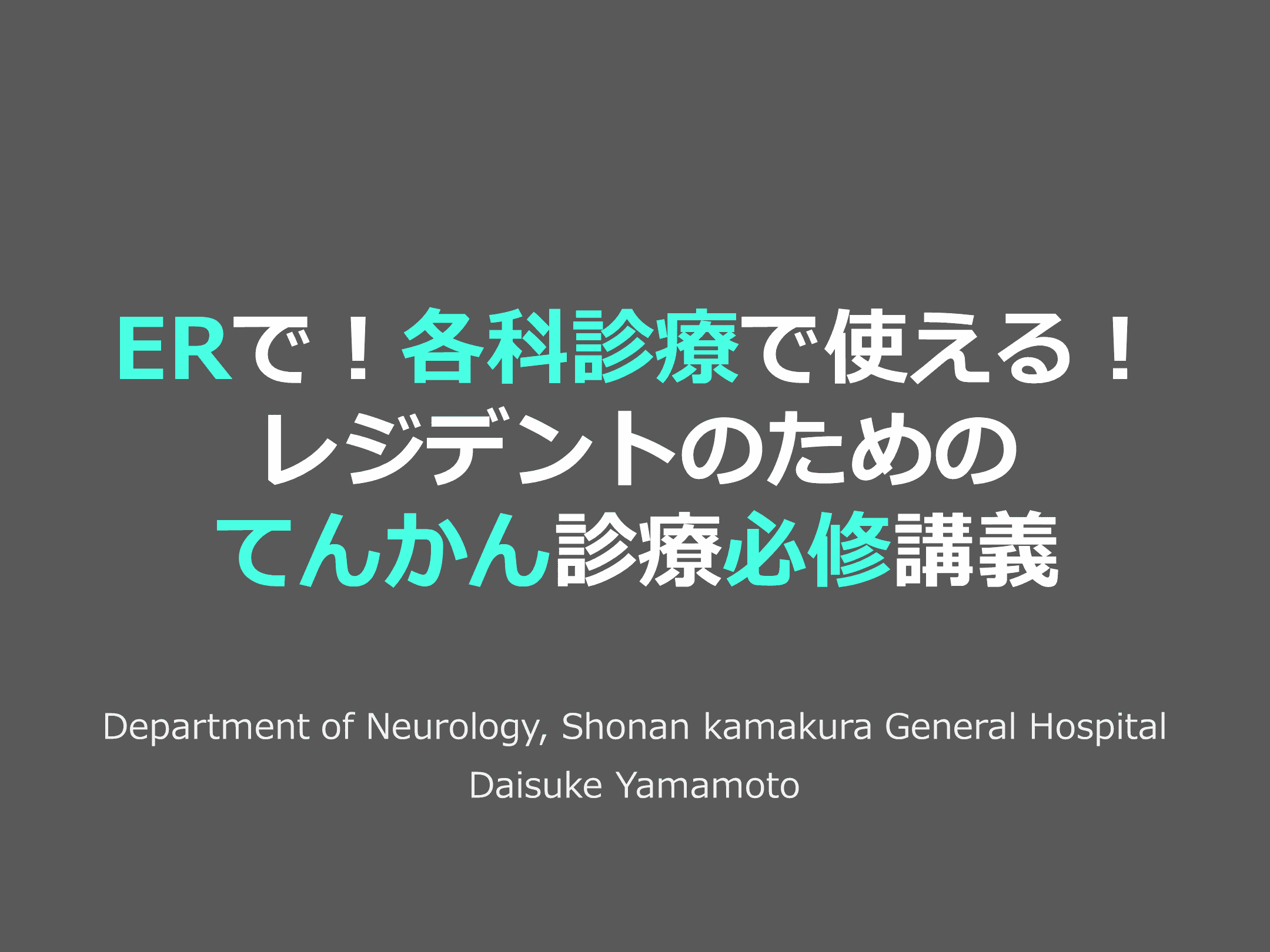1/140
関連するスライド
急性期脳梗塞 初期診療
菊野宗明
372579
898
プラクティカルな脳卒中後てんかん診療 ー患者さんと一緒に治療を選択するー
山本大介
26159
91
コモンとアンコモンをメタ認知して、脳梗塞の誤診を減らす。
山本大介
26052
96
頚動脈狭窄症を見つけたら -診断と治療-
菊野宗明
42001
246
ERで!各科診療で使える!レジデントのためのてんかん診療必修講義
山本大介
Award 2024 受賞者
医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院
280,708
883
概要
ERでのてんかん診療のアウトライン、また抗てんかん薬について総論的に学べるスライドです。
【動画解説】https://www.youtube.com/watch?v=ROzVDkhKjvQ
【書籍:みんなの脳神経内科】https://www.amazon.co.jp/dp/4498328736
本スライドの対象者
研修医/専攻医
投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!
0 件のコメント
山本大介さんの他の投稿スライド
片頭痛診療、はじめの一歩。
山本大介
274,614
626
ミニマム!運動障害の患者さんに出会ったら
山本大介
151,361
290
Common diseaseである脳卒中後てんかんを学ぶ。
山本大介
123,990
347
このスライドと同じ診療科のスライド
テキスト全文
てんかん診療の総論的知識と定義
#1.
Department of Neurology, Shonan kamakura General Hospital Daisuke Yamamoto ERで!各科診療で使える! レジデントのための てんかん診療必修講義
#2.
Introduction てんかん診療の 総論的知識
#3.
まずはてんかんを 自分で説明できる てんかん診療を始めるには、まずは自分の言葉で 「てんかん」を説明できなければいけません。 どのように説明すればいいでしょうか。
てんかんの定義と有病率について
#4.
てんかん とはなにか? まずはてんかんの定義からです。てんかんとは何か、を自分で説明しましょう。ガイドラインでは、このように説明されています。 <てんかんの定義> てんかんとは、てんかん性発作を引き起こす持続性素因を特徴とする脳の障害である。 すなわち、慢性の脳の病気で、大脳の神経細胞が過剰に興奮するための脳の発作性症状が反復性に起こる。 発作は突然起こり、普通とは異なる身体症状や、意識、および感覚の変化などが生じる。明らかなけいれんがあれば、てんかんの可能性は高い。 てんかん診療ガイドライン2018
#5.
自分の 言葉使いで 説明すると わかりやすく嚙み砕いて、このように説明してみます。ご参考にしてください。 けいれん発作のないてんかん発作があることも考慮して、説明に加えています。 <平易なてんかんの説明> てんかんとは、脳の特定の部分から異常な電気活動(ノイズと表現したりもします)が起こり、結果としてその場所の脳の機能がおちてぼーっとしたり、運動神経まで広がればけいれんを起こしたりする病気です。 このような発作を反復しうるので、治療のための薬を飲むか飲まないかの検討を要します。
#6.
てんかんは 稀なものなのか? それほど稀では ないのか? 頻度について言及しましょう。 特に、高齢者てんかんについて説明できる必要があります。 高齢者てんかんの原因としては、加齢に伴い、脳の一部分に傷がついて、その部分にてんかん原性が起こりえます。このロジックについても説明できるようにして下さい。 <有病率についての知識> てんかんの有病率は0.8%である。 てんかんは、小児期に発症するイメージはあるが、高齢者はてんかんを好発する。 65歳以上のてんかん有病率は1%以上(1~2%)と推定される。より高齢になればなるほど、発病率は高くなることが知られている。 Epilepsia 2008;26:19-22
抗てんかん薬導入の基本ルールと介入条件
#7.
介入の基本ルール 2回目の発作から 今一度、抗てんかん薬導入についての「発作2回目ルール」を理解しましょう。 初回発作では治療介入しない、2回目の発作があれば治療介入を検討する、 というものです。 そもそも、てんかんの定義(部分)ですが、 「24時間以上の間隔で、2回以上の非誘発性発作が生じる」とされています。 (非誘発性発作とは明らかな誘因がない慢性疾患としての自発発作を意味します。)
#8.
確率の話 てんかん発作の2回目以降に治療介入を検討するこのルールは、疫学データに支持されています。 非誘発性の孤発発作が出現した後の 再発リスクは 40~52%である 。 非誘発性の無熱性発作が 2 回出現した場合、4 年後までに再発する確率は 73%を超える。 <シンプルに説明するなら> 1度だけけいれん発作があった場合は、2回目が必ずあるとは限らない。半分以上の人は再発がない。 しかしながら、2回以上けいれん発作があった場合には、その後の 発作再発率は非常に高い。 よって、2回目の発作をもって、治療介入が検討されることになる。 Epilepsia 2014;55:475-482
#9.
1回目の発作から 抗てんかん薬を 開始する場合 基本ルールでは、2回以上の発作で介入を検討する、でした。 初回発作でも介入を検討する場合もあります。 特に、ジェネラリストが対応する場合には、 このシチュエーションを押さえておいてください。
#10.
初回から介入する場合① 1つ目は、高齢者てんかん(65歳以上発症) の場合です。この場合は再発率が高いので、治療介入が初回発作から検討されます。この事実を伝えて、初回発作からの介入を相談することになります。 <高齢者てんかんについて> 高齢者てんかんは、一度てんかん発作を生じた場合、若年者よりも 再発リスクが高い。 特に脳梗塞など既往がある場合には 再発リスクが高くなる。 よって、原因となる脳病変(脳卒中・アルツハイマー病など)が指摘できる場合には、初回発作から治療を始めることも多い。 標準的神経治療:高齢発症てんかん 日本神経治療学会
#11.
初回から介入する場合② 2つ目は、脳卒中慢性期のてんかん発作の場合です。やはり、初回発作後の再発率の高さによります。再発率の高さが知られているため、患者さんと相談し初回からの抗てんかん薬の導入は検討されます。脳卒中の合併も多い、高齢発症てんかんと合わせて理解しておきます。 <脳卒中後のてんかん> 高齢発症てんかんの原因で最も多いのは脳卒中で、原因の30-40%を占める。 そもそも、脳卒中後に症候性てんかんを生じる頻度は2-4%である。 脳卒中慢性期のてんかん発作再発率は、10年以内で60%以上である。 脳卒中後てんかん発作では、初回発作から抗てんかん薬の導入が検討されることが多い。 標準的神経治療:高齢発症てんかん 日本神経治療学会
#12.
てんかんとは何かを自分で伝えることができる 高齢者てんかんの理屈を説明できる 二回目発作からの介入ルールについて説明できる 初回発作からの介入条件について説明できる つまり、脳卒中後てんかん、高齢者てんかんは シンプルな介入の対象者であると知る。 SUMMARY
ERでのてんかん発作評価と病歴聴取
#13.
#1 ERの、 そのてんかん発作を 評価する。
#14.
#1 てんかん発作は発作抑制の対応のみならず、その原因についても検討する必要があります。 発作の原因評価と発作抑制の治療を並行して進められる 思考が必要です。 評価の主題:その発作が「てんかん」による発作なのか? 誘発性発作/急性症候性発作なのか?を常に考えましょう。
#15.
前提として2つの用語を理解する。 誘発性発作(provoked seizure):中毒や薬剤、アルコール (多量摂取/離脱いずれも)電解質異常、代謝性要因など誘因が特定可能なてんかん発作。 急性症候性発作(acute symptomatic seizure):頭部外傷や脳卒中、硬膜下血腫、脳外科手術、中枢神経感染症、脳炎などが原因の急性脳機能障害によって誘発されたてんかん発作。 ER診療においては、その発作がてんかん(epilepsy)による発作なのか、誘発性発作/急性症候性発作なのかを判別しようとする思考が重要。
#16.
症状についての 病歴聴取 病歴聴取のポイントを示します。 また、てんかん発作らしさのポイントも確認しましょう。
#17.
発作イベントの健忘があるか? 発作後の混乱や見当識障害があったか? 発作前に前兆があったか? 全身性のけいれん発作の様子は? 身体一部のけいれん発作の様子は? 眼位(上転、共同偏視)はどうたったか? 発作後の限局性の麻痺(Toddの麻痺)は認められたか? 自動症(口をくちゃくちゃする、非合目的運動)は認められたか? 咬舌・失禁の有無は? 発作の様子の記載 患者本人と発作目撃者から以下の様子を聴取してください。
#18.
けいれん(convulsion)は脳由来のみが原因ではなく、 失神(一過性の循環不全)でも認められることがある。 発作が脳由来であった場合、 発作後に遷延する意識障害の存在 や、 発作に関する健忘 を認める。 これらを確認できると、その「けいれん」が、 脳由来の「てんかん発作」であった可能性が高いと判断できる。 その「けいれん」が脳由来の てんかん発作だったかどうか?
#19.
検査 採血で何を確認するか? 髄液検査はやったほうがいい? MRI検査のポリシーは?
急性症候性発作の評価と検査方法
#20.
採血検査 急性症候性発作の原因評価を含めた以下採血オーダー。 電解質(とくにNa)、グルコース、CPK、腎機能、肝機能、NH3、血算、ラクテート(上昇でてんかん発作を肯定)
#21.
中枢神経感染症(細菌性髄膜炎、ヘルペス脳炎など) 自己免疫性脳炎 が鑑別になる場合には髄液検査を行う。 免疫不全状態の患者では積極的に検査する。 髄液検査の検討
#22.
初発けいれん発作であれば、いずれかのタイミングでMRI評価は行われる必要がある。 比較的高齢者であれば、脳卒中による急性症候性発作の 鑑別目的で、ERでの頭部MRI施行は検討される。 発作後神経症状の残存があるならMRIは施行する。 神経症状に異常があればMRI
#23.
てんかんによる発作? そうでない発作? 反復する問いですが、重要です。
#24.
てんかんによる発作であれば、発作抑制が診療の主題となる。 一方、特定の原因によって誘発された発作(誘発性発作/急性症候性発作)の場合は、その原因に対するアプローチを要する。 たとえば、低Na血症、低血糖、脳卒中、脳炎など。よって、背景に 隠れている、治療介入必要な疾患の存在を追求する姿勢が重要。 とくに初回けいれん発作の場合には、慎重な原因評価が求められる。 「てんかん」による発作なのか? 誘発性発作/急性症候性発作なのか?が問題
てんかん発作のマネジメントと治療介入
#25.
共同偏視+けいれん発作 の組み合わせ 共同偏視の向きと、 けいれん発作の組み合わせから、 病態推測可能な、有用なルールがある。
#26.
たとえば、左大脳半球の 脳梗塞による急性症候性発作 の場合には、 左共同偏視+右半身のけいれん発作 となる。 たとえば、左大脳半球が焦点の てんかん発作の場合には、 右共同偏視+右半身のけいれん発作 となる。 このルールは 破壊性障害と刺激性障害 (急性症候性発作と純粋なてんかん発作)を区別するうえで有用。
#27.
ERでのマネジメント てんかん発作での薬剤投与について 発作抑制が困難なら第1段階から第3段階まで治療を ステップアップしていきます
#28.
第1段階 まず発作を止める薬剤 ジアゼパム 5~10mg 静注 第2段階 次の発作抑制に使用する薬剤 ①ホスフェニトイン 22.5mg/kg+生食100ml 15分で点滴静注 ②レベチラセタム 1,000~3,000mg+生食100ml 15分で点滴静注 第3段階 第2段階までの治療で発作抑制困難なら、 ミダゾラム持続静注、またはプロポフォール持続静注を検討。 発作抑制が困難なら 第1段階から第3段階まで 治療をステップアップする。
#29.
低血糖性けいれん、低Na血症など電解質異常、脳卒中、脳炎などによる急性症候性発作の場合には、これらの治療介入を必要とする。 とくに脳梗塞の場合には、tPA療法や血管内治療のtherapeutic time windowを逃さないことが重要。 急性症候性発作に対する 治療介入
#30.
Disposition 初発けいれん発作を帰宅対応とする場合は、 必ず専門外来へ引き継ぐこと。 てんかん発作再燃なく、誘因に対して介入されており、 神経症状の残存がないなら帰宅も検討。 神経症状の残存があるなら、必ず入院対応とする。 神経症状の残存があるなら、MRIや髄液検査施行などの 追加検査を行う。
けいれん発作とてんかんの基礎知識
#31.
その発作がてんかんによる発作なのか、 誘発性発作/急性症候性発作なのか。 この問いがER診療の入り口で常に検討される主題。 けいれん発作抑制を行いながら、 その原因についての評価を行うことを忘れずに。 #1 SUMMARY
#32.
#2 実際の行動編①
#33.
#2 けいれん発作、てんかん診療は難しいです。 また、診断においては慎重さを求められることも 難しさの一要因です。 また、診断ピットフォールも多く、 シンプルには処理できないこともままあります。 ここでは、ERでの初期対応について 可能な限り実用性のある内容を プレゼンテーションのテーマにしています。
#34.
けいれん発作・てんかんの 基礎知識
#35.
けいれん発作、てんかんなどの言葉使いを整理! 1 けいれん(convulsion)は、脳由来ではない可能性も含んだ曖昧な表現であり、使用は 非推奨。 脳由来の異常電気放電による発作に対応する言葉は発作(seizure)。 これだとわかりにくい、と考えるなら、 けいれん発作(convulsive seizure) という表現を。 けいれん、けいれん発作は症候を指した言葉。 一方、てんかん(epilepsy)は、反復性のけいれん発作を起こしうる状態の、診断名。
#36.
けいれん発作、てんかんなどの言葉使いを整理! 1 けいれん → convulsion 曖昧表現である。 けいれん発作 → convulsive seizure 脳由来の「けいれん」 非けいれん性発作 → non-convulsive seizure NCSEのNC。「けいれん」のない発作もある。 発作 → seizure つまり、convulsive+non-convulsive seizure。 てんかん → epilepsy seizureを反復しうる疾患のこと。 会話において誤解が起こりにくいよう、「けいれん」はなるべく使用しないのが望ましいです。ここではけいれん発作で説明していきます。
急性症候性発作の原因と鑑別
#37.
けいれん発作とてんかん けいれん発作 は、「てんかん」ではないので一時的には抗てんかん薬治療が必要かもしれないが、永続的には必要ない。 てんかん (epilepsy)は、長期間の抗てんかん薬治療が 必要である。 初発のけいれん発作を見たときには、それがてんかんによる発作かどうか?その他の原因で起こった発作なのか?は、 区別ができない。ただし、双方は治療方針・検査方針が異なるので、混同してはいけない。
#38.
けいれん発作は、結果である。 けいれん発作の原因について、調べる必要がある。 2 けいれん発作自体も問題だが、 けいれん発作に至った原因を評価しなければならない。その原因を治療しなければならない可能性がある。 初発のけいれん発作を見たら、 けいれん発作に至る原因は?と考えること。
#39.
けいれん発作の原因は 大脳皮質にある。 大脳皮質の細胞障害や機能異常が、けいれん発作の誘因になりうる。 脳梗塞・ヘルペス脳炎による大脳皮質の破壊性刺激は、けいれん 発作を引き起こす。 アルツハイマー病による、大脳皮質細胞変性も原因になる。 自己免疫性脳炎や、代謝性脳症による大脳皮質機能障害も原因に なりうる。 何らかの原因での大脳皮質の破壊、機能障害が、けいれん発作の 誘因になる。
#40.
急性症候性発作、というタームを理解しよう。 3 急性症候性発作とは、ある誘因によって起こされたseizureを指す。 ER診療では、急性症候性発作かどうか?を評価するのがまずは最初のアプローチ。 もしかしたら、「てんかん」によるけいれん発作かもしれないが、そうでない可能性(急性症候性発作)について、まずは検討すべき。
#41.
急性症候性発作 の原因:以下を想起する。 頻度の高いもの: 脳卒中、低血糖、低Na血症、尿毒症、アルコール離脱 薬剤性: NSAIDs+LVFX、テオフィリン、ベンゾジアゼピン離脱 頻度は高くないが鑑別すべき重要なもの: 脳炎(感染性・自己免疫性)
#42.
急性症候性発作の 可能性を十分考慮する。 けいれん発作をみたら、急性症候性発作をまずは想起しよう。原因のあるけいれん発作であれば、原因についての対応が もちろん必要である。 けいれん発作のみへの対応では足りない。 それがCriticalな病態の可能性がある。ヘルペス脳炎や自己免疫性脳炎など、クリティカルな疾患も混ざっている可能性がある。
未診断患者のけいれん発作評価と検査
#43.
急性症候性発作のうち、 まずは コモンな脳卒中を想起する。 脳卒中発症とともにけいれんを発症することがある。 新規発症のけいれん発作では、脳卒中をまずは検討すべき。 けいれん対応のみならず、その原因が脳卒中であった場合には、脳卒中の治療を行わなければならない。まず、脳卒中の可能性について検討すべく、MRI評価をする必要がある。 MRI施行のポリシー:神経脱落症状あり、または、高齢者の場合。
#44.
けいれん対応 既に診断されている患者編
#45.
てんかんの診断が既に ついている患者さんが けいれんしたとき けいれんのきっかけが何だったかを確認する。これら誘因を確認し、発作のきっかけを明らかにする。 きっかけが明らかでないなら、採血やMRI検査を施行することも検討。 きちんと内服していたか? (コンプライアンスの確認) 睡眠不足・疲労はなかったか? (身体的/精神的ストレス?) 感染症などの別の病態は? →採血評価も検討 Triggerとなる薬剤の内服は? →向精神病薬など
#46.
けいれん発作後には意識もうろう状態を来す。 発作後の精神症状を認める場合もある。 発作後の運動障害(トッドの麻痺という)を来すこともある。 発作後の意識障害、精神症状、運動症状など認めない場合には 帰宅可。 症状残存ある場合には、念のためMRI評価も検討される。 発作後、帰宅可能な要件 :発作再発なく、何も症状がない、なら帰宅可。 意識障害や、いずれかの症状残存あるなら入院。
#47.
けいれん対応 未診断患者編 (New onset seizure)
#48.
この場合には、十分な評価が必要。 頭部MRI、採血検査、場合によっては髄液検査を要する。 慎重な対応が必要。 初発のけいれん発作(New onset seizure)なら、 ここまでの説明通り、急性症候性発作の可能性を 追求すること!
抗てんかん薬の使用と治療行動
#49.
検査: 頭部MRI 初発けいれん発作では、少なくとも、最もコモンで確率の高そうな、新規発症の脳卒中を評価しよう、というスタンスでMRIは 施行を検討。 鑑別は多様。 新規脳卒中によるけいれん 陳旧性脳卒中病変による症候性てんかん 認知症に合併する症候性てんかん 脳腫瘍など器質的病変による症候性てんかん 感染性脳炎(特にヘルペス脳炎) 自己免疫性脳炎 など。画像評価は必要。
#50.
検査: 採血検査 以下項目を含んだ一般採血検査をしましょう。 Na, Ca, Mg, Glucose, NH3, CPK, CRP, Vit.B1, 血算, ラクテート +肝機能・腎機能 主には以下を評価する。 電解質異常(低Na血症)のけいれん 低血糖によるけいれん
#51.
検査: 髄液検査 感染性髄膜炎・脳炎評価の鑑別のために行う。 髄液細胞数増多があれば、感染性髄膜炎・脳炎が鑑別になる。 感染性髄膜炎では→細菌性髄膜炎をまずは検討。 脳炎では→単純ヘルペス脳炎を検討。髄液HSV-DNA PCRも。 髄液検査は、MRIなど施行しても原因がはっきりしない場合に最後に検討することになる。とくに免疫抑制状態の患者では積極的に検討。
#52.
けいれん発作をみたら、まずは急性症候性発作の可能性から検討する。 けいれん発作は結果であり、原因を考慮する。 既に診断がついているてんかん患者の発作について。 初回発作の場合には、とにかく急性症候性発作の可能性を考慮。 高齢者では、脳梗塞による急性症候性発作の鑑別を意図して、MRIを検討。 #2 SUMMARY
#53.
#3 実際の行動編②
#54.
#3 今回は具体的な検査行動、治療行動について 解説していきます。 現場でどのような判断をしなければならないのか、 については 事前に知識として 頭に入れておかなければならないものがあります。
ERで使用するけいれん治療薬の選定
#55.
ERでつかう けいれん治療薬
#56.
まずは、すぐに準備する薬。注意点は以下2点。 呼吸抑制を来しやすい。呼吸が停止する可能性がある。 投与量・間隔には十分注意!!! 半減期が短い。次の発作抑制には不十分!!!すぐに効果切れて、次の発作が起こりうる。発作を繰り返す場合には、次の発作抑制のためにレベチラセタム・ホスフェニトインと併せて使用するのがよい。 ジアゼパム 商品名:セルシン・ホリゾン (1A:10mg) まず使う薬!急いで準備してもらう。
#57.
ジアゼパム投与方法 1A = 10mg ※原液のままIV なんとか呼吸停止は避けたい。 使用感覚は使いながら慣れるしかない。 1つの目安は、 体格の小さい人 →0.5A IV 体格の大きい人 →1.0A IV 体格によって使い分ける。 慣れるまでは、0.5Aで使用してもよい。
#58.
ホスフェニトイン 商品名:ホストイン 次の発作を止めるための薬。 ジアゼパム投与後、発作を繰り返すのが心配なら ホスフェニトインまで投与。 投与方法は、初回投与はローディングドーズ、 次の日からは維持量のドーズとなっている。 体重ごとのローディングドーズは、すぐに参照できるようにERに控えておく。
#59.
ホスフェニトイン 体重換算表 すべて、左記バイアル量を 生食100mLで溶いて、 15分で投与! 例:体重60kg患者の場合 ホストフェニイン1.8V + 生食100mL 15分で投与
#60.
ジアゼパム投与後に、レベチラセタム静注のオプションがある。 他剤と比べ、呼吸抑制がなく、速効性もあり、使用しやすい。 ホスフェニトインと同列(2nd line)で検討される。 投与量は、1,000~3,000mg単回投与がガイドラインでも示されている。現状では保険適用外使用ではある。 投与例:LEV 1,000mg + 生食100mL 15分 で点滴静注 もうひとつ、2nd lineの治療 レベチラセタム静注も選択肢。
けいれん治療の流れと実際の行動
#61.
ジアゼパム→ホスフェニトイン投与して、それでも発作を繰り返す場合に是非検討したい方法。非専門医でも使用経験があり、使いやすい薬剤でもあるので、試してみてほしい。 ミダゾラム持続投与まですれば、かなりの症例は発作コントロール可能だと思われる。 ミダゾラム 商品名:ドルミカム 挿管する前に是非試したい治療薬。
#62.
ミダゾラム少量持続投与 MDZ(1A, 10mg, 2mL) MDZ 5A+ 生食40mLで 50mg:50mLの組成で使用。 (※1mL/hr で1mg/hr) 呼吸状態を慎重にモニタリングして行うこと! てんかん診療ガイドラインでは、 0.05~0.4 mg/kg/hr で持続投与と記載されている。 経験的には、ガイドラインの最小用量相当の、2mg/hrで開始。若年者なら、5mg/hrくらいまで試す。高齢者なら慎重に増減を検討する。 ただし、だめなら、次のステップに移行することを躊躇しないこと。
#63.
ジアゼパム →ホスフェニトイン/レベチラセタム →ミダゾラム・プロポフォール まで投与して発作が止まらなかった場合は、挿管・人工呼吸器管理・静脈麻酔薬投与を検討。 ここに至る前には、家族への病状説明とともに、複数医師での方針確認を要する。また専門家の協力も必要。 静脈麻酔薬 プロポフォール、チオペンタール、チアミラール ここからは 救急医、集中治療医、専門医の協力を仰いで。
#64.
難治性てんかん重積 状態での、最終治療への 移行のタイミングについて 発症から、30-60分程度で、最終段階治療への移行を検討。60分程度で、方針決定をするつもりで、ここまでに検査と治療を並行して進める。 てんかん診療ガイドラインでは、「30分以上てんかん重積状態が持続すると後遺障害の危険性がある」とされており、治療開始から60分程度で、静脈麻酔での最終治療に移行することを検討するよう、記載されている。 けいれん抑制ができない場合には、最終段階へ移行することは躊躇せずに判断されるべきである。
#65.
末梢ルート確保困難な場合もある。まずは、ミダゾラム筋注を検討しよう。ジアゼパム筋注は効果不十分であると言われている。 ジアゼパム注腸も選択肢だが、それよりは現実的な投与方法だろう。 ルートが取れないとき ミダゾラム筋注で対応! 10mg 単回投与
#66.
次のスライドからは、 実際の行動を整理しながら、 知識の確認もしよう。
けいれん診断の流れと検査行動
#67.
実際の行動 けいれん抑制編
#68.
酸素投与 MASK 5L! けいれん治療の流れ① 人・物を集める! モニター装着! けいれん発症!
#69.
末梢ルート確保! けいれん治療の流れ② ジアゼパムIV ①回目 0.5~1.0A 呼吸抑制に注意!!! しばらく見極める。
#70.
呼吸抑制観察 けいれん治療の流れ③ 止まらなければ、 発作繰り返せば、 ジアゼパムIV ②回目 0.5~1.0A しばらく見極める。
#71.
止まらなければ、 発作繰り返すなら、 ホスフェニトイン投与 (必要V)+NS 100mL 15分で投与! けいれん治療の流れ④ しばらく見極める。 ミダゾラム少量持続投与検討。 MDZ 5A + NS 40mL作る。 ※オプション:レベチラセタム投与の検討
#72.
止まらなければ、 MDZ 2mL/hrで 開始! けいれん治療の流れ⑤ 呼吸抑制に注意しつつ、 発作抑制ないなら MDZ投与量を増量。 挿管・静脈麻酔の可能性に ついて検討する。 家族にも状況説明加える。 ここまでで30分→→→→→60分
脳炎の評価と対応について
#73.
挿管・静脈麻酔施行の検討。 救急医や集中治療医への応援要請。 けいれん治療の流れ⑥ 挿管。人工呼吸器管理。 静脈麻酔薬の開始。 専門医の召喚。もしくは転院搬送。 ここまでで60分→→→最終判断を。
#74.
実際の行動 診断的行動編
#75.
簡易血糖測定! 低血糖の除外。 けいれん診断の流れ① けいれん治療の開始! けいれん発症! 低血糖なら、Vit.B1 100mg IVしてから、ブドウ糖IV。
#76.
薬剤性の検討 LVFX? テオフィリン? けいれん診断の流れ② アルコール離脱? Bz離脱? 採血一式。 電解質異常? 低Na血症? 低Na血症なら、Na補正とともに、全身管理。
#77.
頭部CT施行 脳出血? けいれん診断の流れ③ 頭部MRI施行 脳梗塞?脳炎? ※痙攣つづくなら、 挿管してからの検査検討。 髄液検査 髄膜炎・脳炎 評価目的。 脳出血の 治療へ。 脳梗塞の 治療へ。 発作止まらず、もしくは診断つかないならここまでで専門医へ。 萎縮やMassなど 構造異常あれば 症候性てんかん の評価。
#78.
てんかん重積状態で、最後までいく場合は多くはない。ただし、その先を想像しながら治療を進めていく必要がある。ある程度はけいれん対応はできることは必須だが、もちろん全部自分でできなくてよい。導入部分の対応がマスターできれば、ほとんど対応可能である。
ヘルペス脳炎の診断と治療
#79.
けいれんの原因評価は、このスライドで提示されたものが想起できており、検査が施行できれば 及第点である。診断的ピットフォールである脳炎があることを知ったうえで、けいれん発作の治療と けいれん評価の検査ができればよい。
#80.
脳炎について どのように考えて どう対応すべきか
#81.
ヘルペス脳炎のみ、最低限カバーできれば及第点としてよい。 ヘルペス脳炎は早期治療介入が必要である。 ヘルペス脳炎は、MRIで画像異常が得られる可能性が高い。 髄液異常も指摘できる可能性が高い。 ただし、所見に乏しいこともある。 脳炎→最低限はヘルペス脳炎のカバー 自己免疫性脳炎の評価については、 専門家に委ねる姿勢で。
#82.
ヘルペス脳炎を 疑うポイント 易感染性背景の場合。 基礎疾患あり。また、 アルコール多飲、高齢者など 特徴的なMRI所見、髄液異常 新規発症の 比較的難治性けいれんのとき 発熱、意識障害、 高次脳機能障害の合併
#83.
ヘルペス脳炎の対応 →ガイドラインも参照。 疑った場合は、 髄液検査を施行する。 髄液一般 髄液HSV-DNA PCR 提出する。 保存検体も提出すると、 GOOD。 アシクロビル 10mg/kg*3回/dayを投与できると最高。 ヘルペス脳炎でなくても、 投与することに問題はない。 迷った場合、疑う場合は迷わず投与、というポリシーになっている。
#84.
最後に キーワード診断
抗てんかん薬の基礎知識と使い方
#85.
-
#86.
-
#87.
てんかん発作を抑制するときの薬剤は、すぐに使えるように押さえておく。 フローについても、押さえる。 脳炎については、単純ヘルペス脳炎をについて理解する。 #3 SUMMARY
#88.
#4 抗てんかん薬できった てんかん診療入門①
#89.
#4 今回は、薬剤を切り口に、てんかん診療を理解します。 ERで出会った患者さんの抗てんかん薬の内容をみて、「こういうニュアンスで、この処方になっているのかな?」と解釈できたりするくらいのレベルが、このレクチャーのゴールです。
#90.
古典的抗てんかん薬 から理解する 薬の基礎知識
古典的抗てんかん薬の理解
#91.
「抗菌薬」に例えて説明。 Narrowか?Broadか? 抗菌薬に例える手法は非専門医の先生方に伝わりやすいので、好んでいます。 「CBZ(カルバマゼピン)はCEZ(セファゾリン)です」。 「LEV(レベチラセタム)はMEPM(メロペネム)です」。 など、抗菌薬に例えるとイメージがわきやすいです。また、抗てんかん薬と抗菌薬の特徴において、ニュアンスが類似しているところもあります。抗てんかん薬には、 守備範囲があり、抗菌薬同様spectrum (Narrowか? Broadか?)で語られます。
#92.
Narrowとは? =焦点性てんかんに有効である、 ことを意味します。 <narrow spectrumのAED> 焦点性てんかんとは、脳の特定部位から異常放電を来たし、てんかん発作に至る、てんかん分類。 焦点性てんかんを考慮する場合には、narrow spectrumの抗てんかん薬が治療薬で選ばれます。 代表的な抗てんかん薬はCBZです。 抗菌薬に例えて、CEZと説明します。
#93.
Broadとは? =焦点性てんかん・全般性てんかん 双方に有効である、こと意味します。 <broad spectrumのAED> 全般性てんかんとは、脳全体に異常放電の発火を来し、てんかん発作に至る てんかん分類です。 発作分類が、焦点性か、全般性てんかんか区別しにくい場合もあります。 この場合は、双方に有効なbroad spectrumの抗てんかん薬を選びます。 代表薬剤はLEVです。 抗菌薬に例えてMEPMと説明します。
#94.
焦点性てんかんとは、脳の特定部位から異常放電を来たし、てんかん発作に至る、てんかん分類。 全般てんかんとは、脳全体に異常放電の発火を来し、てんかん発作に至る てんかん分類。 それぞれの発作抑制に、以下の(古典的)抗てんかん薬が使用される。 焦点性てんかん カルバマゼピン 全般てんかん バルプロ酸 焦点性てんかん、 全般てんかん 2つの分類
#95.
古典的抗てんかん薬について 従来薬=>CBZとVPAが代表薬 従来薬の代表薬は、カルバマゼピンとバルプロ酸です。 カルバマゼピンは=>昔からの、焦点性てんかんの第一選択薬 です。 バルプロ酸は =>昔からの、全般性てんかんの第一選択薬 です。 これら2剤は昔から現在までも、第1選択薬の位置づけです。新規AEDの出現で、使用頻度は減っています。その理由は、薬剤相互作用(併用薬の効果を変えてしまう)や薬剤の副作用によります。よって、従来薬の処方機会は減り、新規抗てんかん薬が選択されることが多くなっています。 (第1世代)
#96.
抗菌薬で例えてみると① カルバマゼピン 焦点性てんかんに有効 イメージはナロースペクトラムの抗菌薬 セファゾリンのイメージ バルプロ酸 全般てんかんに有効 イメージはブロードスペクトラムの抗菌薬 パワフルさには欠ける 第3世代経口セフェムのイメージ
新規抗てんかん薬の特徴と使用法
#97.
抗菌薬で例えてみると② 抗てんかん薬にも、抗菌薬と同様に スペクトラムがある。 理屈的には、抗てんかん薬ごとに作用ポイントが異なり、作用ポイントが違う薬剤を使い分ける。 抗菌薬同様、薬剤の特徴として、スペクトラムが狭い/広い、また、作用機序の異同を考慮して処方している。
#98.
カルバマゼピン、バルプロ酸は、プロ(専門医)処方。 理由は、薬剤相互作用や薬剤の副作用による。 一方、新規抗てんかん薬は、副作用が少なく、使用しやすい薬剤。 プロでなければ、新規抗てんかん薬に馴染んでいくことを、まずは目標に。 古典的抗てんかん薬(従来薬)の 新規投与について
#99.
新規抗てんかん薬 について
#100.
新規抗てんかん薬は、 使用しやすい薬剤である。 近年登場した抗てんかん薬は、新規抗てんかん薬として位置付けられる 新規抗てんかん薬のイメージは、ブロードスペクトラムの抗てんかん薬と理解してよい。 代表薬は、レベチラセタム。抗菌薬に例えるなら、カルバペネムをイメージする。 新規抗てんかん薬の特徴:「副作用の少なさ」。 ブロードスペクトラムで、副作用が少ない、となると、非専門医にとっては使用しやすい抗てんかん薬である。
#101.
非専門医で習熟するとしたら、 新規抗てんかん薬を学ぼう。 新規抗てんかん薬が使用できるようになってからは、古典的抗てんかん薬との使い分けができるようになりそれぞれのメリット・デメリットを勘案して処方するようになっている。 非専門医にとっては、新規抗てんかん薬を使用できるようになる、というのが1つの目標である。 副作用が少なく治療的効果が期待しやすい、というのが、非専門医にとっては重視されるポイントである。
#102.
新規と従来薬のそれぞれの特徴 副作用 薬物相互作用 薬価 新規抗てんかん薬 少ない 気にしない 高い 従来薬 多い 気にする 安い 新規抗てんかん薬の唯一の弱点は、薬価といえる。
成人てんかん診療のポイント
#103.
成人てんかん診療 について
#104.
成人てんかん診療では、基本的には 焦点性(部分)てんかんを考える。 成人てんかんでは、基本的には焦点性てんかんを考慮。 高齢発症なら尚更、焦点性てんかんを考慮して診療を行っていけばよい。 加齢に伴って、さまざまな原因により脳のある部分に 傷がついて、そこにてんかん原性が生じる。 成人てんかん診療においては、焦点性てんかんを想定し、治療においては焦点性てんかんに有効な抗てんかん薬を処方できればよい。
#105.
若年者のてんかん診断の場合には、 専門医への紹介が妥当だろう。 一方、成人てんかん診療でも、全般てんかんをみる可能性がある。 10代~20代までの新規発症のてんかんの場合で考えられる。 小児科でない、内科での診療においては、比較的若年者のてんかんの場合に、全般てんかんの可能性がある。 この場合には、焦点性てんかんでない可能性があるので、専門医への紹介を行い、抗てんかん薬の選定をしてもらうのが妥当だろう。
#106.
抗てんかん薬の特徴と 使い方について
#107.
ブロードスペクトラムの 新規抗てんかん薬 →焦点性でも全般でもOK →副作用少ない →効果はオールマイティ →レベチラセタム、ラモトリギン
#108.
添付文書で示されている、一般的な使用量は1,000mg/day。 レベチラセタムのメリット、デメリットは以下。 メリット:薬剤相互作用が少ない。副作用が少ない。漸増の必要がなく、有効用量を最初から投与できる。つまり、急性期に使いやすい。点滴製剤がある。 デメリット:眠気が強く、使用継続できない症例がある。また、易怒性を誘発することがある。 レベチラセタム 新規抗てんかん薬で、使用しやすい抗てんかん薬の1つ。非専門医が習熟すべき、薬剤の1つ。
抗てんかん薬の使い分けと特徴
#109.
レベチラセタム ① 急性期使用に長じている。 長所 注射製剤もあり、かつ、最初からてんかん発作抑制に十分な有効用量を投与できる。 ERはじめ、急性期病院の現場での使い勝手のよさがある。 短所 眠気や易怒性の誘発は、少なからずあり。 副作用が問題になる場合には、他剤への変更を検討する。 成人てんかんにおいて、非専門医にとっては第1選択にしてもよい薬剤。
#110.
レベチラセタム ② オールマイティな特性。 レベチラセタムの強み:てんかん発作が焦点性てんかん であっても、全般てんかんであっても有効である。 焦点性てんかんか全般てんかんか、てんかん発作分類について診断に悩む場合にも、選択してよい薬剤。 レベチラセタムはすぐに効果が発揮できる、副作用の少ない薬剤で、使い勝手がよい薬剤であるといえる。
#111.
重症薬疹リスクがあり、非専門医にはやや使用しにくい薬剤。 薬疹は、皮疹出現後すぐに中止すること、再診することを徹底してもらえば対応可能である。 また、薬疹リスクを避けるために、添付文書に則った漸増をしなければならないこともデメリット。 漸増プロトコールでは、有効用量に到達するまでには、数週間を要する。 このような性質から、急性期病院の入院加療から始める薬剤としては、すぐにてんかん抑制をしたい、というニーズには応えにくい薬剤。 ラモトリギン 焦点性てんかん・全般てんかん双方に有効な抗てんかん薬です。副作用としては、重症薬疹のリスクがあり、その点についての注意が必要。
#112.
ラモトリギン オールマイティな特性。 メリット :眠気が少なく、高齢者でも使いやすい。 デメリット:投薬開始後、十分な用量まで増量できるまでに数週間を要するため、急性期での現場ニーズには応えにくい。また、重症薬疹の可能性がありうる。 てんかん発作で急性期病院に入院してきた場合には、第1選択薬としては選びにくい薬剤である。 ただし、眠気の少なさ、焦点性てんかん・全般てんかん双方への有効性など、重視すべきメリットがある。
#113.
焦点性てんかん・全般てんかんについて知る。 抗菌薬に例えてみるとわかりやすい。 古典的抗てんかん薬:カルバマゼピンとバルプロ酸 新規抗てんかん薬:非専門医向け カルバペネム的:レベチラセタムとラモトリギン #4 SUMMARY
#114.
#5 抗てんかん薬できった てんかん診療入門②
ケーススタディによる抗てんかん薬の選択
#115.
#5 出会った患者さんの抗てんかん薬の処方内容を理解できるようになりましょう。 抗てんかん薬の使い分けについて知り、自分でも処方できるようになりましょう。
#116.
抗てんかん薬の特徴と 使い方について
#117.
#4の復習 レベチラセタム カルバペネム的抗てんかん薬 焦点性+全般てんかん双方に有効 急性期むけ 眠気と易怒性は時に問題になる ラモトリギン カルバペネム的抗てんかん薬 焦点性+全般てんかん双方に有効 急性期向けではない 重症薬疹リスクは怖い
#118.
ナロースペクトラムの 新規抗てんかん薬 →焦点性てんかん用 →副作用少ない →成人てんかんではこれで →ラコサミド
#119.
メリット :焦点性てんかんについて、有効性が高い薬剤。 デメリット:高価。心筋伝導障害の可能性もある。 焦点性てんかんでは使いやすく、効果も期待しやすい。 有効性はカルバマゼピンと同等。一方副作用は目立たない。 成人てんかん診療では、基本的に焦点性てんかんが対応できればよい、という考えからは、ラコサミドは成人てんかん診療での今後の第1選択薬になる薬剤と言える。 ラコサミド 焦点性てんかんに有効な新規抗てんかん薬。 副作用もあまり目立たず、非専門医でも使用しやすい薬剤。
#120.
ラコサミド 眠気少なく、効果もよい。 200mg/dayが維持量。 1週間での有効用量までの増量が可能であり、レベチラセタム同様急性期病院で使用しやすい薬剤。 眠気が問題になりにくい薬剤でもあり、第1選択薬で眠気が問題になり、継続できなかった症例で変更薬剤の選択肢になる。 高齢者でも比較的使いやすい薬剤。 副作用の心筋電導障害の報告はある。 あまり弱点がなく、焦点性てんかんでは頼りになる薬剤。
抗てんかん薬の処方例と考慮点
#121.
ブロードスペクトラムの 古典的抗てんかん薬 →焦点性も全般も →比較的使いやすい →他の新規抗てんかん薬の 代用的存在 →ゾニサミド
#122.
メリット :比較的広い治療スペクトラム デメリット:尿管結石のリスク 尿管結石の副作用がある。 従来薬(第一世代)の中では新しい薬剤で新規抗てんかん薬よりも安価。 金銭的問題で、レベチラセタム・ラモトリギン・ラコサミドが使えないときの変更薬剤の選択肢として、1つ覚えておく。 ゾニサミド 基本的には焦点性てんかんで使用する。眠気など問題になりにくく、選択肢の1つとして知っておいてもいい薬剤。
#123.
ナロースペクトラムの 古典的てんかん薬 →焦点性てんかん用 →副作用気になる →効果は期待できる →カルバマゼピン
#124.
メリット :焦点性てんかんへの高い有効性。安価である。 デメリット:副作用(眠気、薬物相互作用、低Na血症を誘発) 新規抗てんかん薬に比べて安価である。 投与開始の際には、眠気やふらつきなどが問題になるので、 少量からの開始が必要。 金銭的な問題がクリアできるなら、高齢者では使いにくいため、避けてもいい。 いずれにせよ、過去から現在においても、焦点性てんかんでの中核的な役割を果たす薬剤である。 カルバマゼピン 焦点性てんかんで使用する中核的な薬剤。ただし、薬物相互作用の点、薬疹、低Na血症の原因になりうるなど使いにくい点がある。
#125.
ブロードスペクトラムの 古典的てんかん薬 →全般てんかん用 →副作用は許容できる →成人での使い方は特別 →バルプロ酸
#126.
他剤で、眠気が問題になった場合の選択肢。 焦点性てんかんをバルプロ酸でコントロールしようとする 場合には、比較的高用量を要する。 mood stabilizerとしての副次的な効果も期待して処方することもある。 メリット :副作用が少ない。眠気が少ない。 デメリット:焦点性てんかんについてのてんかん抑制は 効果不十分な可能性がある。 バルプロ酸 全般てんかんの第1選択薬。成人の焦点性てんかんで使う場合には、特別な条件の場合に限られる。
抗てんかん薬の使い分けにおけるポイント
#127.
抗てんかん薬の 処方例
#128.
抗てんかん薬の選択において、考慮されるポイント ▲薬剤相互作用を気にする場合。 ▲怒りっぽい症状が既に知られている。 ▲第1選択薬で眠気が問題になった。 ▲薬価が問題になる。 いずれかの抗てんかん薬を選択する場合には、考慮する条件がある。現実的な診療でよくであるポイントについて解説する。
#129.
古典的抗てんかん薬は、薬剤相互作用がある。 併存症のため多剤内服しており、薬物同士の相互作用が気になる、という場合には、新規抗てんかん薬を選択する。 レベチラセタム、ラモトリギン、ラコサミドが選択肢になる。 薬剤相互作用を気にする場合。
#130.
認知症の周辺症状、また元々のキャラクターで、怒りっぽい症状がある場合にはレベチラセタムは避ける。 易怒性を助長する可能性がある。 この場合は、新規抗てんかん薬では、 ラコサミド、ラモトリギンが選択肢になる。 古典的な抗てんかん薬では、カルバマゼピン、バルプロ酸が選択肢になる。Mood stabilizarとしての効果を持つ、カルバマゼピン、バルプロ酸は違った意図で双方選択肢になる。 怒りっぽい症状が既に知られている。
#131.
この場合には、眠気が問題になりやすい、レベチラセタム、 カルバマゼピンは避けることになる。 この場合には、眠気が少ない、ラコサミド、ラモトリギン、 バルプロ酸が選択肢になる。 第1選択薬で眠気が問題になった。
#132.
薬価が問題になる場合には、新規抗てんかん薬は不適切であり、カルバマゼピン、バルプロ酸が選択肢になる。 ゾニサミドも選択肢にしてもいい。 薬価が問題になる。
抗てんかん薬の特徴まとめとケーススタディ
#133.
使い分けにおける薬剤特徴まとめ 薬物相互作用が少ない:新規抗てんかん薬 薬物相互作用が多い :カルバマゼピン 怒りっぽくなる :レベチラセタム 気分が落ち着く :カルバマゼピン、バルプロ酸、ラモトリギン 眠気がでやすい :レベチラセタム、カルバマゼピン 眠気がでにくい :ラモトリギン、ラコサミド、バルプロ酸 薬価が高い :新規抗てんかん薬 薬価が安い :従来薬
#134.
ケーススタディ
#135.
レベチラセタム1,000mg/dayで治療介入した。発作再然なく自宅退院となった。 退院後外来で、家族から易怒性について指摘をされた。 レベチラセタムの副作用と考えて、レベチラセタムは中止することにした。 代わりに、ラコサミドを選択した。ラコサミド200mg/dayに変更、レベチラセタムは漸減中止し、その後ラコサミド単剤でてんかんなく経過している。 ケース1 5年前に脳梗塞を発症している70歳男性。けいれん発作を来し、入院に至った。けいれんの誘因となる明らかなエピソードなく、けいれん発作前はいつも通りであった。初回発作ではあるが、 脳梗塞発症後に比較的時間経過のある発作であり、再発リスクが高いと判断し、入院中から抗てんかん薬を導入することにした。
#136.
レベチラセタム1,000mg/dayで治療介入した。発作再然なく自宅退院となった。 退院後外来で、家族から易怒性について指摘をさ れた。レベチラセタムの副作用と考えて、レベチラセタムは中止することにした。 代わりに、ラコサミドを選択した。ラコサミド200mg/dayに変更、レベチラセタムは漸減中止し、その後ラコサミド単剤でてんかんなく経過している。 ケース1 5年前に脳梗塞を発症している70歳男性。けいれん発作を来たし、入院に至った。けいれんの誘因となる明らかなエピソードなく、けいれん発作前はいつも通りであった。初回発作ではあるが、 脳梗塞発症後に比較的時間経過のある発作であり、再発リスクが高いと判断し、入院中から抗てんかん薬を導入することにした。 高齢者てんかんの新規導入薬としては使いやすいので、 レベチラセタム。 レベチラセタムは 易怒性の誘発がある。 同じく、新規抗てんかん薬の選択肢、 ラコサミドに変更。
#137.
ケース2 85歳の高齢男性。もともとアルツハイマー型認知症あり、施設入所中。けいれん発作を発症し、発作後意識障害が遷延するため入院になった。今回の発作は2度目であり、発作を繰り返すため抗てんかん薬を導入してから退院することにした。 高齢でもあり眠気を考慮して減量し、レベチラセタム500mg/dayで処方開始した。投薬開始後、眠気の訴えが強く傾眠傾向が認められた。レベチラセタム使用継続は断念した。 レベチラセタムから、ラコサミド200mg/dayに変更し、特に問題なく退院となった。退院後、薬価について家人から相談あり。薬剤変更によるてんかん再然リスクなど説明したうえで、抗てんかん薬を変更することにした。 眠気も問題になっていたことから、バルプロ酸400mg/dayを選択した。てんかん再然があるなら、バルプロ酸を増量、もしくはほかの抗てんかん薬に変更する方針とした。
#138.
ケース2 85歳の高齢男性。もともとアルツハイマー型認知症あり、施設入所中。けいれん発作を発症し、発作後意識障害が遷延するため入院になった。今回の発作は2度目であり、発作を繰り返すため抗てんかん薬を導入してから退院することにした。 高齢でもあり眠気を考慮して減量し、レベチラセタム500mg/dayで処方開始した。投薬開始後、眠気の訴えが強く傾眠傾向が認められた。レベチラセタム使用継続は断念した。 レベチラセタムから、ラコサミド200mg/dayに変更し、特に問題なく退院となった。退院後、薬価について家人から相談あり。薬剤変更によるてんかん再然リスクなど説明したうえで、抗てんかん薬を変更することにした。 眠気も問題になっていたことから、バルプロ酸400mg/dayを選択した。てんかん再然があるなら、バルプロ酸を増量、もしくはほかの抗てんかん薬に変更する方針とした。 高齢者てんかんの新規導入薬としては使いやすいので、 レベチラセタム。 ラコサミドは眠気 少なく使いやすい。 ただし、 新規は高価である。 安価なので古典的薬剤に。バルプロ酸は使いやすいが、効果が不安である。
#139.