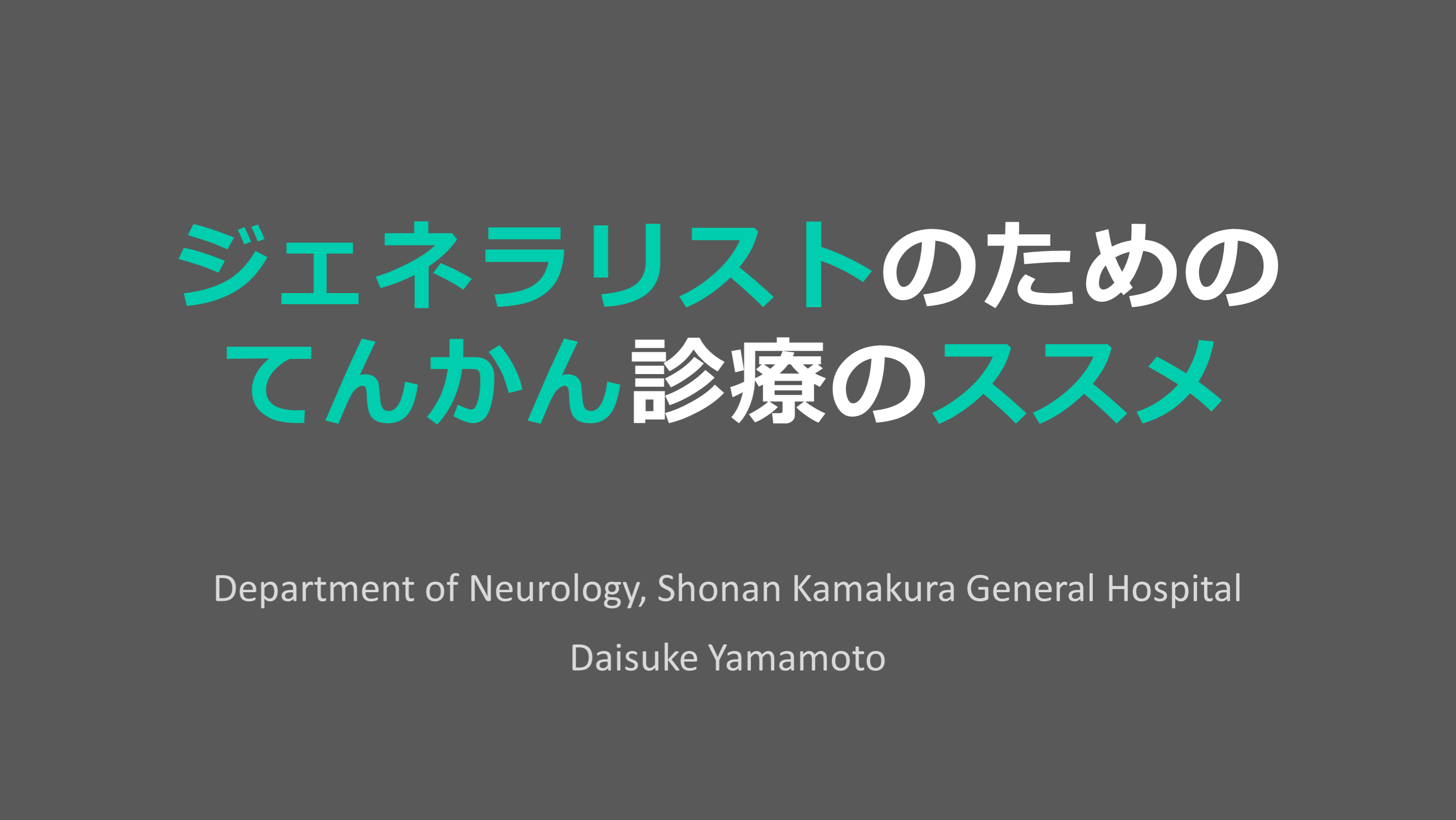1/93
関連するスライド
ERで!各科診療で使える!レジデントのためのてんかん診療必修講義
山本大介
280708
883
ミニマム!運動障害の患者さんに出会ったら
山本大介
151356
290
パーキンソン症候群を見逃してはいませんか?
エスディー@脳神経内科
67745
213
もう迷わない!外来でのふるえの診かた
エスディー@脳神経内科
66243
342
ジェネラリストのためのてんかん診療のススメ
山本大介
Award 2024 受賞者
医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院
171,660
438
概要
ジェネラリスト/非専門医を対象としたてんかん診療の始め方について解説しています。介入可能な症例、使用しやすい薬剤などについての理解を深めるためのスライドです。
【書籍:みんなの脳神経内科】https://www.amazon.co.jp/dp/4498328736
本スライドの対象者
専攻医/専門医
投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!
0 件のコメント
山本大介さんの他の投稿スライド
片頭痛診療、はじめの一歩。
山本大介
274,614
626
ミニマム!運動障害の患者さんに出会ったら
山本大介
151,356
290
Common diseaseである脳卒中後てんかんを学ぶ。
山本大介
123,990
347
このスライドと同じ診療科のスライド
テキスト全文
ジェネラリストのためのてんかん診療の概要
#1.
Department of Neurology, Shonan Kamakura General Hospital Daisuke Yamamoto ジェネラリストのための てんかん診療のススメ
#2.
Introduction このプレゼンテーションは総論的なてんかん診療を テーマにしていません。 ジェネラリストが実行可能である、ということを主題にした、 てんかん診療の実践方法を学ぶためのプレゼンテーションです。
#3.
まずはてんかんを 自分で説明できる てんかん診療を始めるには、まずは自分の言葉で 「てんかん」を説明できなければいけません。 どのように説明すればいいでしょうか。
てんかんの定義と有病率
#4.
てんかん とはなにか? まずはてんかんの定義からです。てんかんとは何か、を自分で説明しましょう。ガイドラインでは、このように説明されています。 <てんかんの定義> てんかんとは、てんかん性発作を引き起こす持続性素因を特徴とする脳の障害である。 すなわち、慢性の脳の病気で、大脳の神経細胞が過剰に興奮するための脳の発作性症状が反復性に起こる。 発作は突然起こり、普通とは異なる身体症状や、意識、および感覚の変化などが生じる。明らかなけいれんがあれば、てんかんの可能性は高い。 てんかん診療ガイドライン2018
#5.
自分の言葉使いで 説明すると わかりやすく嚙み砕いて、このように説明してみます。ご参考にしてください。 けいれん発作のないてんかん発作があることも考慮して、説明に加えています。 <平易なてんかんの説明> てんかんとは、脳の特定の部分から異常な電気活動(ノイズと表現したりもします)が起こり、結果としてその場所の脳の機能がおちてぼーっとしたり、運動神経まで広がればけいれんを起こしたりする病気です。 このような発作を反復しうるので、治療のための薬を飲むか飲まないかの検討を要します。
#6.
てんかんは 稀なものなのか? それほど稀ではないのか? 頻度について言及しましょう。 特にこのプレゼンテーションの肝である、高齢者てんかんについて説明できる必要があります。 高齢者てんかんの原因としては、加齢に伴い、脳の一部分に傷がついて、その部分にてんかん原性が起こりえます。このロジックについても説明できるようにして下さい。 <有病率についての知識> てんかんの有病率は0.8%である。 てんかんは、小児期に発症するイメージはあるが、高齢者はてんかんを好発する。 65歳以上のてんかん有病率は1%以上 (1~2%)と推定される。より高齢になればなるほど、発病率は高くなることが知られている。 Epilepsia 2008;26:19-22
抗てんかん薬導入の基本ルール
#7.
介入の基本ルール 2回目の発作から 今一度、抗てんかん薬導入についての「発作2回目ルール」を理解しましょう。 初回発作では治療介入しない、2回目の発作があれば治療介入を検討する、というものです。 そもそも、てんかんの定義(部分)ですが、 「24時間以上の間隔で、2回以上の非誘発性発作が生じる」とされています。 (非誘発性発作とは、明らかな誘因がない、慢性疾患としての自発発作を意味します。)
#8.
確率の話 てんかん発作の2回目以降に治療介入を検討するこのルールは、疫学データに支持されています。 非誘発性の孤発発作が出現した後の 再発リスクは 40~52%である 。 非誘発性の無熱性発作が 2 回出現した場合、4 年後までに再発する確率は 73%を超える。 <シンプルに説明するなら> 1度だけけいれん発作があった場合は、2回目が必ずあるとは限らない。 半分以上の人は再発がない。 しかしながら、2回以上けいれん発作があった場合には、その後の 発作再発率は非常に高い。 よって、2回目の発作をもって、治療介入が検討されることになる。 Epilepsia 2014;55:475-482
#9.
1回目の発作から 抗てんかん薬を 開始する場合 基本ルールでは、2回以上の発作で介入を検討する、でした。 初回発作でも介入を検討する場合もあります。 特に、ジェネラリストが対応する場合には、 このシチュエーションを押さえておいてください。
#10.
初回から介入する場合① 1つ目は、高齢者てんかん(65歳以上発症) の場合です。この場合は再発率が高いので、治療介入が初回発作から検討されます。この事実を伝えて、初回発作からの介入を相談することになります。 <高齢者てんかんについて> 高齢者てんかんは、一度てんかん発作を生じた場合、若年者よりも 再発リスクが高い。 特に脳梗塞など既往がある場合には 再発リスクが高くなる。 よって、原因となる脳病変(脳卒中・アルツハイマー病など)が指摘できる場合には、初回発作から治療を始めることも多い。 標準的神経治療:高齢発症てんかん 日本神経治療学会
高齢者てんかんの介入条件
#11.
初回から介入する場合② 2つ目は、脳卒中慢性期のてんかん発作 の場合です。やはり、初回発作後の再発率の高さによります。再発率の高さが知られているため、患者さんと相談し初回からの抗てんかん薬の導入は検討されます。脳卒中の合併も多い、高齢発症てんかんと合わせて理解しておきます。 <脳卒中後のてんかん> 高齢発症てんかんの原因で最も多いのは脳卒中で、原因の30-40%を占める。 そもそも、脳卒中後に症候性てんかんを生じる頻度は2-4%である。 脳卒中慢性期のてんかん発作再発率は、10年以内で60%以上である。 脳卒中後てんかん発作では、初回発作から抗てんかん薬の導入が検討されることが多い。 標準的神経治療:高齢発症てんかん 日本神経治療学会
#12.
てんかんとは何かを自分で伝えることができる 高齢者てんかんの理屈を説明できる 二回目発作からの介入ルールについて説明できる 初回発作からの介入条件について説明できる つまり、脳卒中後てんかん、高齢者てんかんが シンプルな介入の対象者であると知る。 SUMMARY
介入対象者の選定基準
#13.
ジェネラリストが 介入できる症例は? てんかんは、コモンな疾患であることから、 ジェネラリストも活躍の場所としてほしい領域です。 しかしながら、適切に介入するのに、治療対象者を選ぶことは重要です。
#14.
ルール: 脳卒中後てんかん に介入。 高齢者てんかん に介入。 この二つのてんかんを、治療対象者として選ぶことを提案します。 脳卒中後てんかん、高齢者てんかんは、先述の内容に加え、以下の特徴があります。 てんかん発作の再発率が高い。 診断について、評価がしやすい。 初回発作からでも介入が検討される。 脳卒中、高齢患者はともに、プライマリケア領域で頻度が高い。 患者対象:高齢者 においては、よりプライマリケア領域での介入が望まれる。 以上の理由から、この2つのてんかんは、ジェネラリストによる介入の、よき適応と考えます。
#15.
ルール: けいれん発作が 確認できた症例にのみ介入 てんかん発作が、必ずしも「けいれんを伴う発作」とは限りません。 けいれんのない発作は介入の難しさがあります。 けいれんのない発作を対象とするのは知識と技術が必要でしょう。 ただし、けいれん発作が確認できた症例への介入と決めれば、悩みは少なくなるはず。 ここでの提案は、介入症例をけいれん発作があった症例に絞ってみる、としてみます。 けいれん発作がなく、てんかん発作かどうか区別できない場合は専門医への紹介を検討して下さい。
けいれん発作の確認と介入のルール
#16.
実際のけいれん発作に加え、 「てんかん」を 肯定できる要素 てんかんの診断をより肯定できるための、 補助的な要素も確認しましょう。 発作後の遷延する意識障害、がわかりやすい要素です。けいれん発作に加えて、この要素が確認できれば、より安心しててんかん発作だと言えそうです。 <発作後意識障害と健忘> 発作後に意識障害が遷延する (5分以上)。 発作・発作後の健忘がある。 これらが確認できるの、けいれん発作が確かに、「脳由来」である、と言えます。失神性けいれんでは、長時間の健忘や意識障害の遷延は説明困難です。
#17.
ルール: 若年者のけいれん発作 は介入しない。 介入しないラインも決めておくのはいいでしょう。 小児科でない場合には、teenagerの初発けいれん発作を みる可能性はあるでしょう。 この場合は判断の複雑さがあるので、介入しないと決めるのも一つの考え方です。
#18.
若年者はやめておく 後述しますが、てんかんの発作分類は、焦点性発作と全般性発作の2通りです。 高齢であれば、焦点性発作をほぼ意識すればよく、投薬はシンプルです。 若年者では、焦点性発作・全般性発作両方の可能性があり、投薬選択が複雑になります。また若年者である場合には、専門医受診のニーズも高い可能性もあります。この場合、介入しないと決めてしまうのは、一つの考え方です。
#19.
介入の推奨 =>高齢者てんかん 介入の推奨 =>脳卒中後てんかん 介入の推奨 =>けいれん発作が確認できた症例 介入の非推奨 =>若年者のてんかん けいれん発作に加えて、確認できるとてんかんを 肯定できる要素=>長時間遷延する意識障害 SUMMARY
急性症候性発作の理解と検査
#20.
てんかんの診断の しかた どのような思考でてんかんを診断していくのか。
#21.
急性症候性発作について やはり知っておく必要あり。 急性症候性発作とは・・・「代謝性、中毒性、器質性、感染性、炎症性などの 急性中枢神経障害と時間的に密接に関連して起こる発作である。」 急性症候性発作は、「てんかん」ではありません。何らかの原因によって引き起こされたけいれん発作を指します。急性症候性発作の場合には、てんかん発作以外に、治療介入すべき他の要素がでてきます。抗てんかん薬の処方のみのアクションではなくなります。よって、初発のけいれん発作を見たときの入り口は常に、その発作が急性症候性発作かどうか?を検討して下さい。 てんかん診療ガイドライン2018
#22.
急性症候性発作の中身は? 初発のけいれん発作では、 これらの可能性はどうか、を 検討しておく必要があります。 採血検査で評価可能なものもあれば、頭部画像検査や髄液検査などまで加えないと評価できないものも含まれてきます。 特に新規発症の脳卒中の評価が重要です。 また、新規開始薬剤がないか?も確認して下さい。薬剤性要因についての検討も必要です。 <急性症候性発作の中身> 脳血管障害(発症後7日以内) 中枢神経系感染症 頭部外傷 代謝異常:低血糖・尿毒症・肝性脳症 電解質異常:低Na血症 中毒:アルコール・テオフィリン 脳炎 てんかん診療ガイドライン2018
急性症候性発作の介入要件
#23.
介入可能な要件:発作後full recoverし、 ベースラインの状態まで元に戻り、 急性症候性発作が否定できるなら。 特に残存症状なく、元通りの状態まで戻ったなら、 介入が必要な急性症候性発作の可能性は低いと評価できます。 この場合には、「てんかん」としての評価に近づきます。 逆に、ベースラインの状態までの改善がないなら、 急性症候性発作の可能性を追求し、原因追及を十分に行う必要があります。
#24.
検査について 採血 頭部MRI 脳波 急性症候性発作の否定のため、また器質的な脳病変の評価のため、やはり検査は一通り施行はしておきたいところです。 採血=>電解質異常のチェック、感染症の可能性のチェック MRI=>てんかんの原因になりうる、器質的病変のチェック 脳波=>治療前のベースラインとなる脳波所見の確認 これらの検査施行は検討されます。
#25.
急性症候性発作はやはり知っておく。 常に、てんかん評価の頭の片隅に置いておく。 発作後元通りにならないなら、急性症候性発作 の可能性は十分に追求する。 基本の検査は、採血、MRI、可能なら脳波。 全例必須とは言わないが、気になるところが あるなら検査施行は推奨される。 SUMMARY
抗てんかん薬の選択と特徴
#26.
診断をしたら、 次に薬はどれを選ぶか? 抗てんかん薬の特徴を理解しましょう。
#27.
抗菌薬に例えて説明。 Narrowか?Broadか? 抗菌薬に例える手法は非専門医の先生方に伝わりやすいので、好んでいます。 「CBZ(カルバマゼピン)はCEZ(セファゾリン)です」。 「LEV(レベチラセタム)はMEPM(メロペネム)です」。 など、抗菌薬に例えるとイメージがわきやすいです。また、抗てんかん薬と抗菌薬の特徴において、ニュアンスが類似しているところもあります。抗てんかん薬には、守備範囲があり、抗菌薬同様spectrumで語られます。
#28.
Narrowとは? =焦点性てんかんに有効である、 ことを意味します。 <narrow spectrumのAED> 焦点性てんかんとは、脳の特定部位から異常放電を来たし、てんかん発作に至る、てんかん分類。 焦点性てんかんを考慮する場合には、narrow spectrumの抗てんかん薬が治療薬で選ばれます。 代表的な抗てんかん薬はCBZです。 抗菌薬に例えて、CEZと説明します。
#29.
Broadとは? =焦点性てんかん・全般性てんかん 双方に有効である、こと意味します。 <broad spectrumのAED> 全般性てんかんとは、脳全体に異常放電の発火を来し、てんかん発作に至る てんかん分類です。 発作分類が、焦点性か、全般性てんかんか区別しにくい場合もあります。 この場合は、双方に有効なbroad spectrumの抗てんかん薬を選びます。 代表薬剤はLEVです。 抗菌薬に例えてMEPMと説明します。
#30.
古典的抗てんかん薬について 従来薬=>プロ処方として理解 従来薬の代表薬は、カルバマゼピンとバルプロ酸です。 カルバマゼピンは=>昔からの、焦点性てんかんの第一選択薬 です。 バルプロ酸は =>昔からの、全般性てんかんの第一選択薬 です。 これら2剤は昔から現在までも、第1選択薬の位置づけです。しかしながら、プロ(専門医)処方として理解してもよいでしょう。その理由は、薬剤相互作用(併用薬の効果を変えてしまう)や薬剤の副作用によります。プロでなければ、従来薬は避けてもよいと思われます。
新規抗てんかん薬と従来薬の比較
#31.
新規抗てんかん薬について 新規=>使いやすい 近年登場した抗てんかん薬は、新規抗てんかん薬として位置付けられます。 代表薬は、レベチラセタム。抗菌薬に例えるなら、カルバペネムをイメージします。 新規抗てんかん薬の特徴は、「副作用の少なさ」と言えるでしょう。 代表薬であるレベチラセタムは、ブロードスペクトラムで、副作用が少ない、となると、非専門医にとって使用しやすい抗てんかん薬である、と言えるでしょう。 プロでなければ(非専門医なら)新規抗てんかん薬を選択する、と決めるのは一つの考え方です。
#32.
新規と従来薬の それぞれの特徴のまとめ 副作用 薬物相互作用 薬価 新規抗てんかん薬 少ない 気にしない 高い 従来薬 多い 気にする 安い 新規抗てんかん薬は従来薬と比較し、使用しやすい薬剤と言えます。 しかしながら、新規抗てんかん薬の唯一の弱点は、薬価といえます。 コストについては、患者さんと相談する必要はあります。
#33.
ここからは、抗てんかん薬 についての各論です。 それぞれの薬剤の特徴を知りましょう。 抗菌薬に例えながら、それぞれの薬剤のイメージを定着させてください。
#34.
CBZ カルバマゼピン 抗菌薬なら、CEZとして説明する。 副作用=>色々気になる。 ナロースペクトラム(焦点性用) 効果は十分である。 従来薬=プロ処方である。 ナロースペクトラムの代表選手です。効果は頼りになるものの、副作用が多々問題になります。よって、プロ処方として位置付けていいでしょう。 抗菌薬に例えて、CEZセファゾリンとして説明しています。 副作用は、眠気、ふらつき、低Na血症が問題になります。 薬物相互作用があり、多剤併用患者=すなわち高齢者 では避けられる薬剤です。
#35.
VPA バルプロ酸 抗菌薬なら三世代経口セフェムで例える。 副作用=>少ない。 ブロードスペクトラム(焦点性+全般性) 焦点性用としては、効果は不十分です。 成人で使用する場合は限定的な場面になる。 成人での使い道は限定的です。 眠気の少なさ、副作用の少なさが長所です。 よって、眠気で他剤が使えなかった症例などで、選択肢になります。 成人てんかん診療では、主として焦点性てんかんを対象とします。よって、VPAをあえて使うとすれば、使用しなければならない特別な理由がある場合のみです。
#36.
LEV レベチラセタム 抗菌薬なら、カルバペネム! 副作用は少ない。 ブロードスペクトラム(焦点性+全般性) オールマイティな使い勝手。 発作抑制効果は少し弱いかもしれない。 カルバペネム的抗てんかん薬です。 てんかんの診断が正しければ、発作分類は問わない、オールマイティな薬剤です。 副作用は、眠気と易怒性です。これは留意しておいてください。 静注薬もあり、頻用されます。 使い勝手がいい薬剤で、新規抗てんかん薬の代表薬といっていいでしょう。
#37.
LTG ラモトリギン 抗菌薬なら、カルバペネム! 副作用=>導入時皮疹に注意。 ブロードスペクトラム(焦点性+全般性) オールマイティ。効果も十分。 漸増を要し導入に時間がかかるのは弱点。 カルバペネム的抗てんかん薬です。 てんかんの診断が正しければ、発作分類は問わない、オールマイティな薬剤です。 副作用は、あまり問題になりません。 最大の弱点は、漸増に時間がかかることです。有効用量に達するまで2-3カ月要します。 また、重症薬疹リスクもあります。 薬剤導入のしにくさは、ジェネラリスト向けとは言いにくそうです。
#38.
LCM ラコサミド 抗菌薬なら、スーパーCEZ! 副作用=>少ない。 ナロースペクトラム(焦点性用) 効果は十分。 成人てんかんの主力といってよい。 新規抗てんかん薬ですが、ナロースペクトラムです。 CBZの上位互換、と説明しています。CBZの副作用がないバージョン。 抗てんかん薬で問題になりやすい、眠気もあまり目立ちません。 効果も高く、使いやすい薬剤です。 まれだが、徐脈の副作用には留意。
抗てんかん薬の特徴まとめ
#39.
ZNS ゾニサミド 抗菌薬なら、第二世代セフェム的? 副作用=>精神症状には悪い可能性。 ナロースペクトラム(焦点性用) 効果は十分。 従来薬であり、安価である。 従来薬ですが、第1世代(従来薬)の晩期に登場したものです。ある程度新規抗てんかん薬(第2世代)のようなニュアンスで使えます。 コストが安いので、新規抗てんかん薬が使えない場合の代替薬として重宝します。 弱点は、精神症状への悪影響は知られています。
#40.
AEDの特徴まとめ Narrow spectrum? Broad spectrum?で区別される特徴がある。 新規? 従来薬?で区別される特徴がある。 発作抑制効果で区別される特徴がある。
抗てんかん薬の使い分けのポイント
#41.
AEDの使い分けのポイント いずれかの抗てんかん薬を選択する場合には、考慮する条件がある。 臨床で、よく出会うポイントについて解説していきます。 抗てんかん薬の選択において、考慮されるポイント ▲薬剤相互作用を気にする場合。 ▲怒りっぽい症状が既に知られている。 ▲第1選択薬で眠気が問題になった。 ▲薬価が問題になる。
#42.
従来薬は、薬剤相互作用がある。 併存症のため多剤内服しており、薬物同士の相互作用が気になる、という場合には、新規抗てんかん薬を選択する。 よって、LEV、LTG、LCMが選択肢になる。 薬剤相互作用を気にする場合。
#43.
認知症の周辺症状、また元々のキャラクターで、怒りっぽい症状がある場合にはLEVは避ける。 易怒性を助長する可能性がある。 この場合は、新規抗てんかん薬では、LCM、LTGが選択肢になる。 従来薬では、CBZ、VPAが選択肢になる。Mood stabilizarとしての効果を持つ、CBZ、VPAは違った意図で双方選択肢になる。 怒りっぽい症状が既に知られている。
#44.
この場合には、眠気が問題になりやすい、LEV、CBZは避けることになる。 この場合には、眠気が少ない、LCM、LTG、VPAが選択肢になる。 第1選択薬で眠気が問題になった。
#45.
薬価が問題になる場合には、新規抗てんかん薬は不適切であり、CBZ、VPAが選択肢になる。 ZNSも選択肢にしてもいい。 薬価が問題になる。
#46.
使い分けにおける薬剤特徴まとめ 薬物相互作用が少ない:新規抗てんかん薬 薬物相互作用が多い :CBZ 怒りっぽくなる :LEV 気分が落ち着く :CBZ, VPA, LTG 眠気がでやすい :LEV, CBZ 眠気がでにくい :LTG, LCM, VPA 薬価が高い :新規抗てんかん薬 薬価が安い :従来薬
ジェネラリストが介入する薬剤の選定
#47.
ナロースペクトラムで選ぶなら =>LCM ラコサミド ブロードスペクトラムで選ぶなら =>LEV レベチラセタム 金銭的な問題があるなら =>ZNS ゾニサミド ジェネラリストが介入するなら使用する薬剤(私見)
#48.
ジェネラリストが介入するなら避ける薬(私見) 成人では限定的な使い道 =>VPA バルプロ酸 は避ける。 プロ処方として認識するなら =>CBZ カルバマゼピン は避ける。 薬疹リスクを避けたいなら =>LTG ラモトリギン は避ける。 金銭的な問題があるなら =>新規抗てんかん薬 は避ける。
#49.
薬剤の特徴ごとに、 使用しやすさと、使用しにくさがあり、 おのずと、選択する抗てんかん薬は決まってくる。 SUMMARY
治療開始後のフォローアップと注意点
#50.
治療開始後、 どうすればいいか? 投薬開始後に、何が検討事項なのかを事前に伝えましょう。
#51.
最初に共有する説明 1 AEDの忍容性があるかどうかを見極めていきましょう。 2 AEDの有効性を見極めていきましょう。 この2点について、説明しておきましょう。
#52.
忍容性について 抗てんかん薬は忍容性が重要です。続けられない人が多いです。 それぞれの抗てんかん薬が、うまくいかなくなる理由を把握しておくことは重要です。まずは、その人が選択した薬剤を継続できるかどうかを確認していきます。
#53.
有効性について:増量 薬剤選択をし、治療開始したとしても、発作を来すこともあります。 その場合、まずは第一原則としては、最初の選択薬を十分量まで増量することになります。うまくいかなかったら、まずは増量対応とします。
#54.
有効性について:変更 最初に始めた抗てんかん薬を増量してもダメだった場合は、他剤に変更することになります。 うまくいかなかったら、今後変更する可能性があることも伝えておきます。 いずれにせよ、治療を始めた後も、薬剤の調整が必要な可能性があることは伝えておきます。
#55.
専門医への 紹介タイミング? 治療方針に困ったなら紹介は潔く、が良いでしょう。 うまくいかないなら専門医へ紹介して、処方を決めてもらいましょう。
#56.
無理はしない。 例えば、1剤目の選択でうまくいかなければ、プロへの紹介も検討していいかもしれません。習熟するまでは、悩むならすぐにコンサルトでいいでしょう。
#57.
忍容性について 有効性について 専門医への紹介について これらについて、自分の中で整理し、 治療方針についてきちんと伝えておきましょう。 SUMMARY
専門医への紹介タイミングとルール
#58.
専門医から フォローアップを 依頼されたら? 専門外来で、てんかんの外来はDO処方になりがち。 可能であれば、安定している患者さんは ジェネラリストにフォローアップしてほしい。と思っている。
#59.
ルール: 処方継続すればよい。 紹介されてきたら、依頼された処方を継続すればよいです。 あえては、気にすべきことをいくらか挙げていきます。
#60.
ルール: よくある副作用には留意。 薬剤による眠気がある。 薬剤による性格変化がある。 薬剤による肝障害・腎障害がある。 薬剤による血球減少症がある。 薬剤のコストが問題視されている。 これらは、忍容性に影響がありますので、確認していくことが重要になります。 先述の薬剤の特徴も併せて検討して下さい。継続困難と判断するなら、紹介元に戻してください。 よくある副作用について知っておいて下さい。先述の薬剤忍容性と同様の内容になります。
#61.
ルール: 発作があればコンサルト すればよい。 もちろん発作のコントロールが悪ければ再度紹介すればよいです。 ただし、発作があったときに、これくらいは確認してみてください。 きちんと内服できているか。コンプライアンスの確認。 寝不足など、心身ともに負荷がなかったか? 新規開始薬剤はなかったか?薬剤誘発性の可能性? てんかん以外の要因(感染症など)はないか? 発作の原因が抗てんかん薬にない場合もあり、これらは紹介前に少なくとも確認して下さい。
#62.
血中濃度測定は? 特定の薬剤のみ、副作用モニタリングのために血中濃度測定は行ってください。 発作コントロールが良好であれば、特に副作用を疑うシチュエーションでなければ、血中濃度測定は基本的には不要です。 <血中濃度測定をする薬剤> フェニトイン カルバマゼピン フェノバルビタール バルプロ酸 =>基本的には薬物中毒を疑ったときに 血中濃度測定を施行して下さい。念のため上記薬剤なら時々は確認して下さい。
ケーススタディによる知識の定着
#63.
処方継続依頼は淡々と行えばよい。 よくある副作用は知っておくのがよい。 発作があればまた紹介すればよい。 血中濃度測定は基本的には不要。特定の薬剤(従来薬)で検討。 SUMMARY
#64.
ケーススタディで 知識の定着 最後にここまでの復習を兼ねて、知識のおさらいをしよう。
#65.
CASE 1
#66.
どのような点を確認し、介入してよいかどうかを整理すればよいでしょうか? ここまでのルールをもとに考えてみましょう。 高血圧症で自分の外来かかりつけ。 50歳男性 48歳時脳内出血の既往あり ある日、けいれん発作を認めた。 ER受診後、帰宅指示となり内科外来へ再診した。
#67.
ルール:脳卒中後てんかんは介入してよい。 脳卒中後てんかんなので、再発率は高いです。 この場合、てんかん発作の原因は脳出血であり、「症候性てんかん」として評価はシンプルです。特に、発作後の残存症状はなく、元の状態までの改善が得られています。 本例は、ジェネラリストの介入可能な症例として、判断してよいでしょう。
#68.
ルール:けいれん発作が確認できた症例に介入。 てんかん発作がすべて、けいれん発作であるとは限りません。 けいれん発作を伴わない、てんかん発作もありえます。 本例は、けいれん発作が確かに確認された症例です。よりてんかんらしさ、を知るには、「発作後の比較的長い意識障害の遷延と健忘症状」の存在を確認する、でした。 けいれん発作+意識障害/健忘あり、と評価できれば、脳由来の異常電気活動によるけいれん発作、すなわち、てんかん発作として評価可能でしょう。 失神後けいれんなど、他にけいれんを来すような疾患は鑑別できそうです。
#69.
ルール:急性症候性発作が鑑別できている。 とにもかくにも、これが最重要です。外来受診時には、いつも通りの様子が確認できました。 ERでは、採血検査が施行されており、特に問題はありませんでした。また、頭部CTも施行されており、再出血はなかったようです。念には念を入れるなら、待機的にMRIは施行しておきましょう。 「脳出血の既往」以外の原因が否定できれば、急性症候性発作が否定され、「てんかん」として診断可能になります。急性症候性発作が鑑別できているので、介入の可能症例と考えます。
#70.
薬剤選択=>LCM/LEV 新規抗てんかん薬で行こう!がジェネラリスト向け抗てんかん薬選択の第一歩です。 脳出血後であり、焦点性てんかんを考慮します。 焦点性てんかんを考えるなら、ナロースペクトラムを選ぶのがシンプルです。 ナロースペクトラムで選ぶ =>super CEZ の LCM ラコサミド を選択する。 ブロードスペクトラムで選ぶ =>カルバペネムの LEV レベチラセタム を選択する。 新規抗てんかん薬で、いずれの選択でもOKです。
#71.
患者説明① このように説明して みましょう。 『脳出血後慢性期にけいれん発作を来しました。 これは、てんかん発作として理解されます。 てんかん発作とは、脳の一部分から起こる、異常な電気活動によるけいれん発作です。 脳出血後の病変から、そのノイズは出ていると推測されます。 検査では、その他にけいれん発作を来す問題のある病態はなさそうです。 脳出血後のてんかん発作は再発率が高いです。 抗てんかん薬は初回発作から検討してもいいことになっています。 もちろん、2回目の発作があってから検討、という方針でもいいですよ。』
#72.
患者説明② 抗てんかん薬開始後の説明。 抗てんかん薬は、焦点性てんかん、を重視して『LCM』を選択しました。 今後の方針としては、薬剤の忍容性・有効性を確認していきます。 『LCMは、忍容性はあまり問題となりにくい薬剤です。 有効性に関しては、最初の処方で大丈夫かもしれませんし、 今後の増量が必要な可能性もあります。 発作コントロールが悪ければ、専門医への紹介も今後検討しますね。』
#73.
CASE 2
てんかん診療の重要性とジェネラリストの役割
#74.
どのような点を確認し、介入してよいかどうかを整理すればよいでしょうか? ここまでのルールをもとに考えてみましょう。 アルツハイマー病で施設入所中。 85歳男性 けいれん発作でERより入院。 発作の結果、誤嚥性肺炎も併発あり、総合内科へ入院。
#75.
ルール:高齢発症のてんかん、 器質的背景が指摘できる(認知症背景)なので 治療介入を検討してもよい。 アルツハイマー病背景のてんかんとして、了解しやすい症例といえます。 初回発作ですが、抗てんかん薬の導入は検討してよいです。 今回のように、高齢者がてんかん発作で入院になるケースもあります。 発作自体がADL低下を来すイベントになりえます。よって、発作抑制は重要です。
#76.
ルール:けいれん発作が確認できた症例は 「てんかん」として評価しやすい。 けいれん発作がきちんと確認できたので、てんかん発作としては了解しやすいです。 けいれん発作のない発作(複雑部分発作)も高齢者てんかんでは多いことが 特徴ではあります。 発作後の意識障害の遷延は、高齢であったり認知機能障害があったりすると、 長期間遷延しやすいです。回復まで比較的日数を要することもあります。
#77.
ルール:急性症候性発作が鑑別できている。 てんかんの診断において重要なのは、 採血検査、画像検査で急性症候性発作の除外をする、でした。 高齢であるので、MRI施行による脳梗塞の除外は行っておきたいところです。脳梗塞を新規に発症し、てんかん発作を来したかどうか?は、確認しておきたいところです。採血検査も施行し、急性症候性発作を除外しておきましょう。
#78.
薬剤選択=>LCM/LEV 新規抗てんかん薬で行こう!がジェネラリスト向け抗てんかん薬の第一歩です。 抗てんかん薬の選択では、以下の思考方法としてください。 高齢発症のてんかんで、焦点性てんかんの可能性が高い。 =>super CEZ の LCM を選択する。 高齢発症であり、薬物相互作用を気にする。 =>新規AEDを選択 =>LEV もしくは LCM を選択する。 いずれの考え方でもOKです。
#79.
患者説明① 抗てんかん薬の導入について 説明する。 『アルツハイマー病が背景にあり、けいれん発作を来しました。 これは「てんかん発作」として理解されます。検査では、とくにけいれん発作を来す、 アルツハイマー病以外の問題のある病態はなさそうです。 今回のように、発作があると入院対応をしなければならなかったりします。 ADL低下にも影響がありそうです。高齢発症のてんかんの再発率も高いです。 今後このような入院を減らすためにも、抗てんかん薬導入は重要です。』
#80.
CASE 3
#81.
今回は処方継続依頼です。 何がポイントなのか、ここまでのルールをもとに考えてみましょう。 65歳男性 脳梗塞後てんかんで急性期治療後。 他院でレベチラセタムが導入された。 状態安定がある、とのことで処方継続依頼をされた。
#82.
ルール:処方継続すればよい。 ルール:よくある副作用には留意。 処方継続依頼をされれば、もちろん継続をすればよいわけです。 一応、よくある薬剤副作用には留意してください。 LEVについては、眠気と易怒性がポイントでした。 「最近よく眠そうにしているんです。」 「最近やけに怒りっぽくなってしまって・・・・。」 などと聞こえてくる場合には、処方元への再度コンサルトをしてください。 この場合には、LEVの忍容性に問題あり、と評価されます。
#83.
患者説明① 有効性・忍容性について 議論する。 『LEVはオールマイティないい薬です。 発作抑制されていますので、有効性については問題はなさそうです。 ただし、LEVの忍容性に問題がありそうです。』 様子を確認すると、眠気があり生活に支障をきたしているようでした。 薬剤選択については、再度紹介元の専門医と相談することにしました。
#84.
CASE 4
#85.
抗てんかん薬の選定について、専門医への紹介を提案しましたが、 このままかかりつけ医での処方希望がありました。 どのような点を確認し、介入してよいかどうかを整理すればよいでしょうか? ここまでのルールをもとに考えてみましょう。 85歳男性 脳梗塞既往あり、軽度認知機能障害もある。 定期外来で、「けいれん発作」のエピソードに ついて訴えあり。
#86.
ルール:脳卒中後・高齢発症てんかんは介入してよい ルール:けいれん発作の確認あり ルール:急性症候性発作の除外をすること この背景であれば、ジェネラリストでも抗てんかん薬介入は可能そうです。 まったくいつもと同じ様子で外来にこられていますので、急性症候性発作も除外可能そうです。一応、採血検査はしておきましょう。
#87.
薬剤選択=>LCM 薬剤選択についてです。以下の思考方法で検討してみて下さい。 高齢発症であり、薬物相互作用を気にする。 =>新規AEDを選択 =>super CEZ の LCM を選択する。 上記で対応してみることにしました。
#88.
ルール:治療開始に当たっては、 忍容性について説明する。 投薬介入後には二つのポイントがありますので理解して下さい。 ①忍容性について=> 『薬が継続可能かどうか、が一つのテーマです。人によって薬の合う合わないがあります。 内服開始後は、まずはそれをフォローしていきましょう。 最初に選んだ薬剤がいまいちだったなら、今後の変更方針になります。』 =>LCMでめまい感の訴えがあり。結局、LCMはやめることにした。 =>もう一つの新規AED、LEVに変更することにした。
#89.
ルール:治療開始に当たっては、 有効性について説明する。 『新しい薬は忍容性は大丈夫そうですね。 もう一つのポイントがあります。それは有効性です。』 ②有効性について=> 『今回選択したLEVで発作抑制が必ずできるとは限りません。 発作抑制が困難だった場合には、二通りの方針になります。 A:薬剤増量、もしくは、B:他剤への変更です。』 =>その後、発作再発あり。LEV1000mgから2000mgに増量しています。
#90.
ルール:困ったら迷わず紹介する。 LCMは忍容性で断念、またLEV変更後発作あり、LEV1000mgから2000mgに増量しました。今後の方針として、色々薬剤を試してみるのもいいですが、LEV増量で対応できなければ、潔く紹介を検討するのもよいでしょう。 『LEV増量対応で発作抑制ができなければ、紹介方針とします。』 その後の方針についても、事前に伝えておくといいでしょう。
#91.
まとめ やはり、てんかん診療は判断に悩むことはもちろんあるわけで、専門家でなければ難しい判断もあります。 一方で、この診療領域は、専門家だけのものではなく、ジェネラリストにもやってほしいとも思っています。医療が専門家だけのもの、という発想は適切ではありません。シンプルな介入可能症例から、てんかんについてできることを検討してみて下さい。このプレゼンテーションでは、ジェネラリストが介入可能な症例についての考え方・薬剤使用について説明いたしました。
#92.