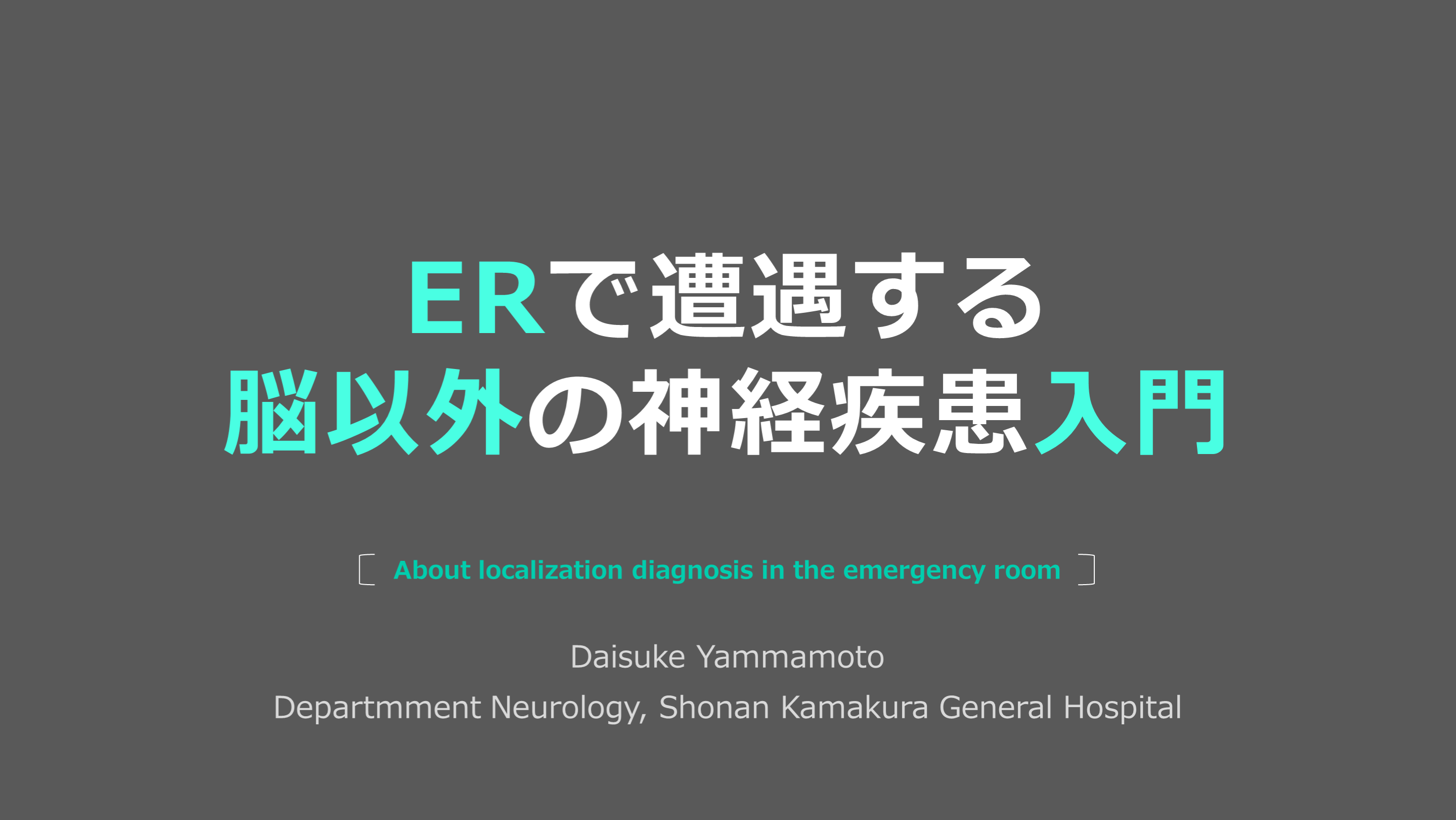1/31
関連するスライド
違法薬物使用を疑ったら
バヤシ@救急集中治療
31100
111
使いながら覚える実践的せん妄治療薬
山本大介
854480
1570
症例で学ぶ神経診療の基本:パーキンソン病じゃない!
山本大介
21005
83
プライマリケア医と患者さんむけ、いまのところのレカネマブ(レケンビ®)を知る。
山本大介
47998
96
ERで遭遇する脳以外の神経疾患入門
山本大介
Award 2024 受賞者
医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院
92,911
296
概要
脳についての評価は、脳卒中で比較的なじみはあるものです。しかしながら、脳以外の他の神経局在を認める神経疾患(脊髄・末梢神経など)については理解を深めることに難しさはあります。ERでの神経局在診断のレベルを上げるための入門スライドです。
【書籍:みんなの脳神経内科】https://www.amazon.co.jp/dp/4498328736
本スライドの対象者
研修医/専攻医
投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!
0 件のコメント
山本大介さんの他の投稿スライド
片頭痛診療、はじめの一歩。
山本大介
274,661
626
ミニマム!運動障害の患者さんに出会ったら
山本大介
151,890
290
Common diseaseである脳卒中後てんかんを学ぶ。
山本大介
124,069
347
このスライドと同じ診療科のスライド
テキスト全文
ERで遭遇する神経疾患の概要
#1.
Daisuke Yammamoto Departmment Neurology, Shonan Kamakura General Hospital About localization diagnosis in the emergency room ERで遭遇する 脳以外の神経疾患入門
#2.
Introduction ERでは脳卒中に触れる機会が多いので、脳障害についての経験多いでしょう。 一方、その他の障害局在を認める神経疾患に遭遇する頻度は そこまで高くないので、理解を深める機会は少ないです。 このスライドでは、ERで遭遇しうる大脳障害以外の神経系疾患 (脊髄障害・末梢神経障害・運動ニューロン病・神経筋接合部疾患・筋疾患) の鑑別について解説します。
運動感覚障害と純粋運動障害の評価
#3.
障害局在を 考えるルール 運動感覚障害パターン なのか? 純粋運動障害パターン なのか? パターンから障害局在を推定する
#4.
運動障害+感覚障害 なのか? 純粋運動障害 なのか? 障害局在の評価において、重要なルールを示します。 『脊髄障害・末梢神経障害の場合は原則、運動障害+感覚障害である。 神経筋接合部疾患・運動ニューロン病・筋疾患の場合は純粋運動障害である。』 このルールをもとに、運動+感覚障害なのか?純粋運動障害なのか?を 導入で確認すると障害局在が探りやすいです。
脊髄障害の重要性と鑑別疾患
#5.
脊髄障害 脊髄障害は重大疾患が多く、判断は重要である 血管障害、外傷性疾患、炎症性疾患など 多様な原因がある
#6.
脊髄障害のヒントと、まず覚える3疾患 KEY WORDS:運動感覚障害、膀胱直腸障害、バビンスキー反射 脊髄障害の場合は、先述のルール通り、運動感覚障害になる。 これに、膀胱直腸障害を合併していれば、より脊髄障害を肯定する所見である。 また脊髄障害を疑う場合には、バビンスキー反射を積極的に評価する。 ERで検討される急性の脊髄障害の理解のため、具体的には 脊髄梗塞(虚血性障害)、脊髄硬膜外血種(血管障害)、脊髄炎(炎症性疾患) の三つの疾患をイメージする。
脊髄梗塞の診断とMRI所見
#7.
背景にある血管障害リスクの高さは診断のヒントとする。また、発症様式は重要。脊髄梗塞は突発発症で、発症後数時間は進行する。疼痛(背部痛)発症であることも多い。下位胸髄が好発病変。脊髄MRIではT2強調画像に加え、拡散強調画像も評価する。また、発症ごく早期では撮像タイミングによって必ずしも画像所見は得られるとは限らない、という知識は重要である。 脊髄梗塞 突発発症の脊髄障害で想起されるべき疾患 血管障害リスク、突発発症+その後の進行、疼痛発症
#8.
脊髄梗塞 MRI T2WI T2WI T2WI T1WI a: T2WIで長大な高信号病変。Pencil like と表現される。 c: T2WIで、snake eyesと呼ばれる脊髄前角の高信号病変。 Neuroradiology 2002;44:851-857
#9.
発症様式は突発発症である。また、発症時疼痛(頸部痛・背部痛)を伴うことが多い。症状や経過は脊髄梗塞に類似し、脊髄梗塞のミミックになりうる。脊髄MRIで評価する。指摘されれば手術適応の検討のため、速やかに脊髄外科へのコンサルテーションをする。 脊髄梗塞では抗血栓療法も検討されるが、脊髄硬膜外血腫は出血性病態であり治療が真逆になるので、ここに鑑別としての重要性がある 脊髄硬膜外血腫 突発発症の脊髄障害で想起すべき、脊髄梗塞のミミック疾患
脊髄硬膜外血腫と脊髄炎の鑑別
#10.
脊髄 硬膜外血腫 MRI 非外傷性の脊髄硬膜外血腫。突発発症の両側上肢脱力を呈した。 C4-T4までの血腫による脊髄圧迫あり。 Spinal Cord Series and Cases 2017;3:16043 T2WI
#11.
発症様式は亜急性~急性経過である。脊髄炎の原因疾患としては、 自己免疫性脊髄炎、感染性脊髄炎を想起する。 自己免疫性脊髄炎を呈する疾患は多岐に渡るが、頻度の高いものとして、 多発性硬化症、視神経脊髄炎をまずは考慮する。 髄液検査では、細胞数増多を認めることが、他の脊髄障害との鑑別に重要である。 脊髄炎 内科疾患で、ERを受診する脊髄障害
末梢神経障害:ギランバレー症候群
#12.
視神経脊髄炎 MRI 最後野病変 (arrowhead)+脊髄長大病炎がNMOに典型的。 b,c) 脊髄中央に病変があるのもNMOらしさ。 RadioGraphics 2018;38:169-193 T2WI T2WI T2WI T1WI
#13.
末梢神経障害 代表疾患はギランバレー症候群 有名疾患だが、診断しようとすると難しい
#14.
「急性経過で悪化する末梢神経疾患」を想定する場合には、ギランバレー症候群を鑑別に挙げる。ギランバレー症候群は運動障害優位が典型的だが、感覚障害も合併していることが多く、先述のルールに準じて運動感覚障害パターンになる。 ギランバレー症候群を、自信をもって診断することはERでは難しい。なぜなら、ギランバレー症候群は画像検査や採血検査、髄液検査を施行しても、その傍証を得ることはできないからである。故に転換性障害(ヒステリー)が鑑別になりうる疾患でもある。 ギランバレー症候群① ERを受診する、急性経過で進行する末梢神経障害
#15.
ギランバレー症候群の評価においては、ERのテーマは以下の2つである。 重大疾患であり四肢脱力という類似する症候を呈しうる脊髄障害の除外を必ず行うこと 悩むなら脳神経内科へのコンサルトを行うこと また、ギランバレー症候群重症例でのⅡ型呼吸不全症例の存在にも留意しておく。 ギランバレー症候群② ERでの考え方について・・・脊髄障害の除外の必要
神経筋接合部疾患:重症筋無力症
#16.
神経筋接合部疾患 代表疾患は重症筋無力症 画像検査をしても採血検査をしても異常が指摘できず underな評価になりやすい疾患
#17.
「原因不明のⅡ型呼吸不全」の原因疾患として、重症筋無力症(Myasthenia Gravis: MG)を想起する。 また、MG患者が急性増悪し、クリーゼ状態で搬送される可能性もある。呼吸不全は来院後、ラッシュに増悪する可能性がある。呼吸不全の急性増悪リスクを念頭におきながら介入する必要がある。患者背景も考慮される必要はあるが免疫療法によって治療可能な疾患であるので、挿管・人工呼吸器管理については積極的に検討してよい。 複視、眼瞼下垂の併存が診断のキーワードとなる。 重症筋無力症 謎のⅡ型呼吸不全 でいつも想起する。 急速進行の呼吸不全に注意。
運動ニューロン病:ALSの理解
#18.
運動ニューロン病 運動ニューロン病の中の代表疾患ALS 未診断のALSが呼吸不全で受診すると本当に悩む
#19.
「原因不明のⅡ型呼吸不全」の原因疾患として、筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis: ALS)を想起する必要がある。 ALSの未診断例が肺炎などを理由に呼吸不全でERを受診することがある。前駆する数か月経過で進行する歩行障害や呼吸苦をキーワードに想起される疾患である。 筋萎縮所見や、舌萎縮、腱反射の亢進、バビンスキー反射も評価に加える。 運動ニューロン病:ALS 謎のⅡ型呼吸不全 で想起する疾患 前駆する症状経過の確認を。
筋疾患:筋強直性ジストロフィーの知識
#20.
筋疾患 未診断の遺伝性筋疾患症例が ERを受診する確率は高くはない。 しかしながら頻度の高い遺伝性筋疾患として 筋強直性ジストロフィーについては 知識を得ておく必要はある。
#21.
軽症例もあり、未診断例をみる可能性がある。成人診療で出会う遺伝性筋疾患としては最も頻度が高い。常染色体優性遺伝であり家族歴も確認する。 嚥下障害による誤嚥性肺炎、呼吸筋障害によるⅡ型呼吸不全で遭遇しうる。 心臓伝導障害(洞不全症候群・徐脈)も来し得る。慢性経過の病歴を確認すること。 キーワードは、筋萎縮、禿頭、斧様顔貌、把握ミオトニア(ものをつかんだら手を開けなくなる)、CK上昇。 筋強直性ジストロフィー 頻度の高い遺伝性筋疾患は知っておく。 多様な臓器障害の可能性。
検査方法と鑑別のポイント
#22.
検査 脊髄MRI、髄液検査、血液ガス分析における検査のヒント
#23.
脊髄MRI どの部位を撮像すればいい? 検査オーダーにおける重要なルールとしては、 「臨床症状で想定される脊髄障害レベルよりも、実際の脊髄障害レベルはより高位となる。」がある。 両下肢脱力を呈している場合には腰髄レベルの障害を想定するものの、実際の脊髄障害部位は、それより高位であればどこでもありうる、というものである。つまり、障害レベルは頚髄~胸髄~腰髄障害のいずれでもありうる。よって、どの部位の脊髄MRIを撮像するかは悩ましい。少なくとも、上記ルールは心得ておき、診察所見で想定されるレベルのみの画像評価では不十分である可能性を留意しておくこと。
#24.
髄液検査 脊髄障害では重要。 GBSでは所見がないかも。 脊髄障害を想定する場合には必ず施行する。脊髄炎の評価に役立つ。 髄液細胞数増多があれば、脊髄炎(炎症性疾患) は肯定的であり、 脊髄梗塞(血管障害性疾患)は否定的といえる。 ギランバレー症候群では検査タイミングにもよるが、蛋白細胞解離が得られるとは限らず、ERではその結果は診断に役立たない可能性にも留意しておく。
#25.
血液ガス分析 謎の呼吸不全で神経筋疾患を想起。 PaCO2貯留からⅡ型呼吸不全を、そして ギランバレー症候群、MG、ALS、筋強直性ジストロフィーなど 呼吸筋麻痺を来す疾患を想起できるようにする。
#26.
鑑別のポイント ここまでの知識の整理と共に 障害局在の特徴をまとめる
#27.
障害局在ごとの 特徴のまとめ やはり、入り口で運動感覚障害か、純粋運動障害かを理解すると、鑑別が進めやすい。 それぞれの障害局在ごとの特徴に当てはめながら、検討することになる。
#28.
pitfall 最後にこの領域のピットフォールについて
#29.
脊髄疾患:頚髄障害は多様な神経症状を呈しうるので、神経所見がセオリー通りでなくても否定しないことが重要である。頚髄障害は往々にして難しい。 末梢神経疾患:ギランバレー症候群が、転換性障害(ヒステリー)と区別できないことがままある。対応に悩んだら専門医へのコンサルトを。 神経筋接合部疾患:MGクリーゼの呼吸不全はラッシュに悪化することを忘れない。 運動ニューロン病:ALSは比較的頻度の高い疾患であることを留意しておくこと。 筋疾患:心筋障害による合併症(心不全、徐脈)がありうることにも注意。 pitfall
#30.