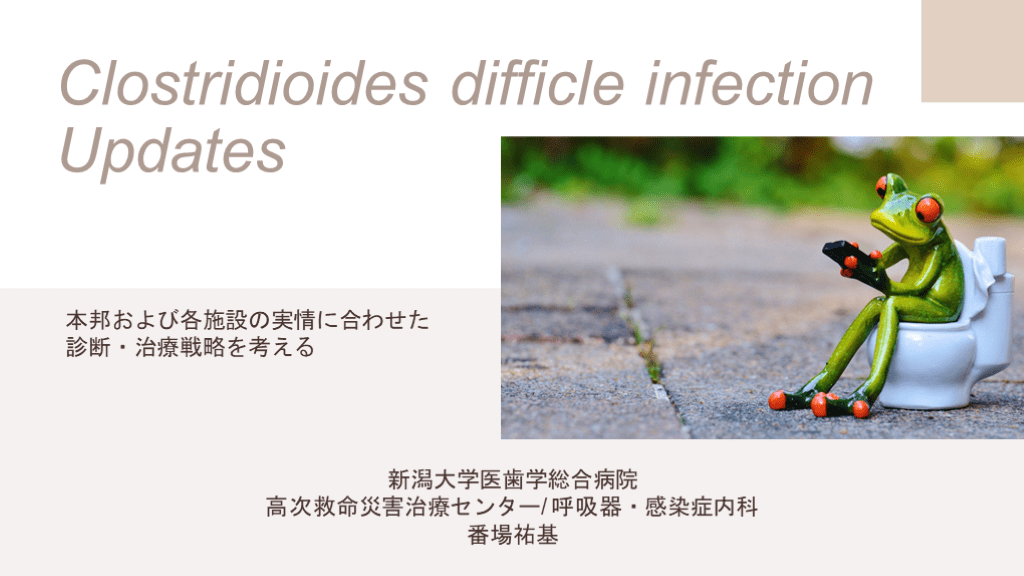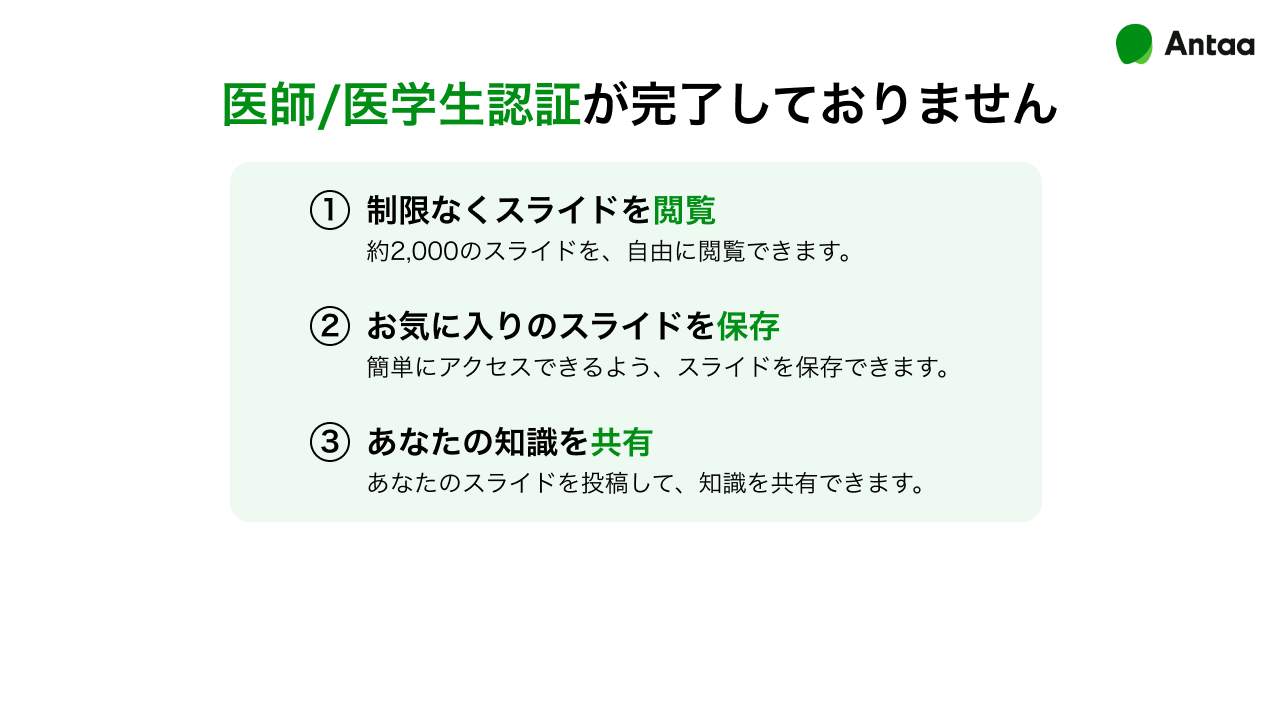このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/53
関連するスライド
2023.5.13改訂 細菌マニュアル ver.8
新米ID
424965
1409
CDI overview
長谷川耕平
133668
334
感染症科医が喜ぶクリスマスプレゼント
高野哲史
12784
18
尿路感染症
森本将矢
153097
402
C. difficile感染症 Updates
番場祐基
Award 2023 受賞者
新潟大学医歯学総合病院
121,652
423
番場祐基さんの他の投稿スライド
摂食障害 Refeeding症候群の管理と急性期からのシームレスなケアについて考える
番場祐基
99,197
310
肺非結核性抗酸菌症 診断と治療のポイント(非専門家向け)
番場祐基
154,322
398
肺炎が良くならないときに考えること
番場祐基
114,387
584
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。