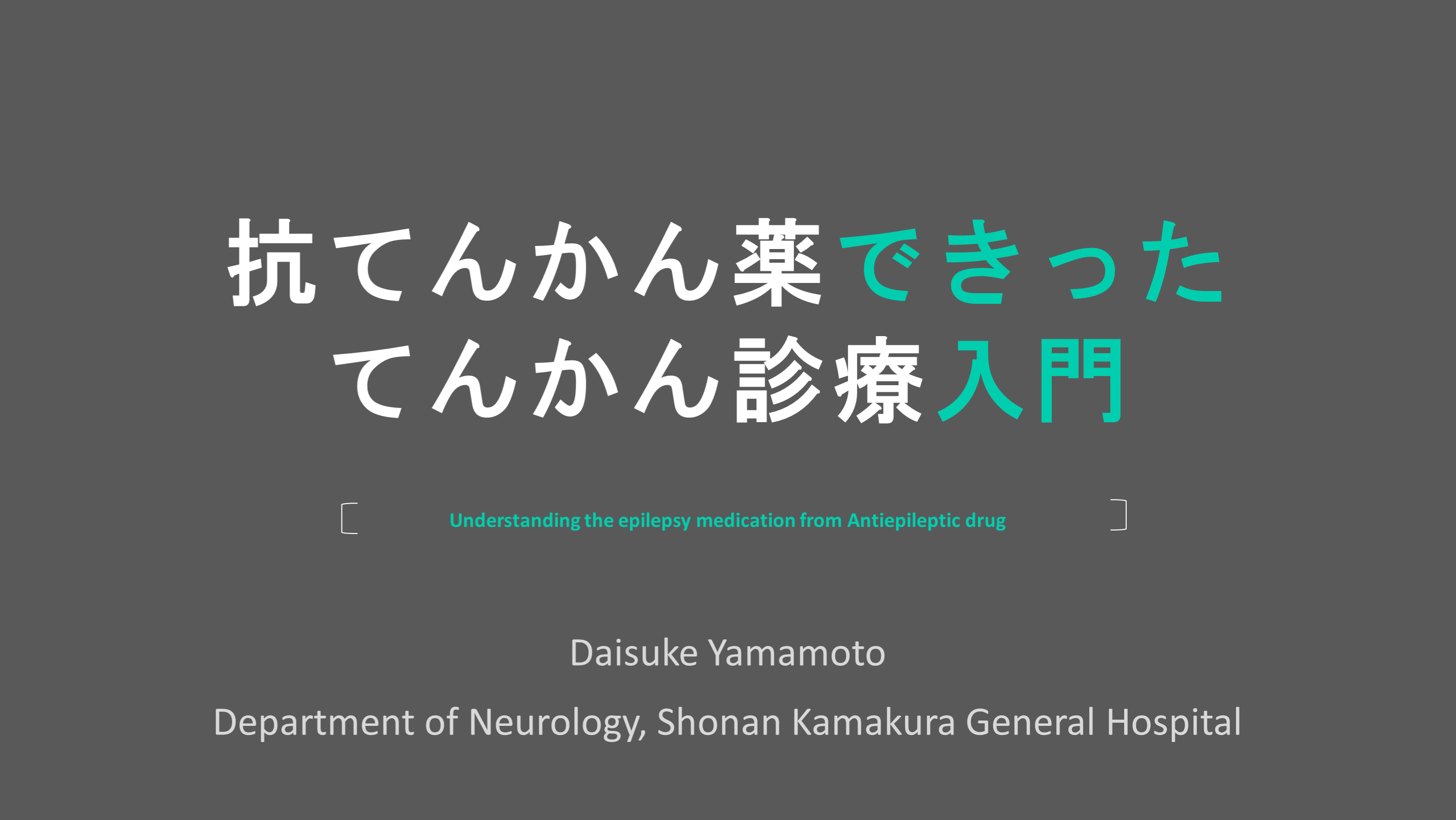1/42
関連するスライド
Drゆみの Weekly Journal Scan vol.13
医療法人社団ゆみの
3400
0
改訂!説明にそのまま使える 熱性発作(熱性けいれん)について ~対応と注意すべき疾患・てんかん症候群も含めて~
Osalepsy
342556
803
使いながら覚える実践的せん妄治療薬
山本大介
853353
1567
Drゆみの Weekly Journal Scan vol.9
医療法人社団ゆみの
2796
2
抗てんかん薬できったてんかん診療入門
山本大介
Award 2024 受賞者
医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院
573,081
560
概要
抗てんかん薬の使い方、薬剤の使用イメージについて、平易に学べるスライドです。
【書籍:みんなの脳神経内科】https://www.amazon.co.jp/dp/4498328736
本スライドの対象者
専攻医/専門医
投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!
0 件のコメント
山本大介さんの他の投稿スライド
片頭痛診療、はじめの一歩。
山本大介
274,308
625
ミニマム!運動障害の患者さんに出会ったら
山本大介
150,826
284
Common diseaseである脳卒中後てんかんを学ぶ。
山本大介
123,390
347
このスライドと同じ診療科のスライド
テキスト全文
抗てんかん薬の基本的理解と目的
#1.
Daisuke Yamamoto Department of Neurology, Shonan Kamakura General Hospital Understanding the epilepsy medication from Antiepileptic drug 抗てんかん薬できった てんかん診療入門
#2.
Introduction てんかん診療の見方としては、様々な切り口があると思います。ここでは、薬剤について理解をすることが、実際のてんかん診療をわかりやくするものであると考え、実際の投薬を通じたてんかん診療の理解、をスライドのテーマにしました。どのように抗てんかん薬を選択するのか、また、一般内科医、非専門医として使用しやすい、使用できる抗てんかん薬についても、ある程度学べるように記載しています。出会った患者さんの抗てんかん薬の内容をみて、「こういうニュアンスで、この処方になっているのかな?」と解釈できたりするくらいのレベルが、このスライドのゴールであります。また、非専門医がここまでは自分でやろう、という範囲を自分で決められる一助になればと思います。成人てんかんは比較的コモンな問題であり、いずれの臨床医としてある程度判断できることが、高齢社会においては求められるものとも思われます。
古典的抗てんかん薬の分類と特徴
#3.
古典的抗てんかん薬 から理解する 薬の基礎知識
#4.
てんかん分類は大きく分けて、焦点性てんかんと全般てんかんに分類されます。 焦点性てんかんとは、脳の特定部位から異常放電を来たし、てんかん発作に至る、てんかん分類です。 全般てんかんとは、脳全体に異常放電の発火を来たし、てんかん発作に至るてんかん分類です。 それぞれの発作抑制に、以下の(古典的)抗てんかん薬が使用されます。 焦点性てんかん カルバマゼピン 全般てんかん バルプロ酸 焦点性てんかん、 全般てんかん 二つの分類
カルバマゼピンとバルプロ酸の比較
#5.
カルバマゼピンは焦点性てんかんに有効です。イメージはnarrow spectrumの抗菌薬、とか研修医の先生には説明したりします。セファゾリンのイメージです。切れ味よく、ピンポイントで狙った投薬意図が両者薬剤の似ているイメージです。 一方、バルプロ酸は全般てんかんに有効です。イメージはbroad spectrumの抗菌薬です。ただし、パワフルさには欠けます。3世代経口セフェム、と例えて説明してみます。焦点性てんかんをこれで治療しようとするには無理があります。経口セフェムが、セファゾリン静注の代わりにはなりませんよね。そういうイメージです。 抗菌薬で例えてみると ①
#6.
抗てんかん薬の理解には、抗菌薬と同様にスペクトラムがある、という風に理解してください。 理屈的には、抗てんかん薬ごとに作用ポイントが異なり、作用ポイントが違う薬剤を使い分ける、というのがまずは理解していただきたい内容です。 抗菌薬同様、薬剤の特徴として、スペクトラムが狭い/広い、また、作用機序の異同を考慮して処方しています。 抗菌薬で例えてみると ②
#7.
基本的には、先述のカルバマゼピン、バルプロ酸については、プロ処方、として、捉えてもらっていいと思われます。その理由は、薬剤相互作用や、薬剤の副作用によります。 後述しますが、新規抗てんかん薬は、薬剤副作用が少なく、使用しやすい薬剤として捉えて下さい。プロ(専門医)でなければ、新規抗てんかん薬に馴染んでいくことを、まずは目標としてください。 古典的抗てんかん薬(従来薬)の新規投与について
新規抗てんかん薬の特徴と利点
#8.
新規抗てんかん薬 について
#9.
新規抗てんかん薬は、 使用しやすい薬剤である。 カルバマゼピン、バルプロ酸は過去からある薬剤で、「従来薬」として表現されます。ここでは古典的、と表現しました。近年登場した抗てんかん薬は、新規抗てんかん薬として位置づけられています。新規抗てんかん薬のイメージは、ブロードスペクトラムの抗てんかん薬と理解してよいです。先ほどの抗菌薬に例えるなら、カルバペネムをイメージしていただければと思います。また、新規抗てんかん薬の特徴としては、「副作用の少なさ」が挙げられます。ブロードスペクトラムで、副作用が少ない、となると、非専門医にとっては使用しやすい抗てんかん薬である、と理解されます。
#10.
非専門医で習熟するとしたら、 新規抗てんかん薬を学ぼう。 新規抗てんかん薬が使用できるようになってからは、古典的抗てんかん薬との使い分けができるようになり、それぞれのメリット・デメリットを勘案して処方するようになっています。非専門医にとっては、新規抗てんかん薬を使用できるようになる、というのが一つの目標であると考えます。副作用が少なく治療的効果が期待しやすい、というのが、非専門医にとっては重視されるポイントであると思われます。
成人てんかん診療における焦点性てんかん
#11.
成人てんかん診療 について
#12.
成人てんかん診療では、基本的には 焦点性(部分)てんかんを考える。 成人てんかんでは、基本的には焦点性てんかんを考慮します。高齢発症なら尚更、焦点性てんかんを考慮して診療を行っていけばよいです。加齢に伴って、様々な原因により脳のある部分に傷がついて、そこにてんかん原性が生じる訳です。成人が焦点性てんかんを来たす、ということはイメージしやすいでしょう。 成人てんかん診療においては、焦点性てんかんを想定し、治療においては焦点性てんかんに有効な抗てんかん薬を処方できればよいのです。
#13.
若年者のてんかん診断の場合には、 専門医への紹介が妥当だろう。 一方、全般てんかんについてですが、成人てんかん診療でも、全般てんかんをみる可能性があります。どのような場合かというと、10代から20代までの新規発症のてんかんの場合で考えられます。小児科でない、内科での診療においては、比較的若年者のてんかんの場合に、全般てんかんの可能性があります。この場合には、焦点性てんかんでない可能性がありますので、専門医への紹介を行い、抗てんかん薬の選定をしてもらうのが妥当だと思います。
新規抗てんかん薬の使用法と注意点
#14.
抗てんかん薬の特徴と 使い方について
#15.
ブロードスペクトラムの 新規抗てんかん薬 →焦点性でも全般でもOK →副作用少ない →効果はオールマイティ →イーケプラ、ラミクタール
#16.
添付文書で示されている、一般的な使用量は1000mg/dayです。高齢者ではより少量(500mg/day)での投与も検討されます。イーケプラのメリット、デメリットは以下のようなものです。 メリット:薬剤相互作用が少ない。副作用が少ない。漸増の必要がなく、有効用量を最初から投与できる。つまり、急性期に使いやすい。点滴製剤がある。 デメリット:眠気が強く、使用継続できない症例がある。また、易怒性を誘発することがあり、使用できない症例がある。 イーケプラ(レベチラセタム) 新規抗てんかん薬で、使用しやすい抗てんかん薬の一つで、非専門医が習熟すべき、薬剤の一つと理解してください。
イーケプラとラミクタールの特性
#17.
イーケプラ ① 急性期使用に長じている。 圧倒的なメリットとしては、注射製剤もあり、かつ、最初からてんかん発作抑制に十分な有効用量を投与できる点にあります。よって、ERはじめ、急性期病院の現場での使い勝手のよさがあります。漸増が必要とされる薬剤との比較において、ここが強いメリットです。 一方、デメリットとしては眠気や易怒性の誘発は、少なからず経験します。継続使用できない症例があるので、これら副作用については十分理解しておく必要があります。副作用が問題になる場合には、他剤への変更を検討することになります。成人てんかんにおいて、非専門医にとっては第1選択にしてもよい薬剤であります。
#18.
イーケプラ ② オールマイティな特性。 イーケプラのよいところは、仮に、てんかん発作が焦点性てんかんであった場合にも、全般てんかんであっても有効である、という点です。本来なら、焦点性てんかんか全般てんかんか、きっちり診断がなされるのはもちろんそうあるべきなのですが、てんかん発作分類について診断に悩む場合にも、選択してよい薬剤でもあります。もちろん、このような場合で発作コントロールが悪い場合には、専門医へのコンサルテーションを行ってください。まとめると、イーケプラはすぐに効果が発揮できる、副作用の少ない薬剤で、使い勝手がよい薬剤です。
#19.
重症薬疹リスクを思うと、非専門医には使用しにくい薬剤かもしれません。薬疹は、皮疹出現後すぐに中止してもらうこと、再診をしていただくことを徹底してもらえば対応可能でありますが、それでもそのようなリスクがあるとなると、やや処方しにくいかもしれません、また、薬疹リスクを避けるために、添付文書に則った漸増をしなければならないこともデメリットではあります。漸増プロトコールでは、有効用量に到達するまでには、数週間を要します。このような性質から、急性期病院の入院加療から始める薬剤としては、すぐにてんかん抑制をしたい、というニーズには応えにくい薬剤です。てんかん抑制について待てない患者には、不適である薬剤です。 ラミクタール(ラモトリギン) 焦点性てんかん・全般てんかん双方に有効な抗てんかん薬です。副作用としては、重症薬疹のリスクがあり、その点についての注意が必要です。
#20.
ラミクタール オールマイティな特性。 メリット :眠気が少なく、高齢者でも使いやすい。 デメリット:投薬開始後、十分な用量まで増量できるまでに数週間を要するため、 急性期での現場ニーズにはこたえにくい。 また、重症薬疹の可能性がありうる。 てんかん発作で急性期病院に入院してきた場合には、第一選択薬としては選びにくい薬剤であると思います。ただし、眠気の少なさ、焦点性てんかん・全般てんかん双方への有効性など、重視すべきメリットがある薬剤です。
ビムパットの効果と使用方法
#21.
ナロースペクトラムの 新規抗てんかん薬 →焦点性てんかん用 →副作用少ない →成人てんかんではこれで →ビムパット
#22.
メリット :部分てんかんについて、有効性が高い薬剤である。 デメリット:高価。心筋伝導障害の可能性もある。 焦点性てんかんでは使いやすく、効果も期待しやすいです。有効性はカルバマゼピンのイメージで副作用が少ない薬剤、としての理解でもいいと思います。 成人てんかん診療では、基本的に焦点性てんかんが対応できればよい、という考えからは、ビムパットは成人てんかん診療では使用の妥当性があります。 ビムパット(ラコサミド) 焦点性てんかんに有効な新規抗てんかん薬です。副作用もあまり目立たず、非専門医でも使用しやすい薬剤の一つです。
#23.
ビムパット 眠気少なく、効果もよい。 200mg/dayが維持量であり、まずは200mg/dayまで増量し、経過をみることになります。1週間での有効用量までの増量が可能であり、イーケプラ同様、急性期病院で使用しやすい薬剤です。眠気が問題になりにくい薬剤でもあり、第1選択薬で眠気が問題になり、継続できない症例については、変更薬剤の選択肢になると思います。高齢者でも比較的使いやすい薬剤という印象です。副作用の心筋電導障害の報告は稀です。ただし、AVブロックなど、もともと知られている場合には注意した方がいいのかもしれません。あまり弱点がなく、焦点性てんかんでは頼りになる薬剤です。
エクセグランと古典的薬剤の比較
#24.
ブロードスペクトラムの 新規てんかん薬 →焦点性も全般も →比較的使いやすい →他の新規抗てんかん薬の 代用的存在 →エクセグラン
#25.
メリット :比較的広い治療スペクトラム デメリット:尿管結石のリスク 尿管結石の副作用については、知っておく必要があります。新規抗てんかん薬の位置付けですが、他の新規抗てんかん薬よりも安価です。 金銭的問題で、イーケプラ・ラミクタール・ビムパットが使えない時の変更薬剤の選択肢として、一つ覚えておくといいと思います。 エクセグラン(ゾニサミド) 焦点性てんかんで使用する選択肢になりうる薬剤です。眠気など問題になりにくく、選択肢の一つとして知っておいてもいい薬剤です。
#26.
ナロースペクトラムの 古典的てんかん薬 →焦点性てんかん用 →副作用気になる →効果は期待できる →カルバマゼピン
抗てんかん薬の処方例と考慮点
#27.
メリット :焦点性てんかんへの高い有効性。安価である。 デメリット:高齢者での使用しにくさ(眠気、薬物相互作用、低Na血症を誘発) 新規抗てんかん薬に比べて安価であるので、薬価が問題になる場合には、焦点性てんかんでの積極的選択薬になり得ます。投与開始の際には、眠気やふらつきなどが問題になるので、少量からの開始が必要です。100mg/dayからの開始がいいと思います。金銭的な問題がクリアできるなら、高齢者では使いにくいため、避けてもいいかもしれません。いずれにせよ、過去から現在においても、焦点性てんかんでの中核的な役割を果たす薬剤であることには変わりはありません。 テグレトール(カルバマゼピン) 焦点性てんかんで使用する中核的な薬剤です。ただし、薬物相互作用の点、薬疹、低Na血症の原因になりうるなど使いにくい点があります。
#28.
ブロードスペクトラムの 古典的てんかん薬 →全般てんかん用 →副作用は許容できる →成人での使い方は特別 →バルプロ酸
#29.
例えば、眠気が問題になり、テグレトールなどが使用できない場合が一つです。焦点性てんかんをデパケンでコントロールしようとする場合には、比較的高用量を要することも知っておいてください。また、mood stabilizerとしての副次的な効果も期待して処方することもあります。バルプロ酸が処方されている人は、怒りっぽい人なのかな?と解釈もできます。 メリット :副作用が少ない。眠気が少ないので使いやすい。 デメリット:焦点性てんかんについてのてんかん抑制は効果不十分な可能性がある。 一番知っておくべき内容は、バルプロ酸で焦点性てんかんを抑制しようとするには無理がある、ということです。大腸菌の尿路感染症を、第三世代経口セフェムで治療とするにはやや、無理がある、というイメージです。 デパケン(バルプロ酸) 全般てんかんの第一選択薬です。成人の焦点性てんかんで使う場合には、特別な条件の場合に限られます。
#30.
抗てんかん薬の 処方例
ケーススタディと処方の実際
#31.
抗てんかん薬の選択において、考慮されるポイントを示します。これがすべてではありませんが、比較的majorな内容を記載します。 ▲薬剤相互作用を気にする場合。 ▲怒りっぽい症状が既に知られている。 ▲第一選択薬で眠気が問題になった。 ▲薬価が問題になる。 高齢者のてんかんてんかんの場合を例に、実際の処方例について記載してみます。ケースは、アルツハイマー型認知症の診断が既についている高齢患者とします。臨床的にけいれん発作のエピソードが2度あり、てんかんの診断に至っています。抗てんかん薬をどのように選択していくか?という状況をイメージしてください。
#32.
古典的抗てんかん薬は、薬剤相互作用があります。併存症のため多剤内服しており、薬物同士の相互作用が気になる、という場合には、新規抗てんかん薬を選択します。イーケプラ、ラミクタール、ビムパットが選択肢になります。 例えば、古典的抗てんかん薬では、ワーファリンとの相互作用があり、ワーファリンの用量調整を要したりします。 薬剤相互作用を気にする場合。
#33.
認知症の周辺症状、また元々のキャラクターで、怒りっぽい症状がある場合にはイーケプラは避けます。易怒性を助長する可能性があるからです。この場合は、新規抗てんかん薬では、ビムパット、ラミクタールが選択肢になります。古典的な抗てんかん薬では、テグレトール、バルプロ酸が選択肢になります。Mood stabilizarとしての効果を持つ、テグレトール、バルプロ酸は違った意図で双方選択肢になり得ます。両者は認知症周辺症状としての易怒性に対して使用することもある薬剤です。 怒りっぽい症状が既に知られている。
#34.
この場合には、眠気が問題になりやすい、イーケプラ、テグレトールは避ける事になります。 この場合には、眠気が少ない、ビムパット、ラミクタール、バルプロ酸が選択肢になります。 第一選択薬で眠気が問題になった。
#35.
薬価が問題になる場合には、新規抗てんかん薬は不適切であり、テグレトール、バルプロ酸が選択肢になります。新規抗てんかん薬ではありますが、エクセグランも選択肢にしてもいいと思います。 このような特徴を加味して、抗てんかん薬は選択しています。出会った患者の抗てんかん薬について、どのような理由で処方されているのか、是非解釈してみて下さい。 薬価が問題になる。
#36.
ケーススタディ
#37.
イーケプラ1000mg/dayで治療介入した。発作再然なく自宅退院となった。 退院後外来で、家族から易怒性について指摘をされた。イーケプラの副作用と考えて、イーケプラは中止することにした。 代わりに、ビムパットを選択した。ビムパット200mg/dayに変更、イーケプラは漸減中止し、その後ビムパット単剤でてんかんなく経過している。 ケース1 5年前に脳梗塞を発症している70歳男性。けいれん発作を来たし、入院に至った。けいれんの誘因となる明らかなエピソードなく、けいれん発作前はいつも通りであった。初回発作ではあるが、脳梗塞発症後に比較的時間経過のある発作であり、再発リスクが高いと判断し、入院中から抗てんかん薬を導入することにした。
#38.
イーケプラ1000mg/dayで治療介入した。発作再然なく自宅退院となった。 退院後外来で、家族から易怒性について指摘をされた。イーケプラの副作用と考えて、イーケプラは中止することにした。 代わりに、ビムパットを選択した。ビムパット200mg/dayに変更、イーケプラは漸減中止し、その後ビムパット単剤でてんかんなく経過している。 ケース1 5年前に脳梗塞を発症している70歳男性。けいれん発作を来たし、入院に至った。けいれんの誘因となる明らかなエピソードなく、けいれんてんかん前はいつも通りであった。初回てんかんではあるが、脳梗塞発症後に比較的時間経過のあるてんかんであり、再発リスクが高いと判断し、入院中から抗てんかん薬を導入することにした。 高齢者てんかんの新規導入薬としては使いやすいので、イーケプラ。 イーケプラは易怒性の 誘発がある。 同じく、新規抗てんかん薬の選択肢、ビムパットに変更。
#39.
ケース2 85歳の高齢男性。もともとアルツハイマー型認知症あり、施設入所中。 けいれん発作を発症し、発作後意識障害が遷延するため入院になった。 今回の発作は2度目であり、発作を繰り返すため 抗てんかん薬を導入してから退院することにした。 高齢でもあり眠気を考慮して、減量し、イーケプラ500mg/dayで処方開始した。投薬開始後、眠気の訴えが強く傾眠傾向が認められた。イーケプラ使用継続は断念した。 イーケプラから、ビムパット200mg/dayに変更し、特に問題なく退院となった。退院後、薬価について家人から相談あり。薬剤変更によるてんかん再然リスクなど説明した上で、抗てんかん薬を変更することにした。 眠気も問題になっていたことから、バルプロ酸400mg/dayを選択した。てんかん再然があるなら、バルプロ酸を増量、もしくは他の抗てんかん薬に変更する方針とした。
#40.
ケース2 85歳の高齢男性。もともとアルツハイマー型認知症あり、施設入所中。 けいれんを発症し、てんかん後意識障害が遷延するため入院になった。 今回のてんかんは2度目であり、発作を繰り返すため 抗てんかん薬を導入してから退院することにした。 高齢でもあり眠気を考慮して、減量し、イーケプラ500mg/dayで処方開始した。投薬開始後、眠気の訴えが強く傾眠傾向が認められた。イーケプラ使用継続は断念した。 イーケプラから、ビムパット200mg/dayに変更し、特に問題なく退院となった。退院後、薬価について家人から相談あり。薬剤変更によるてんかん再然リスクなど説明した上で、抗てんかん薬を変更することにした。 眠気も問題になっていたことから、バルプロ酸400mg/dayを選択した。てんかん再然があるなら、バルプロ酸を増量、もしくは他の抗てんかん薬に変更する方針とした。 高齢者てんかんの新規導入薬としては使いやすいので、イーケプラ。 ビムパットは眠気少なく使いやすい。 ただし、 新規は高価である。 安価なので古典的薬剤に。バルプロ酸は使いやすいが、効果が不安である。
#41.