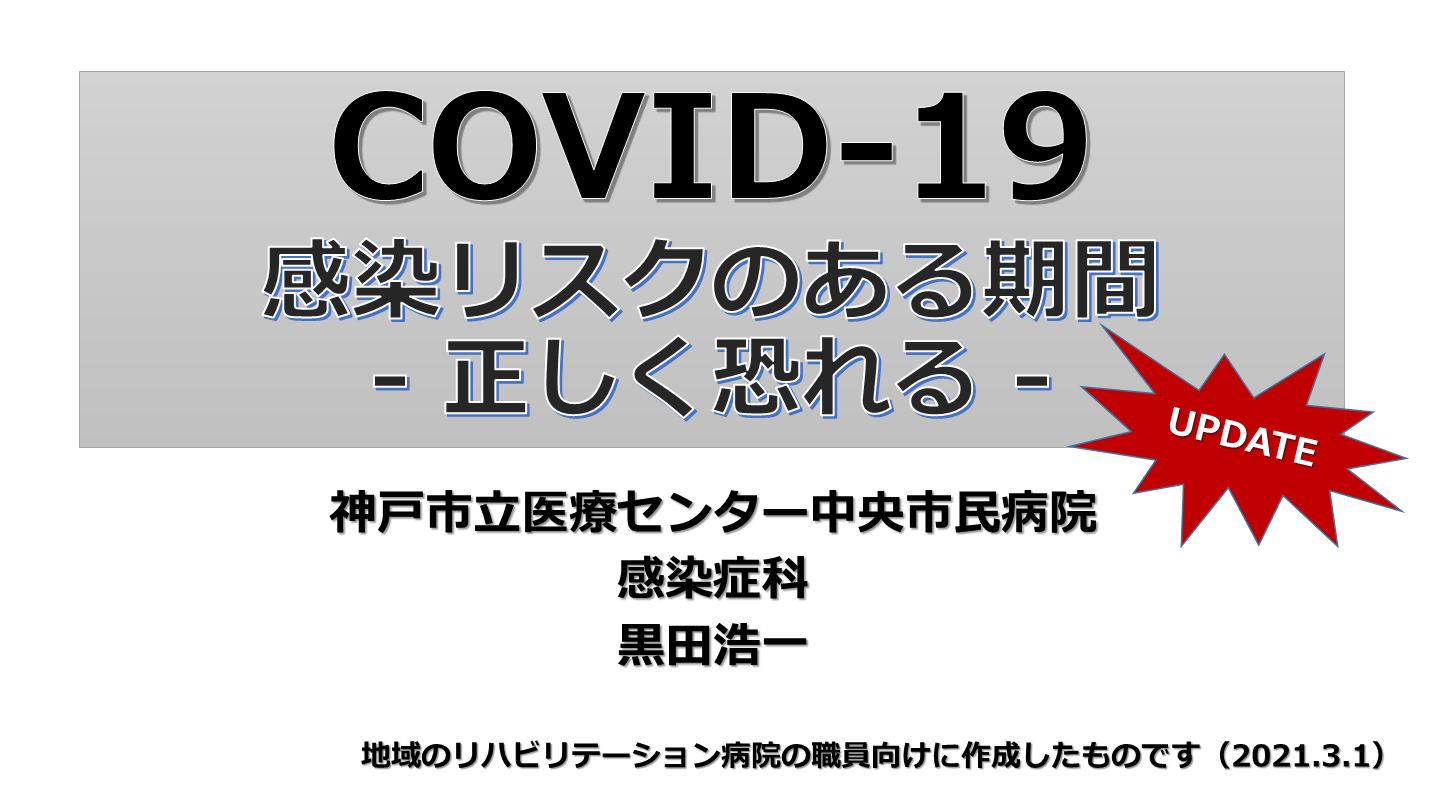1/43
関連するスライド
医療従事者のためのCOVID-19検査まとめ
山田悠史
802530
111
【J-SSCG2024準拠】敗血症診療のまとめ
三谷雄己
4975861
4786
回復期病棟におけるCOVID-19感染対策(2020年9月版)
黒田浩一
574764
94
コロナ禍で変わっていく地域の状況に対して、プライマリ・ケア医は何をしてきたのか?
春田淳志
4423
11
COVID-19の感染伝播リスクと隔離解除 update(2021.3)
63,597
40
概要
COVID-19の感染伝播リスクがいつまで存在して、感染対策終了・隔離解除はいつ可能となるか、これまで報告されてきたevidenceと日本の行政上のルールを解説した上で、私の所属機関の方針を紹介しています。2021年3月作成です。Antaaユーザー以外でも全ページ閲覧可能です。
本スライドの対象者
研修医/専攻医/専門医
投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!
0 件のコメント
黒田浩一さんの他の投稿スライド
市中肺炎診療の考え方 ウィズコロナ時代
黒田浩一
563,171
398
免疫抑制・化学療法によるB型肝炎ウイルス再活性化への対策
黒田浩一
35,385
282
COVID-19治療 アップデート 2023年9月版
黒田浩一
1,088,689
1,015
このスライドと同じ診療科のスライド
テキスト全文
COVID-19感染リスクの評価方法と研究
#1.
COVID-19感染リスクのある期間- 正しく恐れる - 神戸市立医療センター中央市民病院 感染症科 黒田浩一 UPDATE 地域のリハビリテーション病院の職員向けに作成したものです(2021.3.1)
#2.
感染伝播する期間
#3.
「感染性がある」ことの評価方法は? PCR陽性→× ウイルス培養陽性→? 実際に起こったoutbreakの調査結果
ウイルス培養陽性の期間と症例の検討
#4.
これまでの主な研究ウイルス培養がいつまで陽性か調査したものが多い
#5.
軽症から重症のCOVID-19患者12例の検討 ・発症から9日目でウイルス培養陽性の症例があった ・10日目以降のウイルス培養は検討されていない ・気管挿管例は含まれていない Nat Med. 2020 Apr 23. doi: 10.1038/s41591-020-0877-5
#6.
軽症COVID-19(9例の検討)発症8日目までの喀痰ウイルス培養陽性 便のウイルス培養は全例陰性(PCRのウイルス量に関連なし) Nature. 2020 Apr 1. doi: 10.1038/s41586-020-2196-x.
#7.
米国のSkilled Nursing Facilityで起こったoutbreak。重症例も含めたCOVID-19の上気道検体を使用したPCRとウイルス培養を施行。SARS-CoV-2は、発症6日前から発症9日目で培養陽性となった。ウイルス量(PCR)が多い場合に培養陽性となる傾向があるようにみえるが、発症早期にウイルス量が多いことが原因と思われる。 N Engl J Med. 2020 Apr 24. doi: 10.1056/NEJMoa2008457.
#8.
発症前(潜伏期間):45% 発症後:40% 環境接触:10% 無症状感染者:5% 感染伝播:感染(曝露)から10-12日頃まで Science. 2020 May 8;368(6491). doi: 10.1126/science.abb6936.
#9.
COVID-19のヒト-ヒト感染77ペアを解析した研究。感染伝播は、発症2.3日前から出現し、発症前後でpeakとなり、その後発症7日目までに急速に減少する。感染伝播の44%は発症前に起こる(pre-symptomatic transmission)。 Nat Med. 2020 Apr 15. doi: 10.1038/s41591-020-0869-5.
#10.
主に軽症から中等症のCOVID-19患者の上気道検体のウイルス培養は、発症から10日まで陽性となりうる。無症状者も有症状者も同様の結果であった。 Euro Surveill. 2020;25(32):pii=2001483. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483
重症COVID-19患者のウイルス培養結果
#11.
重症または最重症のCOVID-19患者の上気道検体のウイルス培養は、発症から20日まで陽性となりうる。発症から15日を超えて陽性となる可能性は5%以下であった。 Nat Commun. 2021 Jan 11;12(1):267.
#12.
成人COVID-19患者(重症度や年齢・基礎疾患などの詳細なdataは提示されていない)の鼻咽頭または気管内検体のウイルス培養で、発症から8日以降は陽性例なし。Ct値>24でも陽性例はなかった。 Clin Infect Dis. 2020 May 22;ciaa638. doi: 10.1093/cid/ciaa638.
#13.
100名の患者からの感染伝播を調査した台湾の報告。Secondary caseは、index case発症から初回曝露までの期間が5日以下までの症例のみだった。感染率が高いのは、発症前曝露(pre-symptomatic transmission)、家庭内曝露、重症例/最重症例。無症状感染者からの感染(asymptomatic transmission)はなかった。 JAMA Intern Med. 2020 May 1. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.2020. presymptomatic transmissionは発症4日前から起こりうる
#14.
Clinical Infectious Diseases, ciaa1249 https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1249
#15.
例外は存在する:高度免疫不全者 造血幹細胞移植後とCAR-T細胞療法の患者で発症から20日を越えてウイルス培養が陽性となった報告がある 3例報告されており、発症から25日、26日、61日目でのウイルス培養が陽性であった 高度免疫不全者には、マスク着用と手洗いを特に指導する必要がある、かつ、PCRで2回陰性化確認? N Engl J Med. 2020 Dec 1. doi: 10.1056/NEJMc2031670
感染伝播のメカニズムとリスク要因
#16.
例外は存在する:高度免疫不全者 慢性リンパ性白血病よる高度免疫不全の既往のある無症状のCOVID-19患者で、発症70日目の鼻咽頭ぬぐい液のウイルス培養が陽性になった報告がある CD4リンパ球が0のHIV患者のCOVID-19で、発症95日目の鼻咽頭ぬぐい液のウイルス培養が陽性になった報告がある Cell. 2020 Dec 23;183(7):1901-1912.e9. J Infect Dis. 2021 Feb 8;jiab075. doi: 10.1093/infdis/jiab075.
#17.
RT-PCRのCt値と感染性の関係 診断における一般的なCt値のカットオフ値は<40 Ct値が低いほどウイルス培養陽性率が高い Ct > 30-35でウイルス培養は陰性と予測できる Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020 Jun;39(6):1059-1061. Clin Infect Dis. 2020 Aug 25;ciaa1249. doi: 10.1093/cid/ciaa1249. Emerg Infect Dis. 2020 Jul;26(7):e201595. doi: 10.3201/eid2607.201595 Clin Infect Dis. 2020 Oct 24;ciaa1579. doi: 10.1093/cid/ciaa1579. Ct=Threshold Cycle
#18.
Ct値はRT-PCR検査の結果報告に記載すべき?Ans. routineに行うことは推奨されない 同じウイルス量でも、Ct値は検査系によって異なる(cobasとXpertのCt=20のウイルス量copy/testは異なる) Ct値は、検体採取のqualityに左右される Ct値によって、感染性の有無を評価する十分なevidenceはまだない J Clin Microbiol. 2020 Oct 21;58(11):e01695-20. doi: 10.1128/JCM.01695-20.
#19.
感染伝播する期間:文献のまとめ 発症2-4日前から発症後5-10日目までがリスクが高い - 院内感染のリスクが高い感染症である それ以降に感染伝播が起こる可能性は非常に低い → 発症から11日目以降の感染リスクはほぼない 最重症例(人工呼吸器管理)は20日間までリスクあり 高度免疫不全例の場合は、稀だがさらに長期リスクあるかも?
再感染と再燃の事例とその影響
#20.
例外的な状況
#21.
PCR検査は再度陽性になることがあるが感染伝播した例は報告されていない 2回PCR陰性確認された4名のCOVID-19患者で、5-13日後にPCRが再度陽性化した SARS-CoV-2 PCR検査2回陰性確認後退院となった患者の14.5%で再度陽性化した 韓国CDCは、COVID-19の症状が改善し、いったんPCR陰性化した患者で、再度陽性になった285名(約40%が有症状)の追跡したところ、1例も感染伝播を起こさなかった(ウイルス培養も陰性) Clin Infect Dis. 2020 Apr 8;ciaa398. doi: 10.1093/cid/ciaa398. JAMA. 2020 Feb 27;323(15):1502-1503. https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=367267&nPage=1external%20icon
#22.
非常に稀に再燃例は存在する B細胞リンパ腫に対する化学療法中のCOVID-19患者で、おそらく3回再燃した報告がある。発症119日目の鼻咽頭ぬぐい液のウイルス培養が陽性(RT-PCRでCt=21)となった1)。 重症の抗リン脂質抗体症候群に対する治療中(ステロイド、シクロフォスファミド、リツキシマブ、エクリズマブ)のCOVID-19患者で、3回再燃した報告がある。発症143日目に採取された鼻咽頭ぬぐい液のウイルス培養が陽性だった2)。 心臓移植後のCOVID-19患者で、症状再燃時の発症103日目の鼻咽頭ぬぐい液のウイルス培養が陽性となった3)。 1) Clin Infect Dis 2021;223:23-27. 2) N Engl J Med. 2020;383(23):2291-2293. 3) J Infect Dis. 2021 Feb 8;jiab075. doi: 10.1093/infdis/jiab075.
#23.
再感染の報告もある(稀) インドの2名の医療従事者 1)→2回とも無症状(スクリーニング検査) - 1回目の治癒確認から3-5か月後に再感染が判明 既往のない33歳男性 2)→初回:軽症、2回目:無症状 - 1回目の治癒確認から4ヶ月後に再感染が判明 喘息の既往のある51歳女性 3)→初回はSpO2 94%、2回目はより軽症 - 1回目発症から3ヶ月後に2回目を発症 上記の患者は、ゲノム配列の解析で、「再感染」と診断された 1) Clin Infect Dis. 2020 Sep 23;ciaa1451. doi: 10.1093/cid/ciaa1451. 2) Clin Infect Dis. 2020 Aug 25;ciaa1275. doi: 10.1093/cid/ciaa1275. 3) Clin Infect Dis. 2020 Sep 5;ciaa1330. doi: 10.1093/cid/ciaa1330.
#24.
再感染が軽症とは限らない 米国の既往のない25歳男性: 初回軽症、2回目重症(呼吸不全あり) Lancet Infect Dis. 2020 Oct 12;S1473-3099(20)30764-7.
#25.
COVID-19治癒後の患者へのPCR再検は原則不要 治癒後長期間(例えば3か月)経過した場合に再感染1) 高度免疫不全の場合に再燃2) する可能性はあるので個別に検討を CDC sebsite:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html J Infect Dis. 2021 Feb 8;jiab075. doi: 10.1093/infdis/jiab075. 治癒した患者に対する、転院前・転院後PCRは不要
退院基準の変更と感染対策のガイドライン
#26.
退院基準感染対策終了基準
#27.
これまでの退院基準(日本) 2020年6月12日に「発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合」に変更 退院の適応を決定するにあたって、原則PCR検査は行わないことになった この基準は、重症度を考慮していない
#28.
退院基準の変更(日本) 2021年2月25日に重症度に関わらず一律であった退院基準が、「人工呼吸器非使用例」と「人工呼吸器使用例」に分けられた。前者はこれまでと同様。後者は、「発症から15日間経過」に変更。また、「発症から20日間経過するまでは、退院後も適切な感染予防策を講じるものとする」と付記されている。
#29.
英国由来の変異株が増加:これまでの株よりも感染伝播しやすい
#30.
退院基準の変更(日本) 英国由来などの変異株の場合 症状軽快後24時間経過した後に、PCR検査を行い、陰性が確認され、その検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された(PCRを2回連続で陰性確認)場合に退院(隔離解除)可能
院内感染対策の基準と国際的な指針
#31.
院内感染対策終了の基準(米国) 軽症・中等症の場合(呼吸不全なし) 発症から10日以上、かつ、解熱24時間、かつ、症状改善 重症・最重症の場合(呼吸不全あり) 高度免疫不全の場合 発症から10-20日以上、かつ、解熱24時間、かつ、症状改善 ※高度免疫不全患者では、PCR検査を専門家と相談 ※退院基準ではない
#32.
院内感染対策終了の基準(WHO) 重症度に関係なく 発症から10日以上、かつ、症状消失後72時間 発症から13日以上、かつ、症状消失後72時間 Clinical management of COVID-19:interim guidance, 27 May 2020 https://apps.who.int/iris/handle/10665/332196 Clinical management of COVID-19:living guidance, 25 January 2021 変更後...
#33.
院内感染対策終了の基準(欧州) 軽症・中等症 発症から10日以上経過、かつ 解熱後72時間以上、かつ、その他の症状改善 重症・免疫不全 発症から14-20日以上(免疫不全は20日)経過、かつ 解熱後72時間以上、かつ、その他の症状改善 ※24時間間隔で採取したPCR 2回連続陰性確認でもよい Guidance for discharge and ending of isolation of people with COVID-19(2020.10.16) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation
#34.
神戸市立医療センター中央市民病院の場合 院内感染対策終了基準 →転院「可」の判断にも使用
神戸市立医療センターの感染対策基準
#35.
神戸市立医療センター中央市民病院 軽症から中等症の場合(SpO2 94%以上) 発症から10日以上経過 かつ 解熱から72時間以上経過 かつ 呼吸器症状改善
#36.
神戸市立医療センター中央市民病院 重症の場合(酸素投与必要で、HFNCまたはNIVの使用なし) 発症から14日以上経過 かつ 解熱から72時間以上経過 かつ 呼吸器症状改善
#37.
神戸市立医療センター中央市民病院 重症の場合(HFNCまたはNIVまたは人工呼吸器使用例) 発症から20日以上経過 かつ 解熱から72時間以上経過 かつ 呼吸器症状改善
#38.
神戸市立医療センター中央市民病院 高度免疫不全者(すべての重症度)の場合 発症から20日以上経過 かつ 解熱から72時間以上経過 かつ 呼吸器症状改善 造血幹細胞移植後・固形臓器移植後・血液悪性腫瘍の化学療法中など 感染症科の判断で、PCR 2回陰性(24時間以上の間隔)確認を行うことがある
#39.
神戸市立医療センター中央市民病院 重症の場合で、発症21日目の時点で酸素投与が必要な場合 発症21日目の時点からPCR検査の陰性化確認を開始する PCR検査の陰性結果がでた場合は、24時間後に再検する PCR検査2回連続陰性を確認できれば隔離解除とする 人工呼吸器管理が必要な患者の場合、発症から20日以内に呼吸状態が十分改善(酸素投与不要)になることは稀であり、呼吸状態の改善よりPCR陰性化のほうが早いことが多い(軽症から中等症の場合は、通常PCR陰性化より呼吸状態の改善のほうが早い)。 重症例でPCR検査をする目的は、隔離期間を最短にして、①ベッドの回転を速くすることによって多くの重症患者を受け入れる、②「隔離」という人権の制限を最短にする、③リハビリを行いやすい一般病棟に早く移動する(特に、嚥下リハはレッドゾーンでは行っていない)、ためである。
COVID-19回復後の転院と安全性について
#40.
まとめ:転院前に確認すること 呼吸不全なし→発症から10日以上 呼吸不全あり→発症から14-20日以上 高度免疫不全→発症から20日以上 高度免疫不全の場合は、PCR陰性化確認を考慮する
#41.
COVID-19回復後の患者の転院は再燃・再感染は非常に稀なのでむしろ「安全」です 最後に一言...
#42.