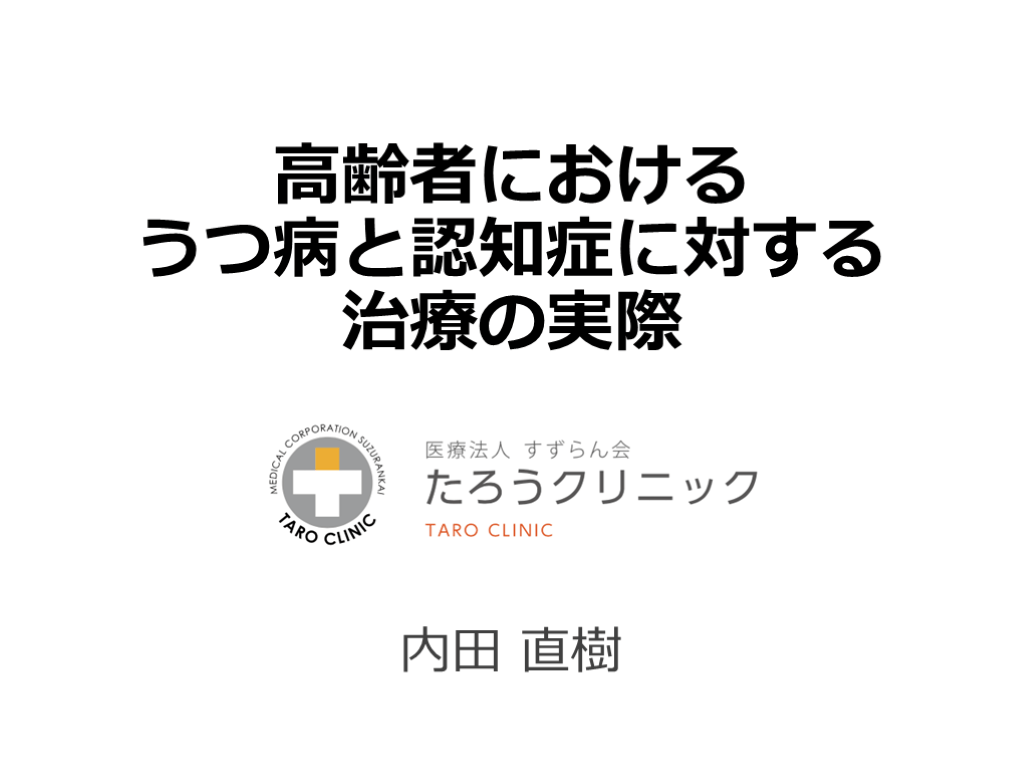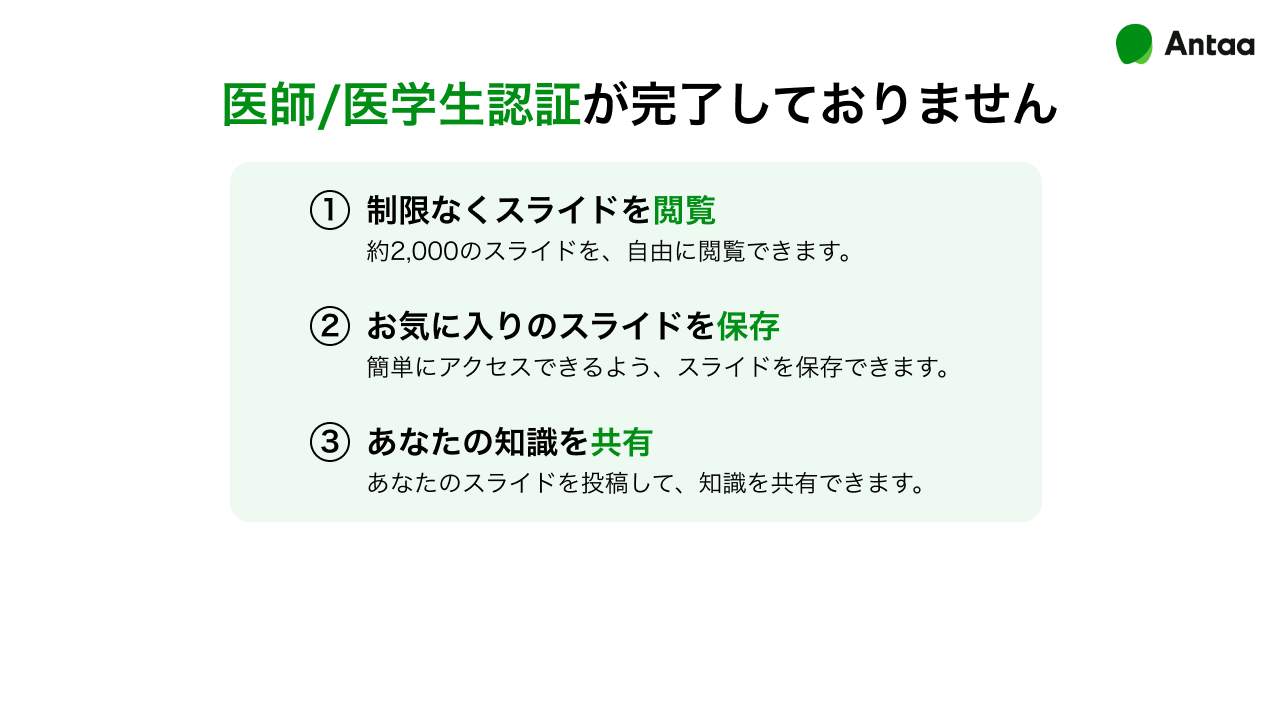このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/72
関連するスライド
ポリファーマシー ~そんなに薬飲んで大丈夫?~
masa1019@救急科、内科
11985
63
Drゆみの Weekly Journal Scan vol.23
医療法人社団ゆみの
1635
1
高齢者におけるうつ病と認知症に対する治療の実際
内田直樹
Award 2023 受賞者
医療法人すずらん会たろうクリニック
57,862
161
内田直樹さんの他の投稿スライド
すべて見るこのスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。