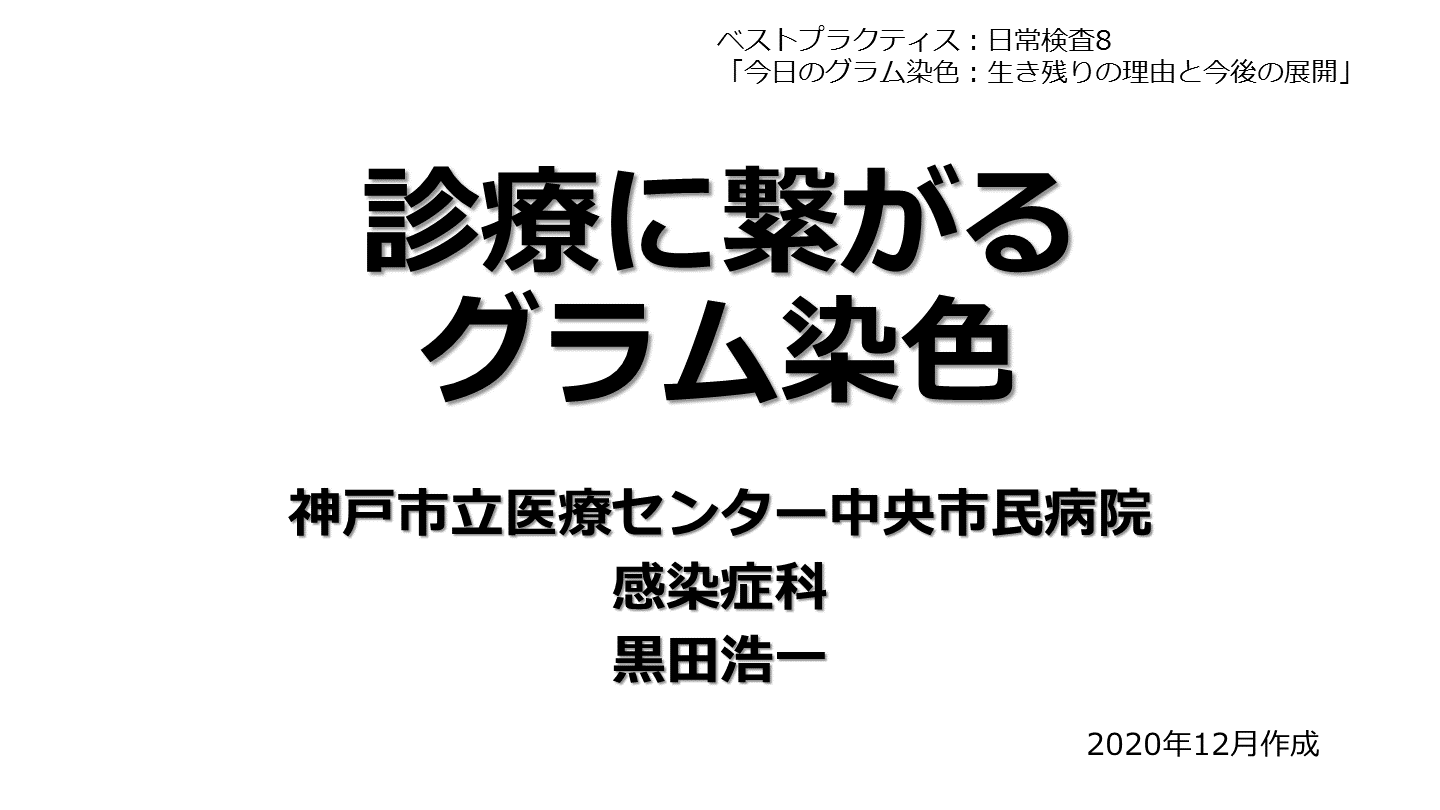1/83
関連するスライド
その他の抗菌薬 -フルオロキノロン,テトラサイクリン,マクロライド-
高野哲史
22546
82
黄色ブドウ球菌菌血症の考え方
長谷川耕平
598926
593
グラム陽性桿菌 オーバービュー
わかやま
5383
16
腸球菌感染症とその周辺
長谷川耕平
37905
68
診療に繋がるグラム染色
251,575
279
概要
2021年に開催された第32回日本臨床微生物学会学術集会でお話した内容です。診療でどのようにグラム染色を活かすか、というお話しです。あまりevidence-basedではないかもしれません。2020年12月に作成しました。Antaaユーザー以外も全ページが閲覧可能です。
本スライドの対象者
研修医/専攻医
投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!
0 件のコメント
黒田浩一さんの他の投稿スライド
市中肺炎診療の考え方 ウィズコロナ時代
黒田浩一
560,386
398
免疫抑制・化学療法によるB型肝炎ウイルス再活性化への対策
黒田浩一
35,269
281
COVID-19治療 アップデート 2023年9月版
黒田浩一
1,088,383
1,013
このスライドと同じ診療科のスライド
テキスト全文
グラム染色の基本と重要性
#1.
診療に繋がるグラム染色 神戸市立医療センター中央市民病院 感染症科 黒田浩一 ベストプラクティス:日常検査8 「今日のグラム染色:生き残りの理由と今後の展開」 2020年12月作成
#2.
COI開示発表者:黒田浩一 発表に関連し開示すべきCOI関係 にある企業などはありません
#3.
グラム染色 安価・簡便・迅速に施行可能な、細菌の染色性・形態・配列を評価する微生物学的検査である 臨床経過と組み合わせることによって、感染巣と原因微生物の推定・同定に有用であり、経験的治療の選択で重要な役割を果たす
グラム染色の分類と有用な感染症
#4.
グラム染色によって4種類に分類される
#5.
グラム染色が有用な感染症 肺炎(喀痰) 尿路感染症(尿) 細菌性髄膜炎(髄液) 化膿性関節炎(関節液) 膿胸(胸水) 膿瘍・壊死性筋膜炎(膿) 細菌性腸炎(便) など
#6.
グラム染色は菌の推定に有用 臨床情報(経過、身体所見、検査)とともに解釈する 推定することによって経験的治療の選択に役立つ 菌の推定以外に... - 検体の質の評価ができる - 検査室での培地の選択に有用な情報となることがある
鏡検時の注目ポイントと血液培養
#7.
鏡検時の注目ポイント 菌(色、形態) 好中球 貪食像:実際はあまり参考にしていない 溶血(血液培養)
#8.
血液・痰・尿
#9.
血液培養での菌の推定
#10.
血液培養陽性例のグラム染色 血流感染症の原因微生物の推定に有用 さらに...感染巣の再検討にも有用
グラム陽性球菌の推定と鑑別
#11.
グラム陽性球菌
#12.
血液培養:グラム陽性球菌の場合 MSSA Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis
#13.
GPC cluster:S. aureus vs CNS? MRSA S. epidermidis
#14.
BacT/ALERT®システム ・oozing sign:cluster を形成するグラム陽性球菌周囲のピンク色の滲み(S. aureusに特徴的) ・four-leaf clover sign:好気ボトルの培養液のグラム染色で,4 つのグラム陽性球菌がcluster を形成している所見がみえる(CNSに特徴的) GPC cluster:S. aureus vs CNS?
#15.
GPC chain 連鎖の程度・球菌の形態 背景の赤血球の溶血 臨床経過から推定されるfocus
#16.
見た目から菌名と感染巣を推定
#17.
溶血の有無:GPC chainの場合に有用β溶血性レンサ球菌の場合に観察される
#18.
グラム染色の背景の溶血の有無 Streptococcus pyogenes Streptococcus salivarius
#19.
感染focusからGPC chainを推定
#20.
腸球菌の鑑別:落花生サイン感度78-94%、特異度78-96%(感染症誌. 2019;93:306‒11) E. faecium:落花生サイン陽性 E. faecalis:落花生サイン陰性
グラム陰性桿菌の特性と検査
#21.
グラム陰性桿菌
#22.
血液培養:グラム陰性桿菌の場合 腸内細菌科細菌:太いGNR ブドウ糖非発酵菌:細いGNR GNR:Gram-Negative Rods グラム陰性桿菌 (主に緑膿菌)
#23.
腸内細菌科細菌とは? Escherichia coli Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca Proteus mirabilis, P. vulgaris Enterobacter cloacae, E. aerogenes Serratia marcescens Citrobacter freundii, C. koseri Morganella morganii, Salmonella spp., Yersinia spp. etc
#24.
グラム陰性桿菌 血液培養:緑膿菌(通常好気培養のみ) 血液培養:E. coli
#25.
血液培養:感染巣の再検討にも有用 発熱と膿尿が指摘された高齢者を尿路感染症として治療していたが、血液培養からβ溶血性レンサ球菌が検出された場合、全身の詳細な診察によって、足の蜂窩織炎が見つかるかもしれない 高齢者の発熱で、膿尿・細菌尿があるため、尿路感染症として治療していたが、血液培養からStreptococcus gordoniiが検出され、感染性心内膜炎と診断されるかもしれない
#26.
喀痰グラム染色での菌の推定
#27.
市中肺炎患者の喀痰のグラム染色 「良質な喀痰」のグラム染色の診断精度 肺炎球菌またはインフルエンザ桿菌で - 感度約60-70% - 特異度90%以上 Med Sci Monit. 2008;14:CR171-6 Clin Infect Dis. 2004;39:165-9 Clin Infect Dis. 2000;31:869-74 BMC Infectious Diseases 2014;14:534
#28.
喀痰グラム染色の限界 1. 良質な検体が採取できる可能性が低い 2. 検体採取前の抗菌薬投与によって感度が著しく低下する 3. 染色者または評価者の技術レベルによって左右される
#29.
COVID-19流行期の注意点 喀痰検査を行う場合、十分な感染対策が必要(飛沫予防策、接触予防策、換気のできる個室での採取) グラム染色は、感染伝播のリスクがあるため、生物学的安全キャビネットの「外」(例えば、救急外来に設置されたグラム染色スペース)で、喀痰グラム染色を行ってはいけない
#30.
米国の最新のガイドラインでは 喀痰検査(グラム染色と培養)の適応 ①重症市中肺炎の場合(人工呼吸器 or shock) ②MRSAまたは緑膿菌を経験的治療の対象とする場合 ③MRSAまたは緑膿菌による感染症の既往 ④過去90日間に入院・点滴抗菌薬投与を受けた場合 - 外来管理の患者では行わないことを推奨する - 入院患者全員に一律に行うことについては言及なし Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(7):e45-e67.
喀痰検査の適応と限界
#31.
喀痰検査の適応(演者の意見) 入院が必要な市中肺炎 フルオロキノロンを使用する場合
#32.
グラム染色で推定できる細菌 肺炎球菌 インフルエンザ桿菌 Moraxella catarrhalis 腸内細菌科細菌(K. pneumoniaeなど) ブドウ糖非発酵菌(主に緑膿菌) 黄色ブドウ球菌 抗酸菌、Nocardia spp.
#33.
卵型またはランセット型と表現される楕円形の菌体が横長に2つ連なっている双球菌のパターンが典型的、莢膜のため、菌周囲が抜けて(不染の透明体)見える 鈴木啓之先生より頂きました 肺炎球菌
#34.
鈴木大介先生より頂きました 肺炎球菌
#35.
小桿菌、短桿菌 小さいのが特徴 インフルエンザ桿菌
#36.
早野聡先生から頂きました そら豆状のグラム陰性双球菌 Moraxella catarrhalis
#37.
Moraxella catarrhalis
#38.
西原悠二先生から頂きました 太いグラム陰性桿菌 莢膜が観察されることがある Klebsiella pneumoniae
#39.
39 口腔内常在菌も観察される Klebsiella pneumoniae
#40.
腸内細菌科に比べ細長くみえることが多い ムコイド産生する株がある 緑膿菌
抗酸菌の染色と鑑別法
#41.
41 黄色ブドウ球菌
#42.
clusterを形成する黄色ブドウ球菌(背景にインフルエンザ桿菌もみえる) 黄色ブドウ球菌
#43.
喀痰培養からMRSA検出の解釈 保菌?原因菌?
#44.
44 誤嚥性肺炎の患者の喀痰。グラム染色で少数のclusterを形成するブドウ球菌が検出され、培養でMRSAが検出されたが、カバーしない治療で治癒した。
#45.
45 ESBL産生E. coli肺炎をMEPMで治療中に、一過性酸素化低下(痰づまり) 熱源精査のための喀痰検査 培養MRSAのみ 呼吸状態・画像悪化なし 治療対象としなかった
#46.
西原悠二先生から頂きました Gram-ghost 抗酸菌
#47.
西原悠二先生から頂きました Ziehl-Neelsen染色 抗酸菌
#48.
西原悠二先生から頂きました 蛍光染色 抗酸菌
#49.
細長い分岐したフィラメント状のグラム陽性桿菌。ビーズ状に不均一に染まる。 Nocardia spp.
#50.
Kinyoun染色 Nocardia spp.
尿のグラム染色と細菌の推定
#51.
尿グラム染色での菌の推定
#52.
尿のグラム染色:GNR E. coli P. aeruginosa
#53.
よく聞くSPACE この覚え方ホントに役立つ??
#54.
SPACEとは? 院内感染で問題となる病原体で耐性化傾向が強い local factorを参考にして経験的治療を決定 - Serratia marcescens (腸内細菌科) - Pseudomonas aeruginosa(ブドウ糖非発酵菌) - Acinetobacter baumanii(ブドウ糖非発酵菌) - Citrobacter freundii(腸内細菌科) - Enterobacter cloacae/aerogenes(腸内細菌科)
#55.
「SPACE」と一括りにしているけれど
#56.
2つのグループが含まれている 腸内細菌科細菌とブドウ糖非発酵菌
#57.
そしてそれらはグラム染色で区別可能 であることが多い(難しいこともあります)
#58.
Acinetobacter spp.は形態が特徴的 血液培養 喀痰(院内肺炎)
#59.
グラム陰性桿菌の一般的な治療 腸内細菌科細菌 →セフトリアキソン ブドウ糖非発酵菌 →抗緑膿菌活性のある抗菌薬
#60.
CTRXのSPACEへの効果 Serratia marcescens (腸内細菌科) ○ Pseudomonas aeruginosa × Acinetobacter baumanii × Citrobacter freundii(腸内細菌科) ○ Enterobacter cloacae(腸内細菌科) △
腎盂腎炎の治療と抗菌薬選択
#61.
SPACEを疑うので治療を●●にします とはならない! そのため
#62.
カルバペネマーゼ産生菌 多剤耐性菌(カルバペネム・アミノグリコシド・フルオロキノロン耐性) 腸内細菌科細菌その1 :もともとCEZ or ABPCで治療可能 E. coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis 腸内細菌科細菌その2 :内因性AmpCβLあり→CTRX Serratia marcescens Citrobacter freundii Enterobacter cloacae ブドウ糖非発酵菌:Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumanii (Stenotrophomonas maltophilia) (Burkholderia cepacia) 市中感染 医療関連感染/抗菌薬曝露 ESBL産生菌 治療: カルバペネムが第1選択 セフメタゾール ピペラシリン/タゾバクタム△ AmpCβL過剰産生菌 特にEnterobacter spp. 治療: セフェピム、カルバペネムが第1選択 ピペラシリン/タゾバクタム 抗菌薬曝露 抗菌薬耐性機序 分類(3つのグループ)
#63.
GNRの初期治療の選択 耐性機序まで考慮した6群のどの群まで想定・カバーすべきか、右記の情報をもとに検討すると、初期治療が決まる 発症場所(市中・院内) 抗菌薬使用歴 過去の培養歴 重症度 患者の基礎疾患 など
#64.
選択する抗菌薬(耐性菌リスクなし) 各群で経験的治療が異なる 腸内細菌科細菌その1: セフォチアム or セフトリアキソン 腸内細菌科細菌その2: セフトリアキソン or セフェピム ブドウ糖非発酵菌: 抗緑膿菌活性のある抗菌薬 院内アンチバイオグラムも参考にします
#65.
腎盂腎炎の治療
#66.
太いGNR→腸内細菌科細菌? 単純性腎盂腎炎 :E. coliをカバーすればよい :E. coliの院内アンチバイオグラムを参考 ・おそらく多く病院では 第2世代セフェム、または 第3世代セフェムで治療可能
#67.
太いGNR→腸内細菌科細菌? 最近の抗菌薬使用 以前の培養でESBL産生菌やEnterobacterの検出歴 院内発症 複雑性腎盂腎炎 EnterobacterとCitrobacterなどを考慮、かつ、軽症 →セフトリアキソンが検討できるかもしれない ESBL産生菌を考慮 →メロペネム AmpC過剰産生Enterobacter spp.を考慮 →セフェピムまたはメロペネムまたはピペラシリン/タゾバクタム
#68.
細いGNR→緑膿菌? 単純性腎盂腎炎ではこのような状況はほとんどない 市中発症の尿管結石による閉塞性腎盂腎炎でもほとんどない 大半の緑膿菌による尿路感染症は 抗菌薬使用歴(繰り返す尿路感染症を含む) 院内発症(抗菌薬曝露歴が通常存在する) 膀胱留置カテーテル使用 が認められる J Infect 2012;64:478, Infect Control Hosp Epidemiol 2013;34(1):1 Clin Microbiol Infect 2012;18:E13, Infect Control Hosp Epidemiol 2012;33(10):993
#69.
細いGNR→緑膿菌? 治療を決めるにあたって、以下を確認する 最近使用した抗菌薬 以前の培養結果(菌種、感受性) 緑膿菌の院内アンチバイオグラム 実は腸内細菌科細菌であった場合に想定される耐性機序 を検討して、抗緑膿菌活性のある抗菌薬を選択 CAZ、CFPM、PIPC/TAZ MEPM(ESBL、AmpC過剰産生、重症) 尿路閉塞がある場合は、その解除が必要です →泌尿器科コンサルト
#70.
尿のグラム陽性球菌 GPC chainがみられることが多い 多くの場合GNRも観察される 多くの場合GNRの治療だけすればOK GPC chainの治療は不要なことが多い
検体の質評価と臨床への応用
#71.
尿のGPC chain Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Streptcoccus agalactiae Viridans Group Streptococcus
#72.
尿のGPC chain 尿のGPC chain(腸球菌)を治療する状況 - 血液培養で検出された場合 - GPC chainによる単一菌感染の場合 - 複雑性腎盂腎炎、かつ、グラム染色でGNRも見られるが、GPC chainがdominantな場合 - 重症の場合/shockの場合
#73.
尿のGPC cluster
#74.
検体の質の評価ができる 喀痰検査は、グラム染色による検体の質の評価が重要
#75.
Miller & Jonesの分類Gecklerの分類
#76.
Miller & Jonesの分類(喀痰の肉眼的評価)
#77.
Gecklerの分類(100倍での1視野あたり) J Clin Microbiol 1977;6:396-399 ※G6:気管支鏡検体、好中球減少状態では評価に値すると判断
#78.
Geckler 5
#79.
検査室での培地の選択に有用 臨床情報を踏まえて判断(医師からの情報、カルテからの情報) 重症市中肺炎で良質な痰であるがグラム染色陰性 →レジオネラ肺炎を考慮する(BCYEα培地) 糖尿病性足壊疽や褥瘡感染、膿瘍の手術検体で多菌種みえている →嫌気培養を追加(通常routineに施行される) 尿のグラム染色で菌体がみえるが、好気培養が陰性の場合 →嫌気培養を追加(抗菌薬の先行投与がない複雑性尿路感染症) 痰のグラム染色から放線菌 →ノカルジアを疑う(サブロー寒天培地、BCYEα培地など)
#80.
「なにも見えない」も重要な情報 市中肺炎 :Legionella pneumophila、Mycoplasma pneumoniae 抗酸菌 など 産婦人科領域の術後感染症 :Mycoplasma hominis
#81.
検査室での培地の選択に有用 臨床側と検査室側のdiscussionが重要 しかし、その重要性を認識して、微生物検査室とdiscussionする習慣のある医師は少ない →感染症内科医はこの点で検査室と臨床側をつなぐ役割を果たす必要がある
#82.