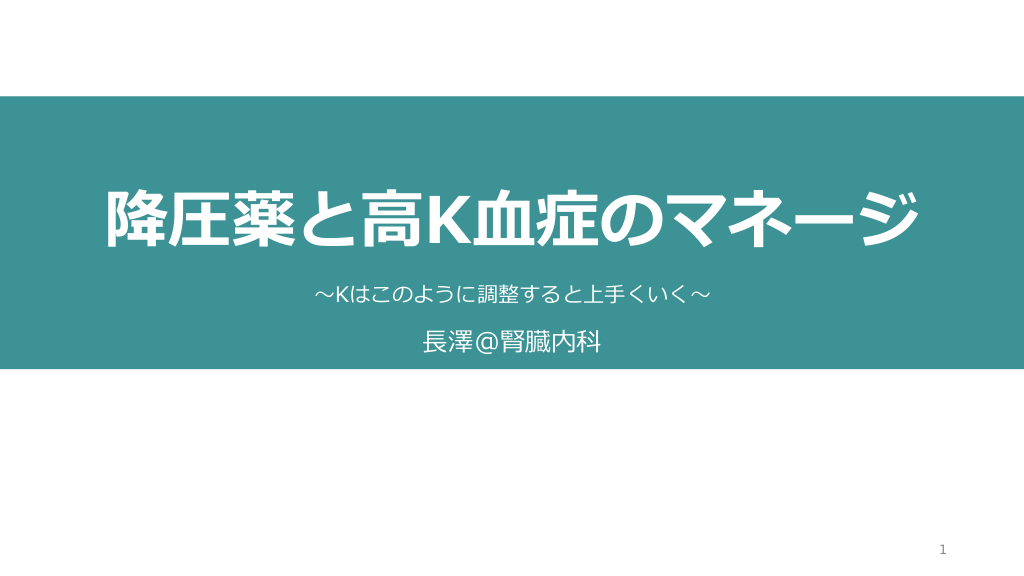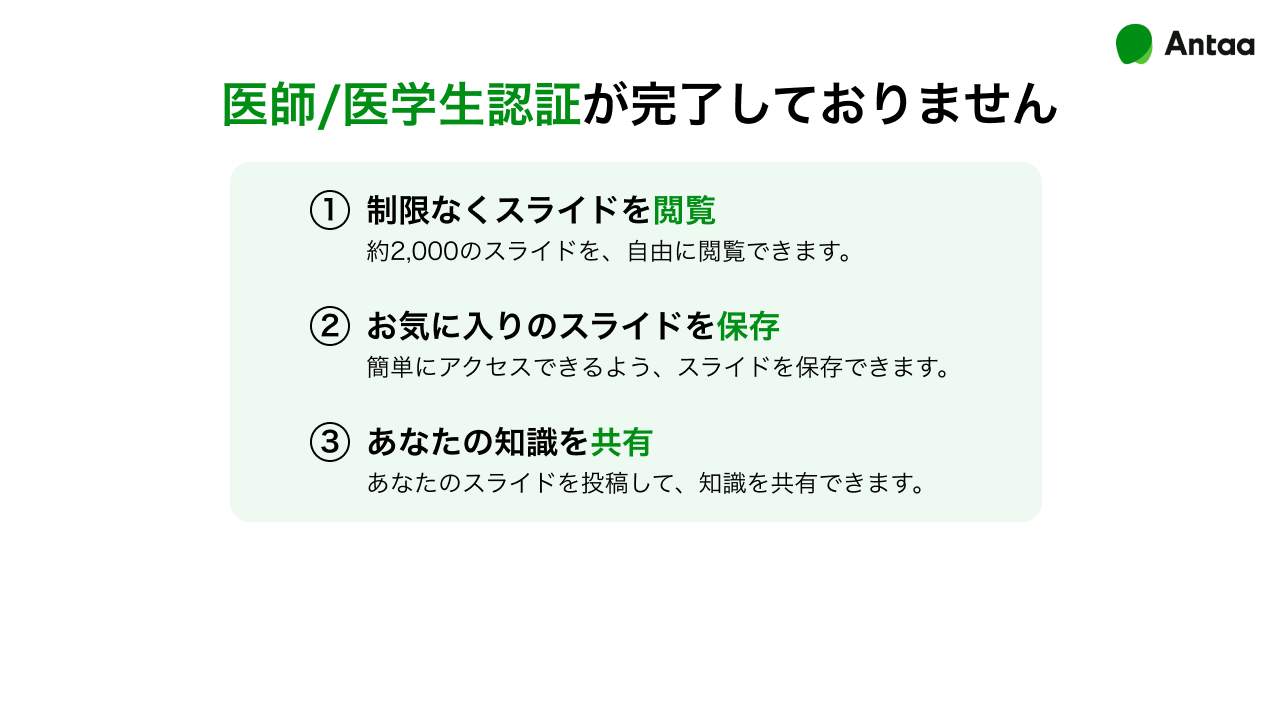このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/23
関連するスライド
高カリウム血症の治療
かんぱち
36996
163
高カリウム血症で日和るな 〜イベント回避のためのRAA系薬剤の使い方〜
長澤将
40657
300
腎臓が悪い患者に出会ったら
ねこすけ
17147
102
#3 K代謝異常 | 電解質輸液塾
門川俊明
367341
1160
降圧薬と高K血症のマネージ 〜Kはこのように調整すると上手くいく〜
102,031
787
長澤将さんの他の投稿スライド
薬剤性腎障害 〜頻用薬、造影剤、抗がん剤でおきる病態と早期発見について〜
長澤将
17,275
94
低カリウム血症〜腎臓から出ているかいないか?それが問題だ〜
長澤将
63,374
273
糖尿病性腎症の捉え方 〜臨床上大事なのはアルブミン尿の有無〜
長澤将
29,782
129
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。