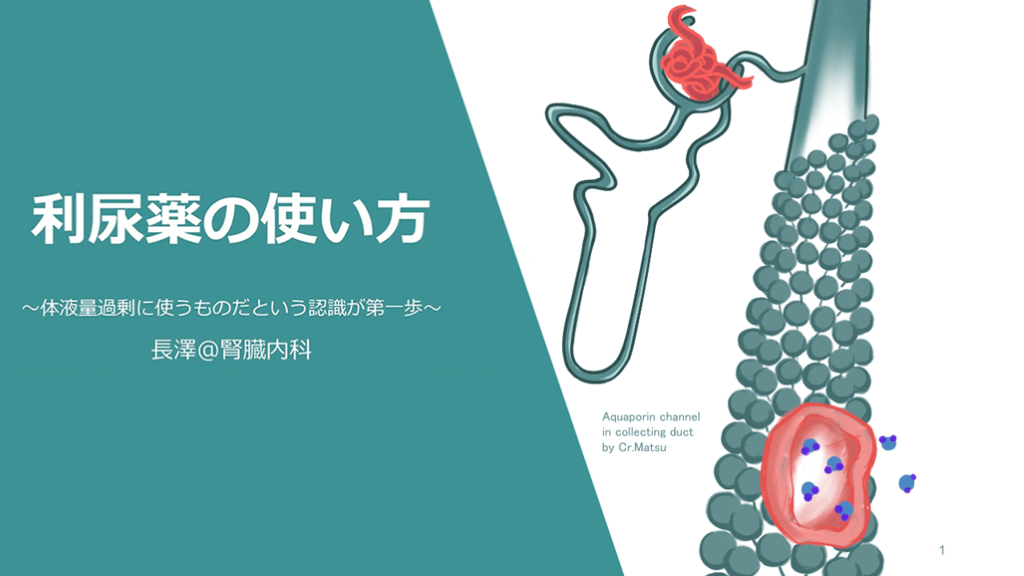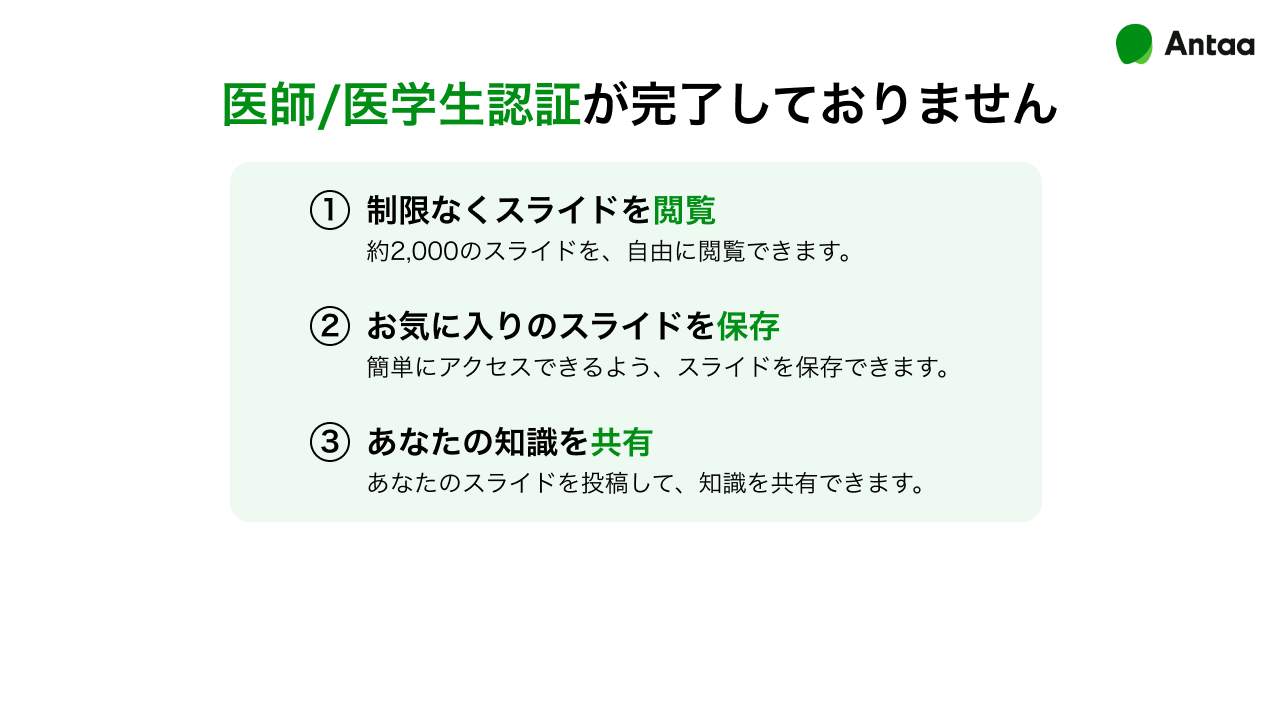このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/25
関連するスライド
利尿薬の使い方 〜フロセミドを中心に〜
ミント@腎臓内科
49249
388
低Na血症の診断と治療
ねこすけ
202656
623
慢性腎臓病(CKD)と抗菌薬・抗ウイルス薬の使い方
アイジュ@海外勤務医
60683
146
高K血症に出会ったら? =専門医へ送るタイミング=
さくら@漢方/腎臓内科
43855
210
利尿薬の使い方〜体液量過剰に使うものだという認識が第一歩〜
258,925
2,141
長澤将さんの他の投稿スライド
薬剤性腎障害 〜頻用薬、造影剤、抗がん剤でおきる病態と早期発見について〜
長澤将
17,255
94
降圧薬と高K血症のマネージ 〜Kはこのように調整すると上手くいく〜
長澤将
101,979
787
低カリウム血症〜腎臓から出ているかいないか?それが問題だ〜
長澤将
63,177
273
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。