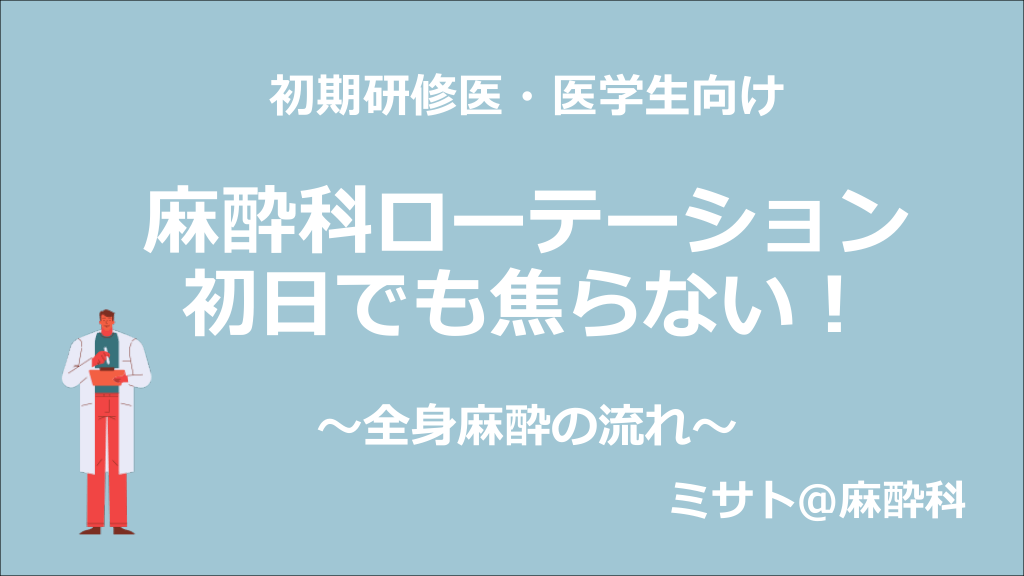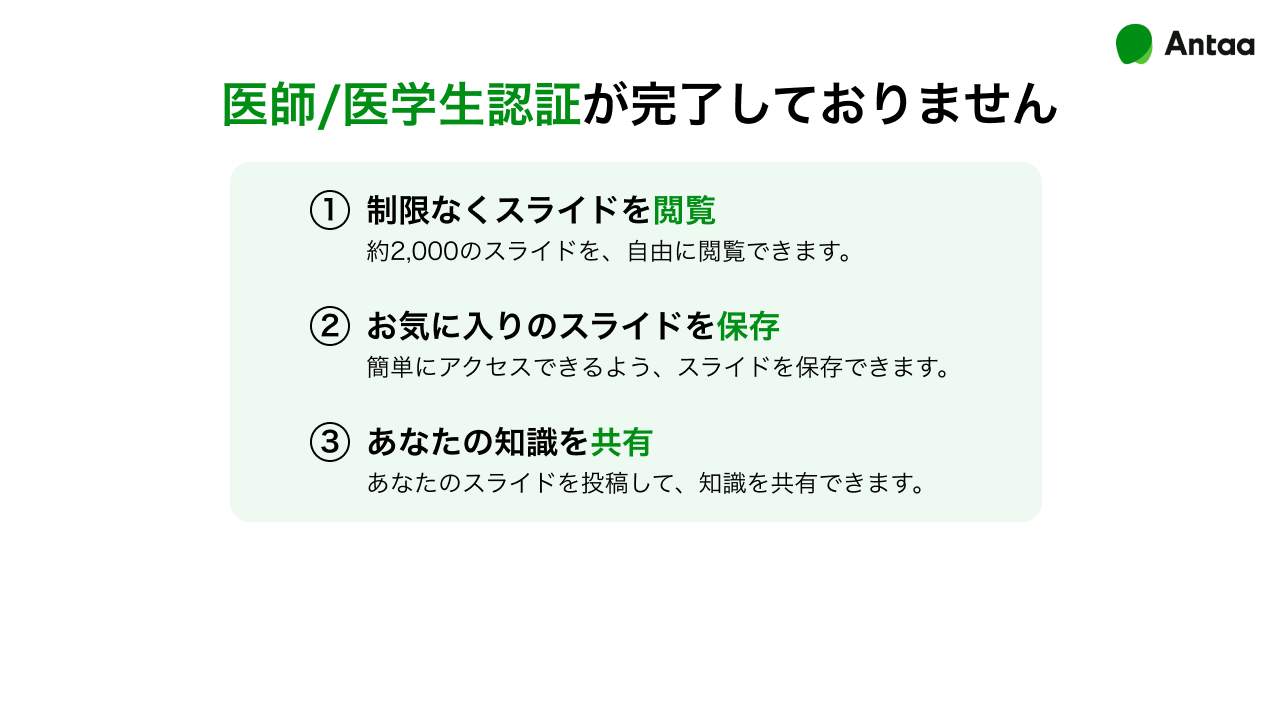このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/26
関連するスライド
もう迷わない心電図!(徐脈・頻脈編)
常見勇太
40259
147
【デキレジ】脳梗塞⑤病型診断のキホン
やまて
259003
904
アナフィラキシーの初療についてAntaa Slideと本で勉強してみよう
永井友基
29585
102
#4 高血圧症【高血圧の基礎から2次性高血圧の実臨床まで】
うし先生
140269
366
麻酔科ローテーション初日でも焦らない!〜全身麻酔の流れ〜
208,747
1,428
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。