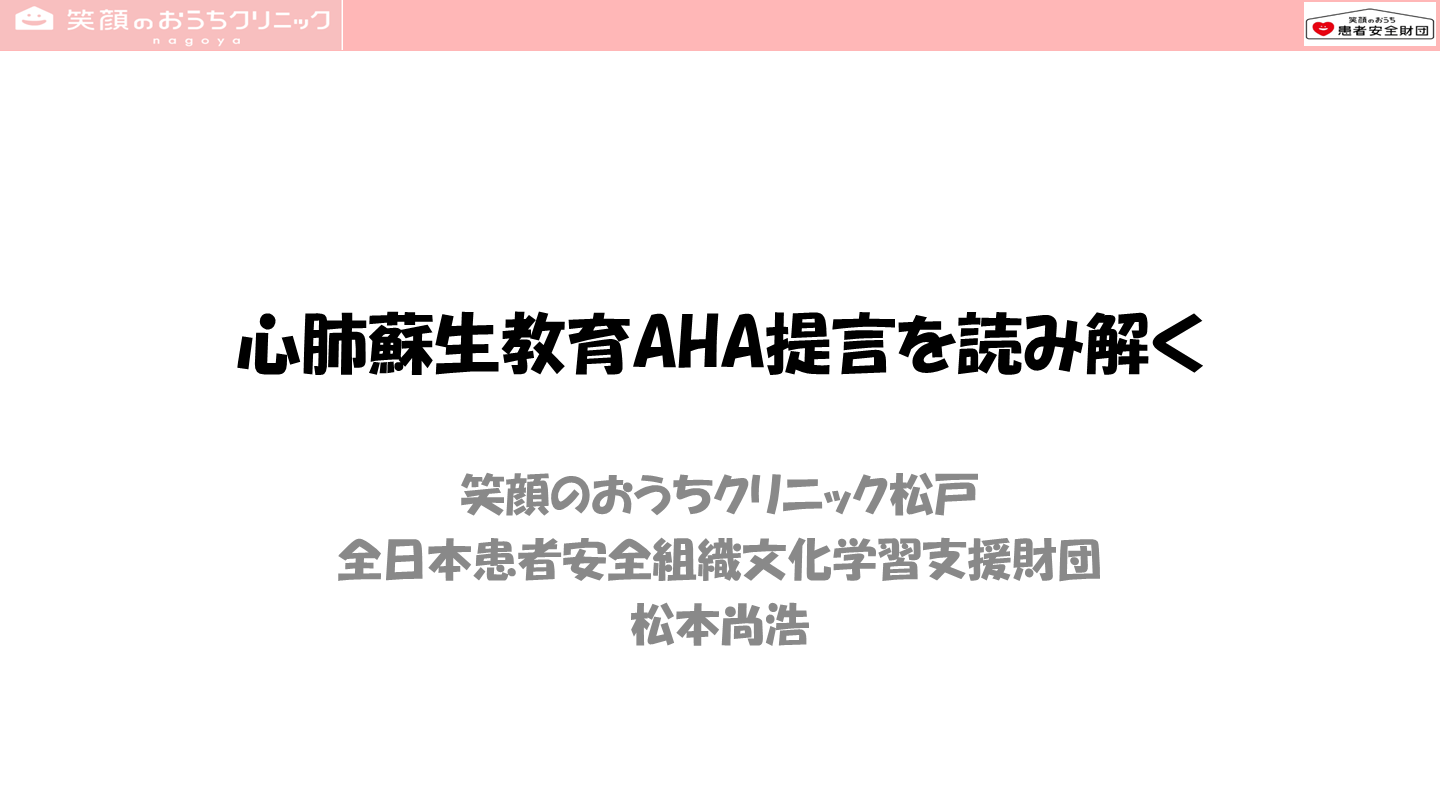1/168
関連するスライド
【最新版】BLS・ALS(ACLS)のまとめ【JRC 蘇生ガイドライン2025参照】
三谷雄己
1116105
1243
おそるるに足らず。在宅の褥瘡の診かた
やまと診療所 AHC-ACADEMY OF HOME CARE-
8862
47
イケてる医療教育・訓練をめざそう
松本尚浩
16440
18
在宅医療における患者さんの電話対応
やまと診療所 AHC-ACADEMY OF HOME CARE-
7232
11
蘇生率改善につながる蘇生教育
20,066
12
概要
アメリカ心臓協会(AHA)が医学雑誌Circulationに提示した蘇生科学教育への提言の内容に基づき、蘇生教育の問題、改善への方略をまとめました。
本スライドの対象者
専攻医/専門医
投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!
0 件のコメント
松本尚浩さんの他の投稿スライド
このスライドと同じ診療科のスライド
テキスト全文
心肺蘇生教育の重要性と提言
#1.
心肺蘇生教育AHA提言を読み解く 笑顔のおうちクリニック松戸 全日本患者安全組織文化学習支援財団 松本尚浩
#2.
DVD収録プレゼンテーション 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 2
#3.
完全習得学習と集中的練習 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 3
完全習得学習と集中的練習の実践
#4.
【物語1】ある市民向け心肺蘇生術コースで、Aさんは、100回/分の速さで胸骨圧迫するのが難しく、インストラクターが手拍子でその速さを示してくれて、なんとかコース終了しました。 CPR Education for Patient Safety 4 15 Jun 2019 Aさんは胸骨圧迫を正しい速さで 実施出来るでしょうか?
#5.
【物語2-1】ある医療者向け二次救命処置コース。モニター付き除細動器の時限でインストラクターは、看護師Bさんに、「これが心室細動(VF)の波形です」と示した。 CPR Education for Patient Safety 5 15 Jun 2019
#6.
【物語2-2】看護師Bさんはシナリオの時限で、「心電図波形が示されたら「VFです。」と言えばいい」と把握。波形診断の自信はないけど、「VFです」と言うだけはできて、インストラクターも「OK」と判定 CPR Education for Patient Safety 6 15 Jun 2019 Bさんは心電図波形を みわけることが出来るでしょうか
#7.
完全習得学習と集中的練習 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 7 コース参加者が、 患者安全と明確に関連するスキルを 「習得できる」まで、 教育者は教育体験を提供する必要あり インストラクターは、「完全習得学習」と「集中的練習」支援技能の習得を
心肺蘇生術コースの改善案と提案
#8.
完全習得学習 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 8
#9.
完全習得学習と集中的練習 教育的利益を最大化するために教師が知るべき、シミュレーション基盤型医学教育の特徴 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 9
#10.
例示(1/2):心肺蘇生術でのモニター付き除細動器使用 場面: 心肺蘇生術が開始されている 応援者がモニター付き除細動器を現場に届けた チェックリスト □「モニター付き除細動器到着しました」報告 □電源ボタンを押す □心電図導線装着(赤:右肩、黄:左肩、緑:左下肢) □心電図波形をII誘導 □「心電図モニター装着、波形II誘導です」報告 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 10
#11.
例示(2/2):心肺蘇生術でのモニター付き除細動器使用 完全習得学習 チェックリスト1項目ずつ実技実施 ある項目が実施可能かどうか形成的評価 ある項目実施可能を確認して、次項目実技 集中的練習 あるチェックリスト項目で達成ギャップあり フィードバック・キュー(学習者状態の情報を提供) 練習・練り上げ そのチェックリスト項目達成確認 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 11
#12.
心肺蘇生術コース中に「起こっていること」と改善案 コース参加者は、コース終了時点で、「確実にわかる」「確実にできる」か不明 改善案:誰が判定しても差が生じないチェックリスト インストラクターは、一度「わかる」「できる」を確認すると、「学べた」と判定している 改善案:指定された回数以上、基準時間より短時間に 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 12
市民と医療従事者向けの教育提案
#13.
心肺蘇生術コース後に「起こっていること」と改善案 コース参加者は、自分の現場で、どんな知識・技能レベルに到達しているか不明。 改善案:コース後も利用可能なチェックリストと、知識・技能確認の仕組み創り インストラクターは、シミュレーション教育場面で、「完全習得学習」や「集中的練習」を応用できない。 改善案:「完全習得学習」や「集中的練習」技能を自分の教育現場で応用するための訓練 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 13
#14.
【残念な私達の習慣】学習者が学ぶべきことを確実に到達したかどうかはさておき、試験点数つけて、次の単元にすすむ教育に慣らされている CPR Education for Patient Safety 14 15 Jun 2019
#15.
【改善すべきこと】「傷病者が救命される」ための最低限項目を確実に達成させる CPR Education for Patient Safety 15 15 Jun 2019
#16.
【市民コース向けの提案】一回の市民一次救命処置コースで、達成目標は出来る限り少なく。例)「救急車とAEDを要請する」「胸骨圧迫の速さが100-120/分」 CPR Education for Patient Safety 16 15 Jun 2019
#17.
【医療従事者コース向けの提案】「インストラクター技能」向上のために、「完全習得学習」と「集中的練習」を実施する学習内容を限定的に決めてインストラクションを実施する CPR Education for Patient Safety 17 15 Jun 2019
#18.
【市民コース後の提案】一次救命処置達成チェックリストが多すぎるならばコース後も、自分の周囲の人とチェックリスト全項目で完全に出来るよう練習を続ける場を創る CPR Education for Patient Safety 18 15 Jun 2019
#19.
【医療従事者コース後の提案】自分の職能・職責に適切な二次救命処置チェックリスト項目は完全到達目指して、集中的練習を現場で続ける仕組みを創る CPR Education for Patient Safety 19 15 Jun 2019
フィードバックとデブリーフィングの重要性
#20.
【インストラクターへお願い】「完全に習得できた!」を保証できるインストラクションや、ゴール達成が困難あれば適切なフィードバックができるインストラクション技能を身に着けましょう CPR Education for Patient Safety 20 15 Jun 2019
#21.
集中的練習の要点 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 反復練習とフィードバック(狭義)が重要 21
#22.
完全習得学習へのフィードバック 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety (松本尚浩、医療職の能力開発 ;2:25-34,2013) この3段階を実践して完全習得学習促進 一般的(狭義) フィードバック 22
#23.
反復練習を含めたフィードバック 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety フィードバック・システムであれば、 練習は含まれていて確実に起こる 練習・変化 23
#24.
【要注意】 現状の蘇生術コースで 「完全習得学習」や 「集中的練習」は 応用する余裕は 限定的です 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 24
#25.
反復練習 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 25
#26.
【物語3】ある市民向け心肺蘇生術コース後、Cさんは「忘れないよう繰り返しを」と、子供のサッカーチームの父母会で心肺蘇生術練習会を毎月開催している CPR Education for Patient Safety 26 15 Jun 2019
#27.
【物語4】ある二次救命処置コース後、理学療法士Dさんは「コース中は一気に新しいことばかりで、自信がもてなかった」と感じた。職場の同僚と、「急変に遭遇した直後の対応」だけ練習を繰り返すことにした。 CPR Education for Patient Safety 27 15 Jun 2019
#28.
反復練習 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 28 蘇生訓練コース後、 スキルと知識が悪化して、 実際の蘇生パフォーマンスが最適でない。 インストラクターは、学習者に個別的に適切な間隔・回数の反復練習調整を
#29.
反復練習 短時間に 集中して学ぶ方法(massed practice)は、直後の試験合格には 効果的な学習方法 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 29
#30.
心肺蘇生術コース中に「起こっていること」と改善案 コース参加者は、コース終了時点で、「たくさん、詰め込まれた気分」になっている。 改善案:分割コース インストラクターは、コース終了間際に、参加者が知った・できたことを再現できる程度には教える。 改善案:コース中から、反復練習の機会を創るよう、コース参加者の計画立案を支援する。 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 30
認知負荷と学習効果の関連性
#31.
心肺蘇生術コース後に「起こっていること」と改善案 コース参加者は、コース後、数ヶ月で学んだ内容を忘れて・できなくなる。 改善案:コース後、蘇生術知識・技能を反復練習する仕組み創り インストラクターは、コースとコースの間の時期に反復練習の支援をしていない。 改善案:日常的なインストラクション場面で、「保持・転移」を促進するインストラクション技能を高める。 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 31
#32.
【残念な私達の習慣】繰り返される試験の度に、「直前対策」や「一夜漬け」で間に合わせた体験を続けている。 CPR Education for Patient Safety 32 15 Jun 2019
#33.
【改善すべきこと】学習内容は、時と共に「忘れる・できなくなる」のを前提とした学習支援を設計しよう CPR Education for Patient Safety 33 15 Jun 2019
#34.
【市民コース向けの提案】一度に学ぶ量を減量させる。例)「胸骨圧迫のみコース」「AED(自動体外式除細動器)のコース」「救急システム連絡練習のみコース」 CPR Education for Patient Safety 34 15 Jun 2019
#35.
【医療従事者コース向けの提案】コース終了後、知識技能の悪化を防ぐための、反復練習や過剰学習の計画立案を支援 CPR Education for Patient Safety 35 15 Jun 2019
#36.
【市民コース後の提案】一次救命処置コース後に、自分の地域で互助的な「ミニコース」を繰り返し開催 CPR Education for Patient Safety 36 15 Jun 2019
#37.
【医療従事者コース後の提案】自分の部署内で、急変第一対応者と数名で行う「チームでBLS」の反復練習 CPR Education for Patient Safety 37 15 Jun 2019
#38.
【インストラクターへお願い】コース後、現場で、コース参加者の知識・技術の個人データを収集してトレーニング間隔を決定する学習環境創りに貢献してください CPR Education for Patient Safety 38 15 Jun 2019
#39.
【要注意】 現状の蘇生術コースで 「反復練習」を実施すると 練習・テスト回数が増え、 所要時間と費用が 増加する可能性 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 39
#40.
文脈学習 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 40
実践的な学習環境の構築
#41.
【物語5】ある市民向け心肺蘇生術コースで、Eさんの自宅地域では、救急車到着まで30分近くかかるので胸骨圧迫を一人で30分も続けられない不安がある CPR Education for Patient Safety 41 15 Jun 2019
#42.
【物語6】ある医療者向け二次救命処置コース。放射線技師のFさんは、自分の現場では、蘇生チームのリーダーは務めないのにコース中、その役割を割り当てられて人前で失敗して辛かった。 CPR Education for Patient Safety 42 15 Jun 2019
#43.
文脈学習 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 43 コース参加者が、現場で実施することと関連性がある適切な 学習内容を選択すべき インストラクターは、 学習者の感情やストレス、職能・職責に適切な学習支援を
#44.
文脈学習 学習者の現実世界での パフォーマンス最適化につながる訓練を実施。 「いつか役立つ」よりも 「明日、役立つ」を 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 44
#45.
心肺蘇生術コース中に「起こっていること」と改善案 コース参加者は、コースで学ぶ学習内容が自分の現実で役立つのか不明。 改善案:コース参加者が現場で遭遇しそうな物語を提示したり体験談を視聴したりする場を提供。 インストラクターは、参加者一斉に同様の学習内容習得を求める。 改善案:学習達成予定チェックリスト一覧から、参加者個別に、「現場で役立ちそうな」項目を選び、学ぶ 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 45
#46.
心肺蘇生術コース後に「起こっていること」と改善案 コース参加者は、コース後に自分の現場で知識・技能の出来栄え(パフォーマンス)改善を明示できない。 改善案:実際に蘇生術を実施するのは稀なので、蘇生術自体のパフォーマンス改善は、確認が困難。市民であれ、医療従事者であれ、コースとコースの間に、胸骨圧迫のパフォーマンス状態を評価する仕組みを工夫する インストラクターは、「現場で実践が改善する」ために学んだ知識・技能を応用する方略を示していない。 改善案:振り返り会話で「今日学んだ内容を現場でどのように活かすか」に話題の焦点を置く。 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 46
#47.
【残念な私達の習慣】「いつか役立つかもしれない」学習内容を与えられることに慣らされている。 CPR Education for Patient Safety 47 15 Jun 2019
#48.
【改善すべきこと】学習者の現場でのパフォーマンスが改善するために、その学習者に個別に、適切な教育・訓練を提供する CPR Education for Patient Safety 48 15 Jun 2019
#49.
【市民コース向けの提案】市民一次救命処置コースで、「傷病者の見分け方」、「119番通報の仕方」、「胸骨圧迫ができる人の集め方」などから、自分の現場実践と関連性のある学習内容を選択する CPR Education for Patient Safety 49 15 Jun 2019
#50.
【医療従事者コース向けの提案】現実の職務・職責で実施する業務内容に関連性がある学習内容を選択して、コース参加する仕組みを創る CPR Education for Patient Safety 50 15 Jun 2019
評価方法とその改善点
#51.
【市民コース後の提案】自分の地域で、利用可能AED確認、救急出動要請リハーサル、長時間の胸骨圧迫想定して胸骨圧迫ができる、近所の住民を集める方法検討。 CPR Education for Patient Safety 51 15 Jun 2019
#52.
【医療従事者コース後の提案】「コースでは実施できても現場では緊張が強くてできない」学習者には、自分の現場に類似の環境、模擬患者などを工夫して、現場実践向上を目指す CPR Education for Patient Safety 52 15 Jun 2019
#53.
【インストラクターへお願い】「役立つかもしれない」を避けて「その学習者の現場でのパフォーマンスが改善するかどうか?」に配慮した学習支援を心がけましょう。 CPR Education for Patient Safety 53 15 Jun 2019
#54.
フィードバックとデブリーフィング 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 54
#55.
お詫びと訂正(蘇生教育科学AHA提言 全文日本語訳) 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 55 パフォーマンスのデータ(フィードバック)と パフォーマンスに関する会話(デブリーフィング)がパフォーマンスの向上を促進します。
#56.
【物語7】ある市民向け心肺蘇生術コースで、Jさんは、初参加のため緊張していた。担当インストラクターが、「今日のゴールはこのチェックリスト内容です。最初はうまくできなくても、最後には出来るまで必ず手伝います。」と話してくれてとても安心できた。 CPR Education for Patient Safety 56 15 Jun 2019
#57.
【物語8-1】ある医療者向け二次救命処置コース。看護師Kさんがチームリーダー役で、シナリオ実施後に、インストラクターが、「今回胸骨圧迫中断時間が11秒の場面がありました。」とデータをフィードバックした。 CPR Education for Patient Safety 57 15 Jun 2019
#58.
【物語8-2】そして「次回同じシナリオだとしたら、11秒を短縮するにはどうしますか?リーダー役のKさん司会して2分間で計画をまとめてください。」といった。 CPR Education for Patient Safety 58 15 Jun 2019
#59.
フィードバックとデブリーフィング(FB と DB) 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 59 最適化されたFDとDBの実践は 主要スキルの保持を促進し、 患者の転帰に影響を与える。 FBは、パフォーマンスギャップ(学習目標と現状の差)を埋めることを目指す
#60.
フィードバックとデブリーフィング 重要な教育手法だが、 指導者が 訓練されていないため、 学習効果上、有害な こともある 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 60
インストラクターの能力開発と役割
#61.
医療従事者の自己評価能力に問題 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 61 インストラクターも自己評価能力が低い可能性
#62.
学習者が積極的にフィードバックを求める技能が必要 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 62 フィードバック・デブリーフィング能力への フィードバックをインストラクターは自ら求めるべき
#63.
あなたがフィードバックを受ける(与える)と、学習者パフォーマンスが改善する A: 全くそう思わない B: あまりそう思わない C: ややそう思わない D: ややそう思う E: かなりそう思う F: とてもそう思う CPR Education for Patient Safety 63 0 vote at Tak-Mats.participoll.com A B C D E F 15 Jun 2019
#64.
フィードバックもデブリーフィングも学習の状態改善を目指そう 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 64
#65.
心肺蘇生術コース中に「起こっていること」と改善案 コース参加者は、インストラクターから何か言われるのではないかと、心配・不安を感じている。 改善案:コース参加者に、「インストラクターは、基準に到達するまで手伝う」と宣言する。 インストラクターは、デブリーフィングが効果的かどうか、自信がない。 改善案:デブリーフィングで示された「改善計画」に従って、同じシナリオに取り組ませ、パフォーマンスが改善するかどうか確認する。 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 65
#66.
心肺蘇生術コース後に「起こっていること」と改善案 コース参加者は、コースで学んだ知識・技術を現場で活かす機会がなく、忘れて・できなくなってしまう。 改善案:コース中のフィードバック・デブリーフィングは毎日現場で応用出来ることを、インストラクターは示唆する。 インストラクターは、改善が明確な、フィードバックやデブリーフィング技能がない。 改善案:見よう見まねでなく、フィードバックやデブリーフィング技能の訓練を受ける。 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 66
#67.
【残念な私達の習慣】日常的に行っている反省や指摘、振り返りを学習場面で流用しているだけ。 CPR Education for Patient Safety 67 15 Jun 2019
#68.
【改善すべきこと】学習者のパフォーマンスギャップが小さくなるためのフィードバック・デブリーフィング技能をインストラクターは身につけよう CPR Education for Patient Safety 68 15 Jun 2019
#69.
【市民コース向けの提案】コース終盤で、「今日学んだことを活かして、自分の周りの人々も心肺蘇生術が出来るようにするにはどうしたらいいか?」に焦点をおいた、振り返り会話 CPR Education for Patient Safety 69 15 Jun 2019
#70.
【医療従事者コース向けの提案】インストラクターは、心肺蘇生術の知識・技術があるだけではなく、学習者のパフォーマンスギャップが小さくなるフィードバック・デブリーフィングを実施できる訓練を続ける。 CPR Education for Patient Safety 70 15 Jun 2019
行動変容と蘇生率改善のための戦略
#71.
【市民コース後の提案】コース終了後、心肺蘇生術の知識・技術の状態を、自らフィードバックしてもらう仕組みをつくる CPR Education for Patient Safety 71 15 Jun 2019
#72.
【医療従事者コース後の提案】自分の現場で、実践改善のために、学習支援手法としてフィードバック・デブリーフィング応用。 CPR Education for Patient Safety 72 15 Jun 2019
#73.
【インストラクターへお願い】自分の自己評価能力が妥当になるまで、積極的に他者からのフィードバックを受けましょう CPR Education for Patient Safety 73 15 Jun 2019
#74.
【要注意】 現状の蘇生術コースでは適切なフィードバックや デブリーフィングを 実施するのは困難 (コースの構成変更が必要) 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 74
#75.
評価(1/3) 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 75
#76.
すこし、道草学びの「真正性」について 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 76
#77.
複数の「妥当だね」が共有され、その場での「本物さ」とか「真正性」に 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 77 これ、 妥当だね これ、 妥当だね
#78.
学ぶ人にとって、必ずしも妥当でない「真正性」が疑わしい学びの場がある 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 78 教える 私には 妥当だね 学ぶ私には 妥当かしら
#79.
学習者の現実世界と関連が疑われる「真正性の低い」評価は避けるべき 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 79 今日は、救急部の医師として、蘇生チームのリーダー役を その学び方で、 私の現実世界で、何か改善?
#80.
【物語9】ある市民向け心肺蘇生術コースで、Mさんは、自動体外式除細動器(AED)の操作手順がなかなかできず、マニュアルみながら実技を試行、間違いはマニュアルみて練習、そしてマニュアルなし練習を手伝ってくれて、最終評価で合格できた。 CPR Education for Patient Safety 80 15 Jun 2019
教育の妥当性と評価の重要性
#81.
【物語10】ある医療者向け二次救命処置コース。シナリオの時限で、検査技師Nさんは、インストラクターから「安全な除細動ができていなかったので、もう一度同じシナリオを。」と評価された。 CPR Education for Patient Safety 81 15 Jun 2019
#82.
評価 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 82 効果的な蘇生教育にするには、蘇生教育プログラムの評価方略を開発すべき 妥当な評価のためには、 インストラクターの評価能力開発が必要
#83.
AHA提言「評価」で、示唆はあるが、 質の高い評価 コース開催中をとおしての随時評価 多様な形態の評価 コースとコースの間の期間の評価 学習者の職能・職責に適切な評価 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 83 この、第4,5項目が、 蘇生率改善のために重要な評価改善 しかし、あまり論じていない
#84.
AHA提言「評価」の記述に異議あり 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 84
#85.
評価 評価が容易なものよりも むしろ、患者の転帰にとって 本当に重要なことを 評価では測定すべき 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 85
#86.
評価(2/3) 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 86
#87.
教育観の違い 意図的教育観 結果として「学習が起こった」かどうかにかかわらず「働きかける」ことを重視 成功的教育観 学習者に学習が生じたことによって初めて「教えた」と呼ぶことができる 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 87 「教えたつもり」あり得る インストラクショナル・デザインの立場
#88.
「教室」がなかった頃の人類の学び 訓練の対象 現場実践上の課題 訓練の評価 実践課題の解消 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 88
#89.
「教室での訓練」は現場実践での課題解消を達成しているか? 訓練の対象 本当に現場実践上の課題を扱っているか? 訓練の評価 本当に、実践課題の解消につながっているか? 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 89 教室(現場外)
#90.
「教室での訓練(コース)」にも、実は、妥当な「いいぶん」がある 訓練の対象 訓練の設計者が決定 訓練の評価 訓練終了の基準が設置 例)筆記試験合格基準達成。 例)実技チェックリスト達成 例)6時間以上参加 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 90 教室(現場外) コース後、現場で実践変化は責任の範囲ではない!
学習者のパフォーマンス向上のための方策
#91.
インストラクショナルデザイン(ID)は、「現場で実践改善」を目指す 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 91 教室(現場外) 教室(現場外) IDには現場変化の評価指標あり 従来型 「教室での教育」な 訓練の限界
#92.
多様な側面での「評価」が必要 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 92 コース評価 学習者の現場実践評価 インストラクター技能評価 蘇生率改善の評価
#93.
カークパトリックの研修効果の4段階 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 93
#94.
蘇生率改善こそが、蘇生教育のゴール 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 94 コース評価 学習者の現場実践評価 インストラクター技能評価 蘇生率改善の評価 カークパトリック3レベル、4レベルの教育・訓練の成果確認を カークパトリック2レベル カークパトリック1レベル カーク パトリック 3レベル カークパトリック4レベル
#95.
カークパトリックの3段階を目指そう 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 「蘇生率向上が蘇生教育による」という 結論は難しい 95
#96.
心肺蘇生術コース中に「起こっていること」と改善案 コース参加者に「アンケート調査」をしているが、そのアンケートは「何を評価しているか?」「何を改善するためか」が不明である。 改善案:アンケート調査に「学習体験評価」を応用(後述) インストラクターは、学習者にとって、「多すぎる項目」を一度で評価しようとする。 改善案:「認知負荷」(後述)に配慮した少ない項目数毎、数回に分けて評価を実施 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 96
#97.
「学習体験」を評価しよう(1/2) ARCSモデルを応用 学習意欲のに関するモデル 4要因 A:おもしろそう(注意) R:役に立ちそう(関連) C:やればできそう(自信) S:やってよかった(満足) 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 97
#98.
「学習体験」を評価しよう(2/2) ARCSモデルの各要因別にアンケート調査 調査例(1から10で答えてください) 今日のコースは 1:おもしろくない、2、、、10:おもしろい 1:役に立たない、2、、、10:役に立つ 1:自身が持てない、2、、、10:自身が持てた 1:やってよかったと思わない、10:やってよかった 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 98
#99.
動機づけを改善するARCSモデル、お勧めです! 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 99 インターネットでも多様な資料があり 例: https://goo.gl/eK0lWK
#100.
評価(3/3) 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 100
知識の転移と実施に向けた提案
#101.
数字10個、覚えられる A: 全くそう思わない B: あまりそう思わない C: ややそう思わない D: ややそう思う E: かなりそう思う F: とてもそう思う CPR Education for Patient Safety 101 0 vote at Tak-Mats.participoll.com A B C D E F 15 Jun 2019
#102.
学習には認知負荷がかかる 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 102 作業記憶(ワーキングメモリー)はすぐに限界になる
#103.
「認知負荷」に配慮した評価(1/2) 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 103 1度の評価では、可能な限り認知負荷を下げる工夫を
#104.
「認知負荷」に配慮した評価(2/2) 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 104
#105.
電気ショック不適応波形 電気ショック適応波形 【私案】「認知負荷に配慮した評価」 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 105 医師でないコース参加者は 「心停止波形4種類を答える」は免除で
#106.
心肺蘇生術コース後に「起こっていること」と改善案 コース参加者は、自分の現場で、パフォーマンス改善したかどうか不明。 改善案:コース後は、カークパトリック・レベル3「行動変容」を確認する仕組みを創る。 インストラクターは、学習者の変化に基づいて、コース改善を続けなければならない。 改善案:「学習体験」評価をつうじて、コース改善 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 106
#107.
【残念な私達の習慣】私達は、教育の場で、「妥当な評価方法」を体験したことが、ほとんどないためか、職場教育・訓練で「妥当な評価方法」を実践できていない CPR Education for Patient Safety 107 15 Jun 2019
#108.
【改善すべきこと】「教えたつもり」で満足せず、学習者が変化したこと、さらには、例えば「蘇生率向上に適切な心肺蘇生術実施」の達成を確認する「妥当な評価方法」を探究する CPR Education for Patient Safety 108 15 Jun 2019
#109.
【市民コース向けの提案】市民一次救命処置コースで、「次のコース参加までに知識・技術を保つには?」と尋ね、「計画立案できた」を評価項目にする CPR Education for Patient Safety 109 15 Jun 2019
#110.
【医療従事者コース向けの提案】「実際の職務に適切な知識・技術チェックリスト」を用いて、コース参加、訓練実施、そして評価を。 CPR Education for Patient Safety 110 15 Jun 2019
市民コースと医療従事者コースの違い
#111.
【市民コース後の提案】コース終了後の市民が心肺蘇生術を広げる場を創ることをコース関係者が支援して、確認(カークパトリック3レベル評価) CPR Education for Patient Safety 111 15 Jun 2019
#112.
【医療従事者コース後の提案】自分の施設・部署内で定期的に「チームで胸骨圧迫中断の短い心肺蘇生コンテスト」を開催することをコース関係者が支援・確認(カークパトリック3レベル評価) CPR Education for Patient Safety 112 15 Jun 2019
#113.
【インストラクターへお願い】コース後、参加者が自分の現場で「行動変容した」ことを確認する工夫をしてください。 CPR Education for Patient Safety 113 15 Jun 2019
#114.
【要注意】 学習者は、自分の状況/役割で評価されるべき。 蘇生チームリーダーを現場で務めないならばチームリーダ役として評価されるべきでない。 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 114
#115.
能力開発 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 115
#116.
能力開発 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 116 蘇生率を向上させるには、 蘇生教育のインストラクター能力開発を インストラクター自身が、自己主導型で生涯にわたり学習を続ける人になろう
#117.
優れたインストラクター(学習支援者)の特徴 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 117 自ら学び続ける学習者
#118.
自分は自己主導型学習者 A: 全くそう思わない B: あまりそう思わない C: ややそう思わない D: ややそう思う E: かなりそう思う F: とてもそう思う CPR Education for Patient Safety 118 0 vote at Tak-Mats.participoll.com A B C D E F 15 Jun 2019
#119.
「自己主導型学習者になる学習会」 教材 主な学習方法: アクティブ・ブック・ダイアログ CPR Education for Patient Safety 15 Jun 2019 開催ご希望あればお問い合わせください 119
#120.
学習者に「わかりましたか?」と尋ねる指導者には、やるべきことが多い A: 全くそう思わない B: あまりそう思わない C: ややそう思わない D: ややそう思う E: かなりそう思う F: とてもそう思う CPR Education for Patient Safety 120 0 vote at Tak-Mats.participoll.com A B C D E F 15 Jun 2019
教育方法の改善と学習者の主体性
#121.
私達に染み込んでいるのは、伝導者が神の言葉を伝える場面を真似した教育方法 CPR Education for Patient Safety 121 15 Jun 2019
#122.
【初期インストラクターが改善すべきこと】指導者が話して、デモを見せて、「伝わったかな?」ではなく、学習者にやらせて学ばせる「Learning by Doing(練習ベースの学習)」を実践 CPR Education for Patient Safety 122 15 Jun 2019
#123.
初期インストラクターの訓練 デブリーフィングのツールを用いる デブリーフィング評価ツール ピア・インストラクション インストラクター同士で学ぶ ロールモデル(真似たくなる人)と学ぶ 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 123
#124.
継続的にインストラクターが取り組むべき領域 省察的実践(reflective practice) ピア・コーチング(peer coaching) 実践のコミュニティー(communities of practice) 学び合う仲間を創る アウトカム基盤型教育(outcome-based education) 患者の転帰改善に役立つ学習に焦点化 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 124
#125.
CPR Education for Patient Safety AHAコア・インストラクタ・コース(AHA: アメリカ心臓協会) テキスト裏表紙: “このコースは, 『ibstpi インストラクター コンピテンシー』に 準拠している“ 125
#126.
CPR Education for Patient Safety プロフェッショナルとしての基礎 1. 効果的なコミュニケーションを行う。 2. 専門分野の知識やスキルを常に磨いておく。 3. 規定の倫理や法を順守する。 4. プロフェッショナルとしての信用を確立する。 企画と準備 5. インストラクションと方法と教材を企画準備する。 6. インストラクションに必要な具体的な準備をする。 方法と戦略 7. 受講者が意欲的に、集中して学べるように働きかける。 8. プレゼンテーションを効果的に行う。 9. ファシリテ-ションを効果的に行う。 10. タイミングよく的確に質問をする。 11. 明確な説明とフィードバックを与える。 12. 学んだ知識やスキルが持続するように働きかける。 13. 学んだ知識やスキルが実際に使えるように働きかける。 14. メディアやテクノロジーを使って学習効果を高める。 評価 15. 学習成果とその実用性を評価する。 16. インストラクションの効果を評価する。 マネジメント 17.学習効率と学んだことの実践を促進する環境を維持する。 18.適切なテクノロジーを使って、インストラクションのプロセスを管理する。 国際標準のインストラクター能力 126
#127.
日本語訳もあります 論文「インストラクターコンピテンシーの医療者教育への応用」 ibstpi インストラクターコンピテンシーの解説と応用提案 資料「ibstpi インストラクターコンピテンシー 第4章」 18項目の粗訳 CPR Education for Patient Safety 127
#128.
国際標準のインストラクション技能学べます CPR Education for Patient Safety https://goo.gl/MYkYmu 15 Jun 2019 128
#129.
【事例】動画教材を開発する仲間と指導者の能力開発へ共同体つくり https://goo.gl/Au27sz https://goo.gl/W9QdaU CPR Education for Patient Safety 15 Jun 2019 129
#130.
継続的にインストラクターが取り組むべき領域 省察的実践(reflective practice) ピア・コーチング(peer coaching) 実践のコミュニティー(communities of practice) 学び合う仲間を創る アウトカム基盤型教育(outcome-based education) 患者の転帰改善に役立つ学習に焦点化 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 130
現場での行動変容を促す教育
#131.
私達は、教室で教育できると思い込んでいる CPR Education for Patient Safety 131 15 Jun 2019
#132.
教室で知識・技術与えればどうにかなるだろう? 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 学習者が、現場で問題解決できてこそ 教育の意義がある 132 せいぜいここまでしか到達しない
#133.
「行動変容しているか?」だけでも探究を 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 行動変容・蘇生率変化を観察しながら 教育以外にも出来ることを探す 133 現場で行動が変わるかどうかで、蘇生コースを練り直す
#134.
【インストラクターへお願い】「蘇生コースでインストラクター」で満足しないでください。学習者が自分の現場で行動を変えることを支援する「変化エージェント(変化を起こす人)」を目指してください。 CPR Education for Patient Safety 134 15 Jun 2019
#135.
知識の転移と実施 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 135
#136.
知識の転移と保持 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 136 エビデンスは変化しているのに、 蘇生実践変化はとても小さい 教育だけでなく「改善する」ための 様々な方略が必要
#137.
これまでの教育は「伝えれば人は変わる」と信じていた CPR Education for Patient Safety 137 15 Jun 2019
#138.
医科学と蘇生術コースだけでは、足りない 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 138 ここまでは、改善したとしても 学習者の現場 「教室で学んだ」としても、学習者は 現場で変わっていないのが現実 学習者が 変わるには 大きな壁
#139.
蘇生率改善への焦点は、「コース改善」から「学習の保持と転移へ」 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 139 インストラクショナル・デザイン応用 学習者・組織の変化促進へ 「変化への壁」を改善する取り組み 改善科学 変化理論 デザイン思考
#140.
デザインすることとは、状況を実際の状態からより好ましいものへと変えることである。(ハーバート・サイモン, 1969)
認知負荷に配慮した教育手法
#141.
インストラクショナルデザインの特徴 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 141 学習者の「パフォーマンス改善」が基盤
#142.
「知識の転移と実施」に提案 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 142 是非、論文を読んで、 お役立てください
#143.
傷病者に遭遇したら、躊躇せず救命処置が出来る A: 全くそう思わない B: あまりそう思わない C: ややそう思わない D: ややそう思う E: かなりそう思う F: とてもそう思う CPR Education for Patient Safety 143 0 vote at Tak-Mats.participoll.com A B C D E F 15 Jun 2019
#144.
救命処置の知識・技術は教えられても現場で出来る「態度」は教育困難 A: 全くそう思わない B: あまりそう思わない C: ややそう思わない D: ややそう思う E: かなりそう思う F: とてもそう思う CPR Education for Patient Safety 144 0 vote at Tak-Mats.participoll.com A B C D E F 15 Jun 2019
#145.
【市民コース後の提案】蘇生術で助かった方々の語り、蘇生術を実施した方々の語りなど「救命処置実施が、市民の常識」を目指した、対話の場を創りましょう CPR Education for Patient Safety 145 15 Jun 2019
#146.
都道府県別の蘇生後生存率に違い 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 146 この地域での 高い生存率要因を 研究する価値がある 【提案】蘇生率のよい地域で 「なぜうまくいくのか」を探究しよう [窪山泉、体育・スポーツ科学研究, 11:85-93, 2011]
#147.
最近の教育・訓練評価方法:成功事例法 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 147 この161-3頁に 「成功事例法」記載あり。 成功事例法を応用して、 蘇生率の高い医療機関・地域を分析しませんか
#148.
【インストラクターへお願い】医療で改善すべきことは蘇生率改善だけではありません。また、蘇生率は改善がわかりにくい。変えられそうなことを変える取り組みにもチカラを注いでください。 CPR Education for Patient Safety 148 15 Jun 2019
#149.
特集:認知負荷 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 149
#150.
認知負荷 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 150 今回の提言で高頻度出現(22回)のキーワード インストラクターは、認知負荷に配慮した 学習支援技能を身につけるべき
学習者の感情と動機づけの重要性
#151.
【物語11】ある市民向け心肺蘇生術コースで、Sさんは、心肺蘇生術のデモンストレーション動画を見せられたあと、インストラクターから説明の講義がおわると動画で観たことを忘れてしまっていた。 CPR Education for Patient Safety 151 15 Jun 2019
#152.
認知負荷と関連用語1/2 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 152 (https://bit.ly/2W0ZpUB) 感覚情報 貯蔵庫 短期記憶 長期記憶 注意系 感情系 注意を払う(認知する)と、 短期記憶に情報が集まる(負荷がかかる) (https://bit.ly/2VQwPQS)
#153.
認知負荷と関連用語2/2 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 153 (https://bit.ly/2W0ZpUB) 感覚情報 貯蔵庫 短期記憶 長期記憶 注意系 感情系 短期(作業)記憶は、すぐに限界に達する (https://bit.ly/2VQwPQS)
#154.
インストラクションが認知負荷に悪影響かも 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 154 (https://bit.ly/2W0ZpUB) 感覚情報 貯蔵庫 短期記憶 長期記憶 感情系 注意系 胸骨圧迫のポイントは5つあります。 それは、1,、、、2,、、、 このインストラクターの説明、 わかりにくいけど 大丈夫かなぁ インストラクターが、無駄に 注意を払わせて、短期記憶を 悪化させているかもしれない
#155.
15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 155 大きな認知負荷を 必要とする行動については、 過剰学習を用いましょう 【過剰学習】一定の基準に達した後も、更に同じ訓練を繰り返し、学習すること 完全習得学習・集中的練習と認知負荷
#156.
学習に最も大事なのは、長期記憶の書き換え 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 156 (https://bit.ly/2W0ZpUB) 感覚情報 貯蔵庫 短期記憶 長期記憶 感情系 注意系 多くの段階がある手順 小分けにして 長期記憶を「書き換え」なければ、学んだとは言えない 一定の基準に達した後 何度も同じ訓練 (過剰学習)
#157.
反復練習と認知負荷 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 157 作業記憶(working memory)は7±2に限られ、 タスクの認知負荷が作業記憶容量を超えると 学習者は痛手を負う
#158.
学ぶ人には認知負荷がかかっている 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 158 (https://bit.ly/2W0ZpUB) 感覚情報 貯蔵庫 短期記憶 長期記憶 感情系 注意系 時期を変えて 反復して学ぶ 認知的疲労を予防しながら学ぶ工夫を
#159.
文脈学習と認知負荷 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 159 コース参加者に適切な認知負荷となる 学習内容要素やストレスを調整
#160.
学びやすくなる「感情」を引き起こす 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 160 (https://bit.ly/2W0ZpUB) 感覚情報 貯蔵庫 短期記憶 長期記憶 感情系 注意系 自分の家族は、 心疾患があるから 蘇生術は大切だ! 【要注意】心が傷つかない 体験的学習に配慮が重要 動画視聴
効果的なインストラクションの設計
#161.
学習者に適切な学習内容要素を調整1/2 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 161 (https://bit.ly/2W0ZpUB) 感覚情報 貯蔵庫 短期記憶 長期記憶 感情系 注意系 もうすでに わかってること 自分は学ぶ必要がないと感じると学びにくい (インストラクター) 今日の内容は、、、 知ってるし、 出来るし、 退屈だなぁ
#162.
学習者に適切な学習内容要素を調整2/2 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 162 (https://bit.ly/2W0ZpUB) 感覚情報 貯蔵庫 短期記憶 長期記憶 感情系 注意系 これは、やったこと ないぞ! 学習者の背景に応じた負荷で動機づけが改善 (インストラクター) 次のリーダー役は、 シナリオの状況から 心停止の 原因検索して 適切な治療法を 示してください 難易度が上がって 面白そうだ
#163.
フィードバック・デブリーフィングと認知負荷 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 163 認知負荷を考慮してパフォーマンス・ギャップを検索し、学習必要性を診断すべき 多数の指摘をして、認知負荷を過剰にしない
#164.
評価と認知負荷 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 164 評価者は、 認知負荷を最小限に抑えるために、 一度に少数の、関連する構成概念に 焦点を当てるべき
#165.
評価するときには、いろいろと広げすぎない インストラクション事例 (心停止シナリオ終わって) 安全な除細動は、全員が離れているのを確認できていました。 心室細動のアルゴリズムでも、心停止の原因検索は必要ですので、、、 リーダーは、質の高いCPRができているかどうか、、、、 インストラクション改善案 (心停止シナリオ終わって) このシナリオの目的は「チームワーク改善」でした。 今回は、特に「胸骨圧迫の中断時間」を測定して、1回目は12秒、2回めは9秒、3回目は11秒でした。 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 165 除細動技能、蘇生の手順、リーダーシップなど多数の構成概念に言及している 限定した構成概念に言及している
#166.
認知負荷に配慮した、インストラクションや教材開発が重要 15 Jun 2019 CPR Education for Patient Safety 166 (https://bit.ly/2W0ZpUB) 感覚情報 貯蔵庫 短期記憶 長期記憶 注意系 感情系 雑音を減らして、長期記憶を書き換え易い 教材・インストラクションが必要
#167.