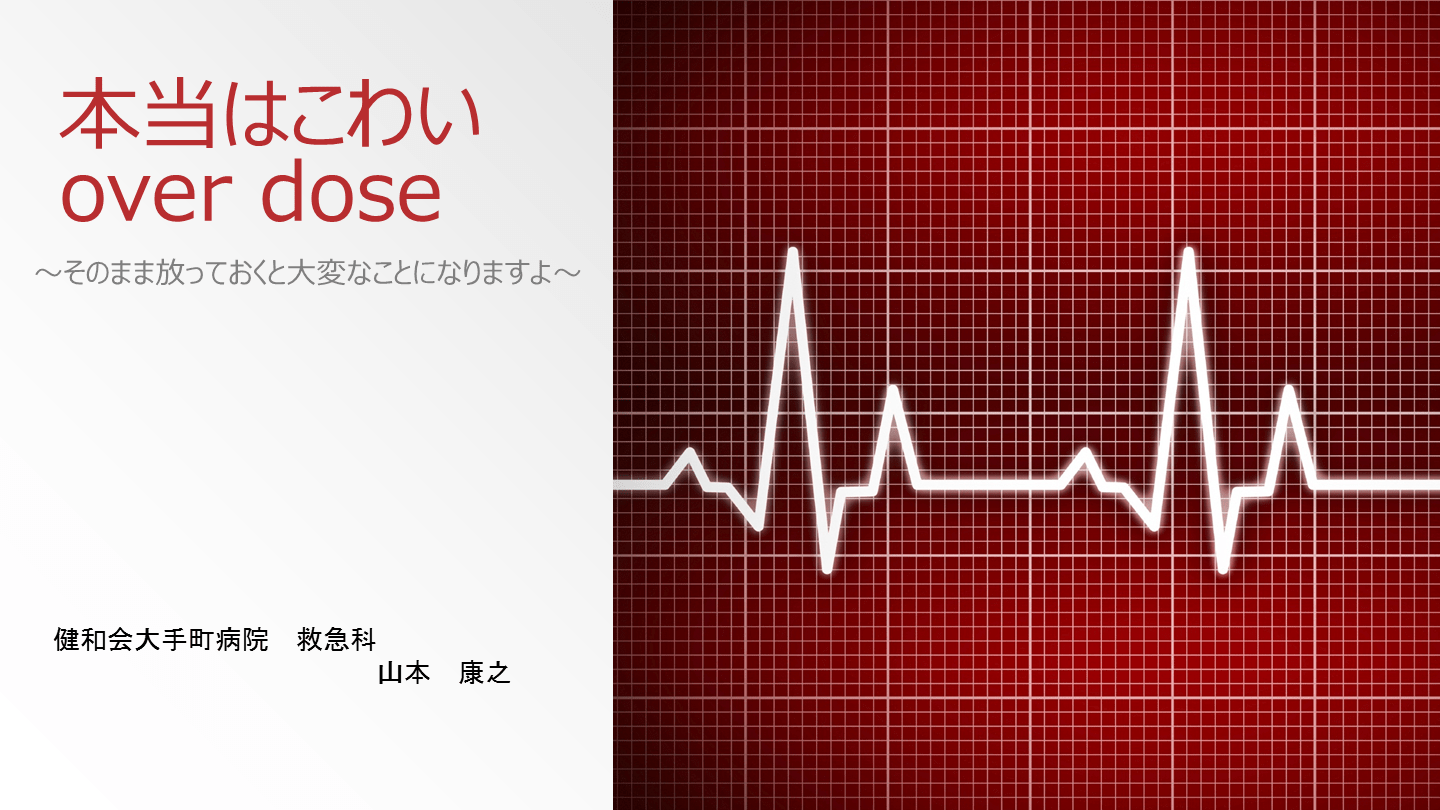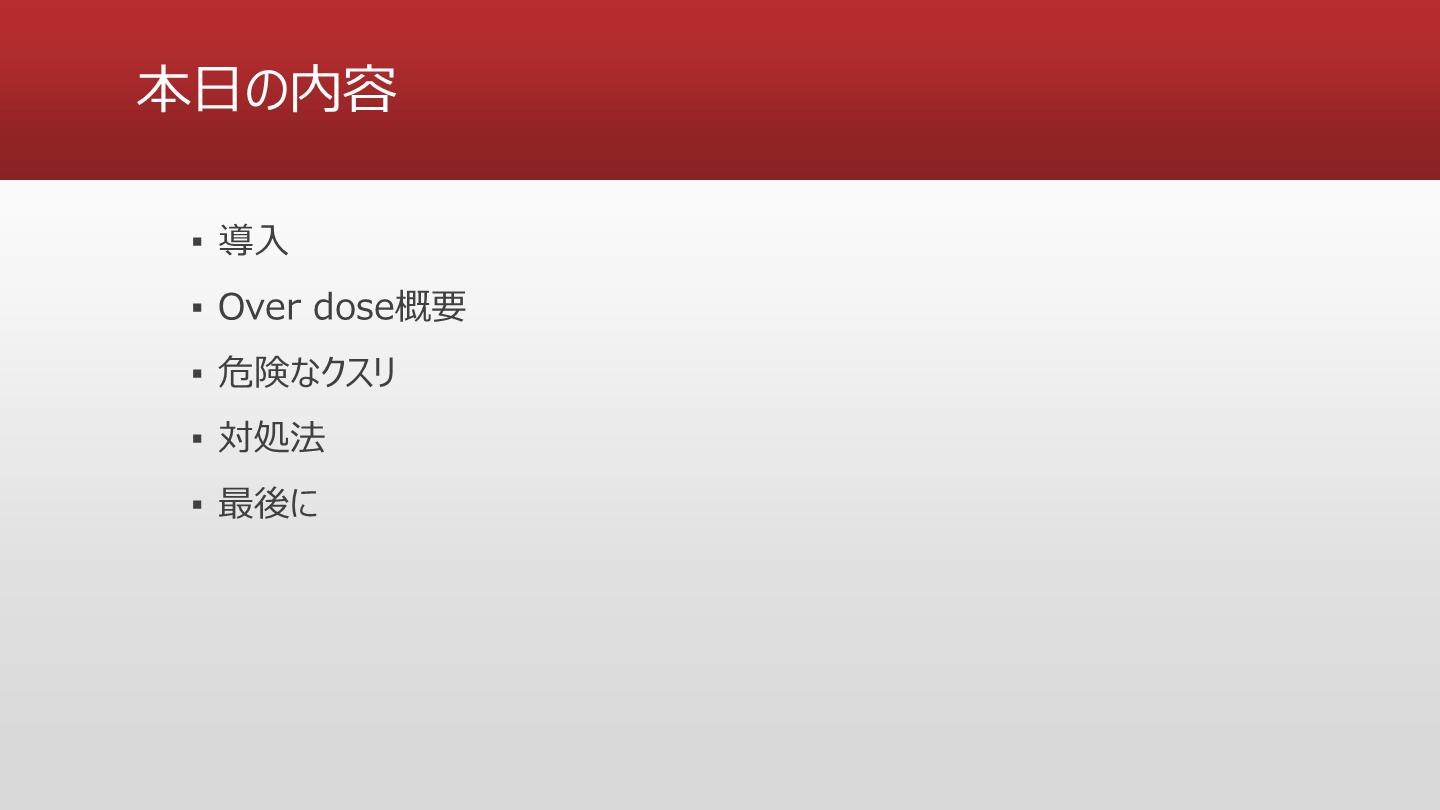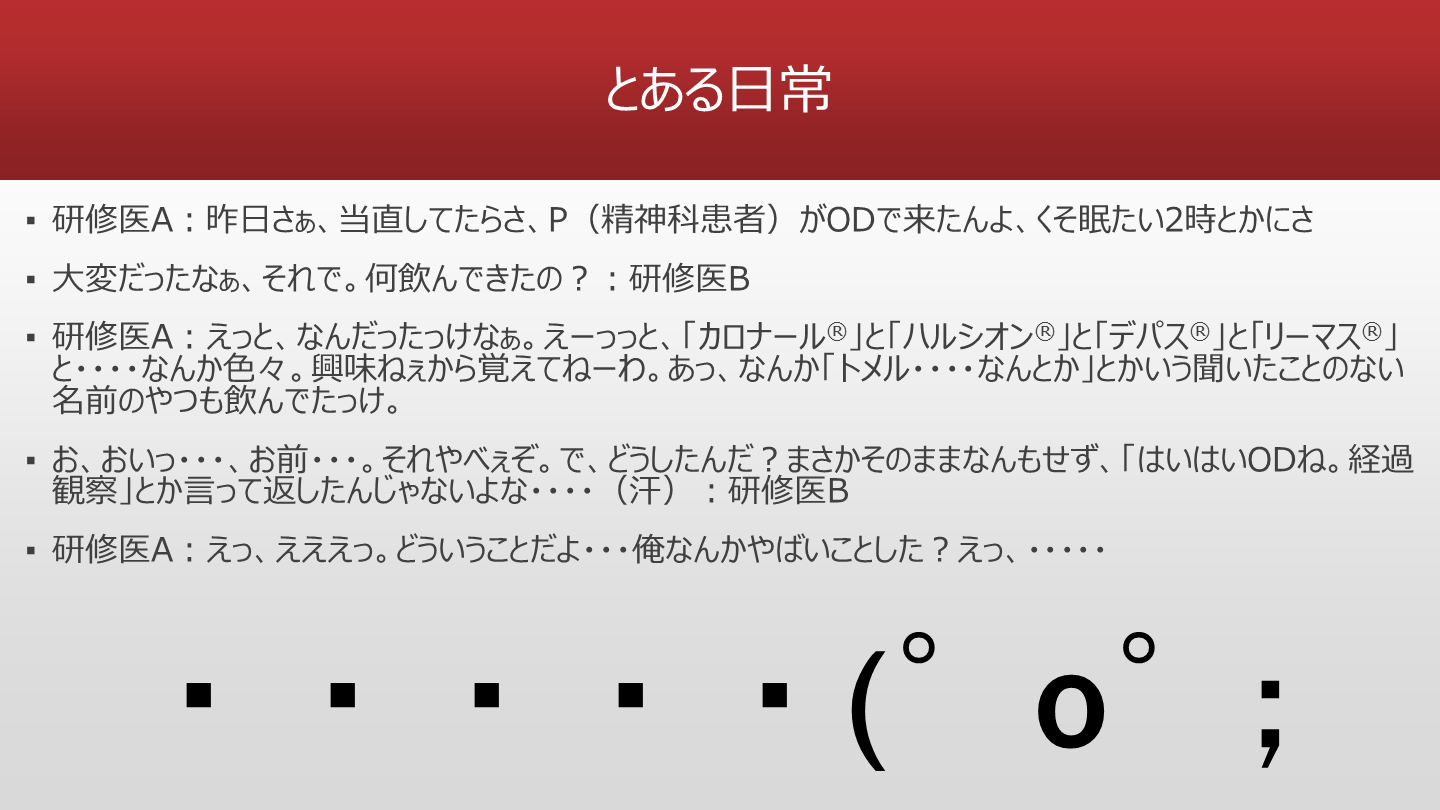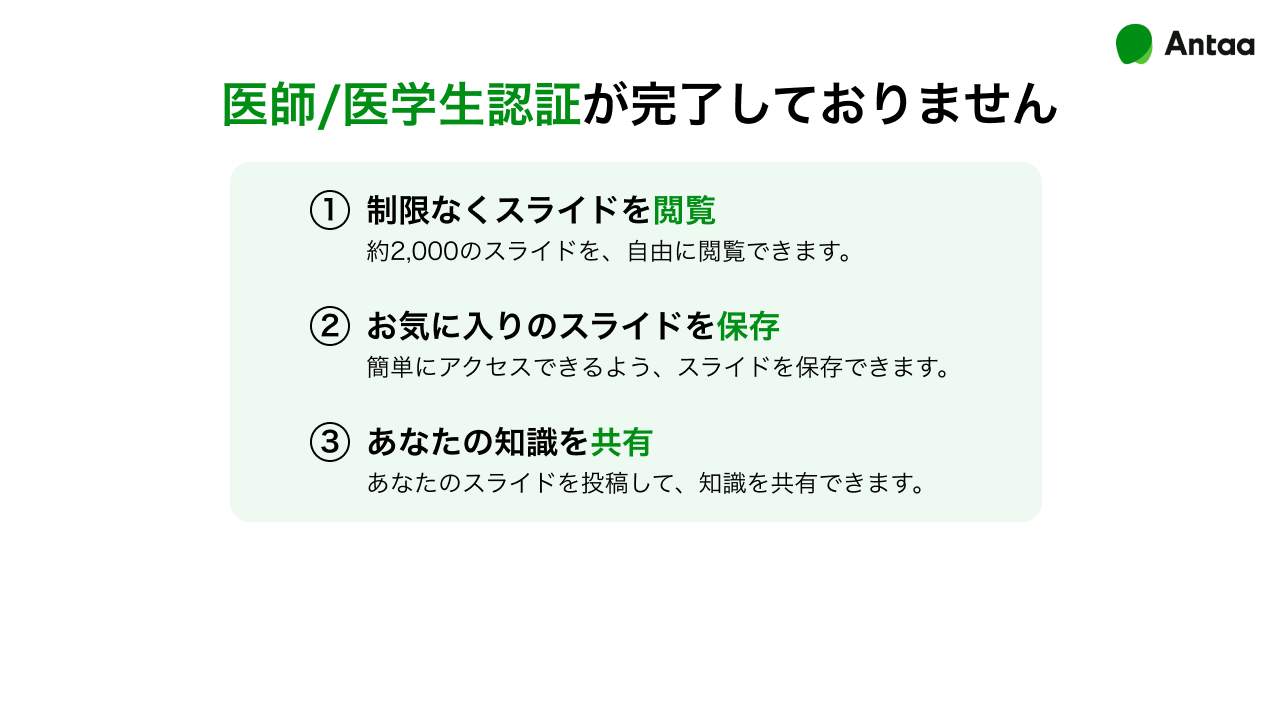このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/21
関連するスライド
薬物中毒診療のピットフォール 〜救急外来や当直の現場でハマる 3つのワナ、教えます!〜
香月洋紀
82603
264
違法薬物使用を疑ったら
バヤシ@救急集中治療
31130
111
中毒まとめ〜症状、臓器障害別原因物質とトキシドローム
ジョージ
53798
176
入院中の転倒予防について、ガイドライン概説とQI事例紹介
びりー
1658
3
過量服薬-本当は怖いoverdose- 危険な薬剤/対処法
129,875
538
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。