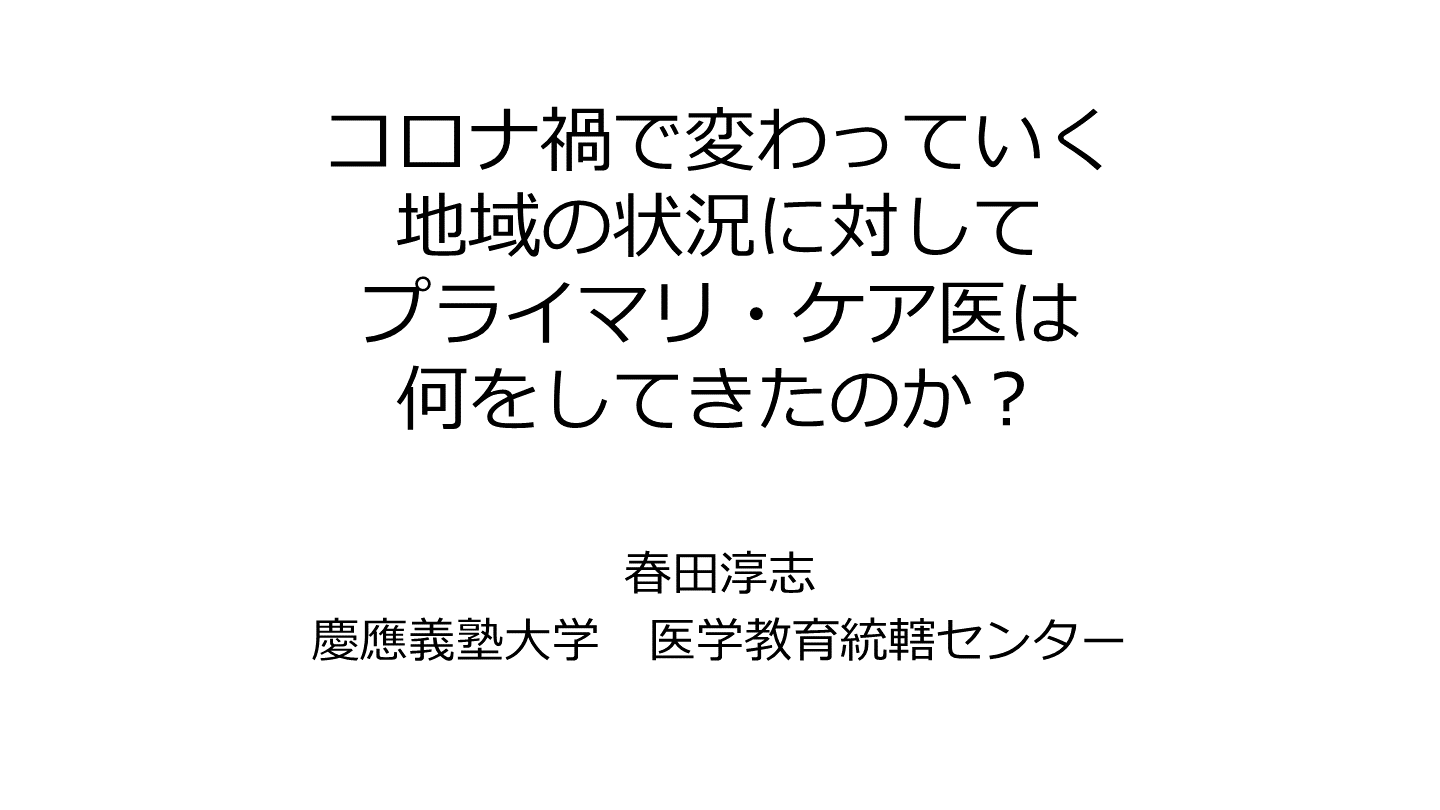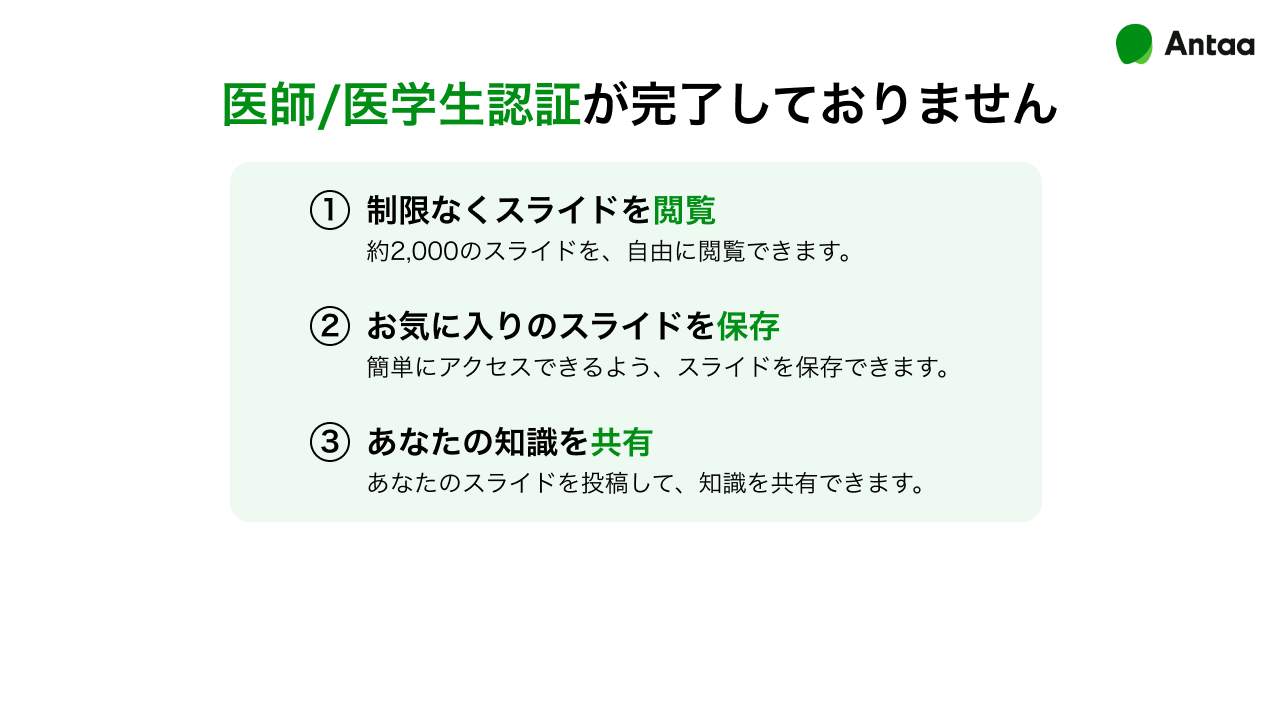このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/36
関連するスライド
健康診断で要精査 尿潜血の対応方法
湯浅駿
100518
785
【藤田総診】糖尿病2019【金子浩之】
近藤敬太
327346
568
「量的研究の変数」プライマリ・ケア研究 はじめの一歩 Vol.6
金子惇
1602
7
〜福島編〜若手総合診療医が地域医療にガチで挑んでみた
森冬人
6288
10
コロナ禍で変わっていく地域の状況に対して、プライマリ・ケア医は何をしてきたのか?
4,426
11
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。