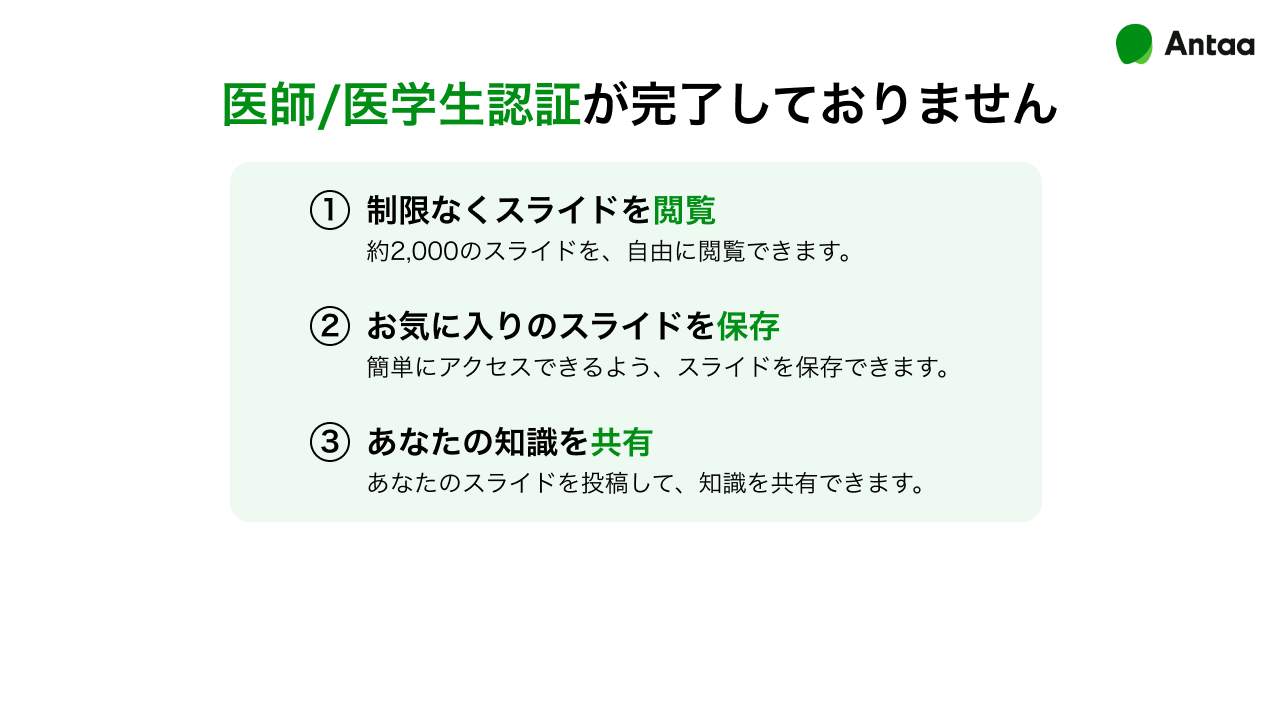このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/65
関連するスライド
精巣捻転症のまとめ【歩いてくるレッドフラックを見逃さない!】
三谷雄己
11714
78
慢性腎臓病のトピックス 一般診療における腎臓病のみかた
志水英明
24924
121
頻尿について~病棟・外来での初期対応~ 基本編
サラリ医マン@泌尿器科
134856
617
尿路結石について ~診断から初期対応まで~ 基本編
サラリ医マン@泌尿器科
213443
558
尿定性検査の見方
79,370
438
ねこすけさんの他の投稿スライド
すべて見るこのスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。