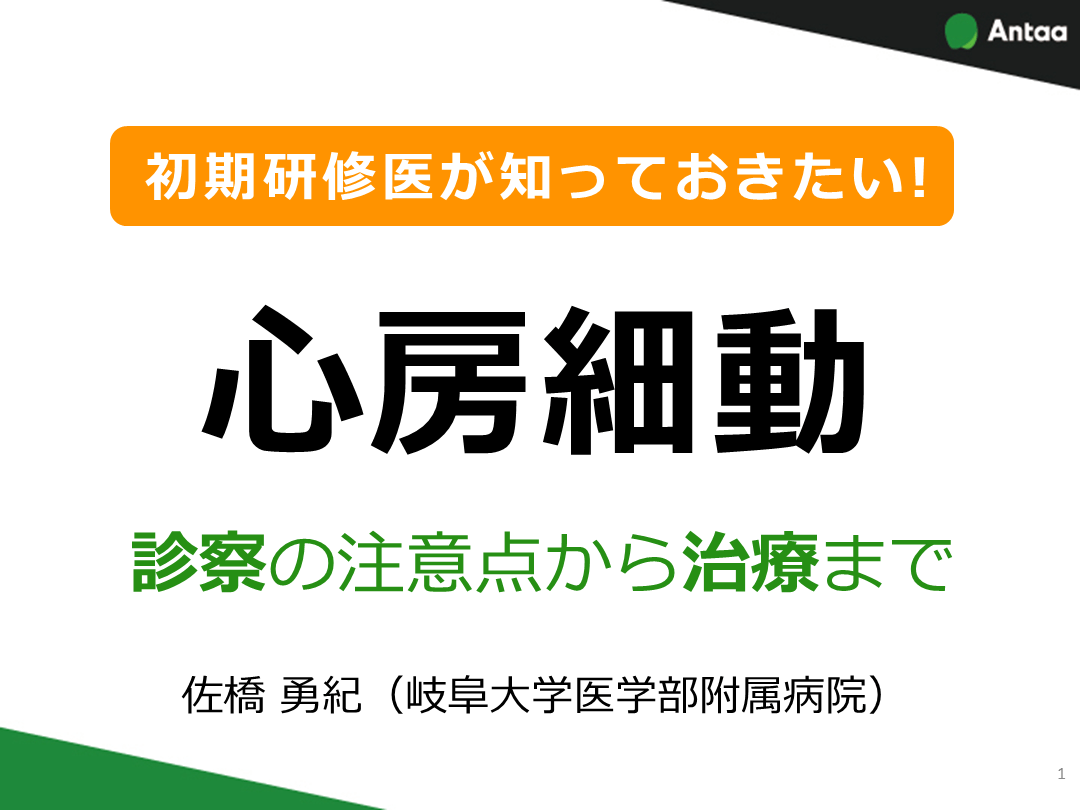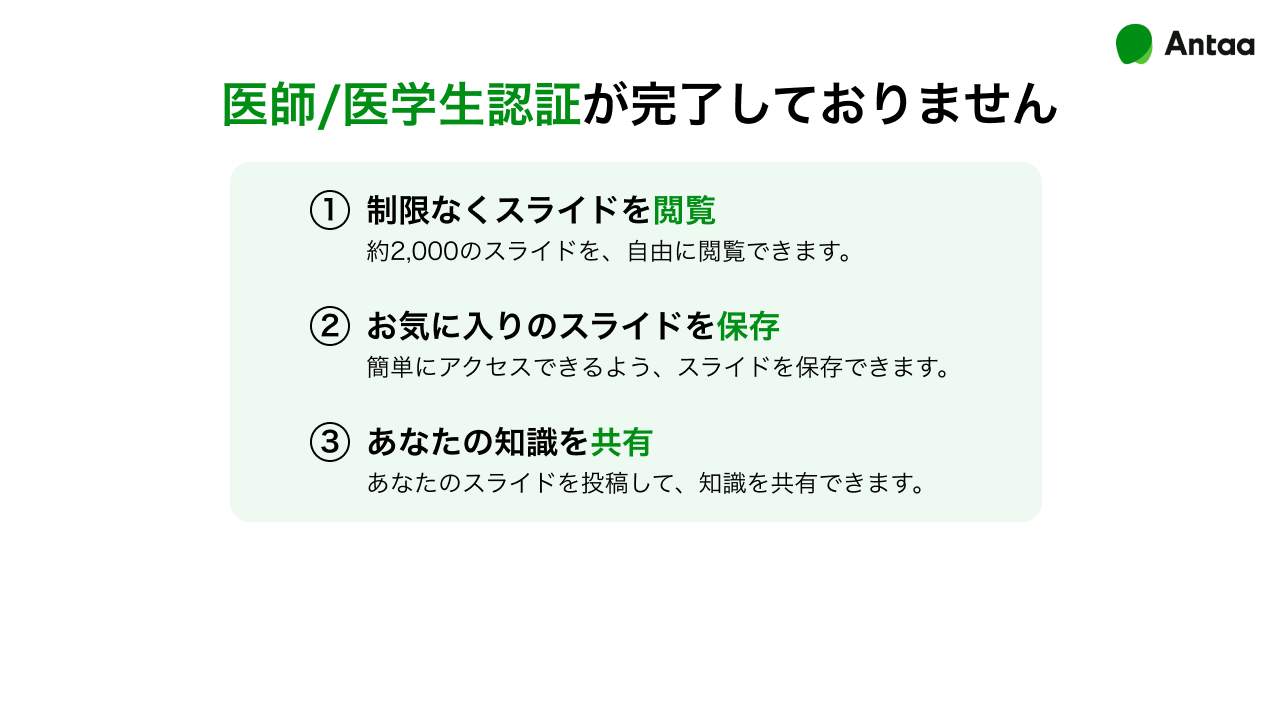このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/51
関連するスライド
【2021年上半期まとめ】ER(救急外来)診療に役立つ最新の医学書5選
三谷雄己
71256
108
病棟での輸液の組み方!
永井友基
3608079
6004
【デキレジ】腰椎穿刺 - 確実にキメるための7step -
やまて
689329
1462
腎梗塞〜教科書にあまり詳しく載っていない疾患の本当のところ〜
長澤将
78898
330
初期研修医が知っておきたい! 心房細動 診察の注意点から治療まで
282,823
825
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。