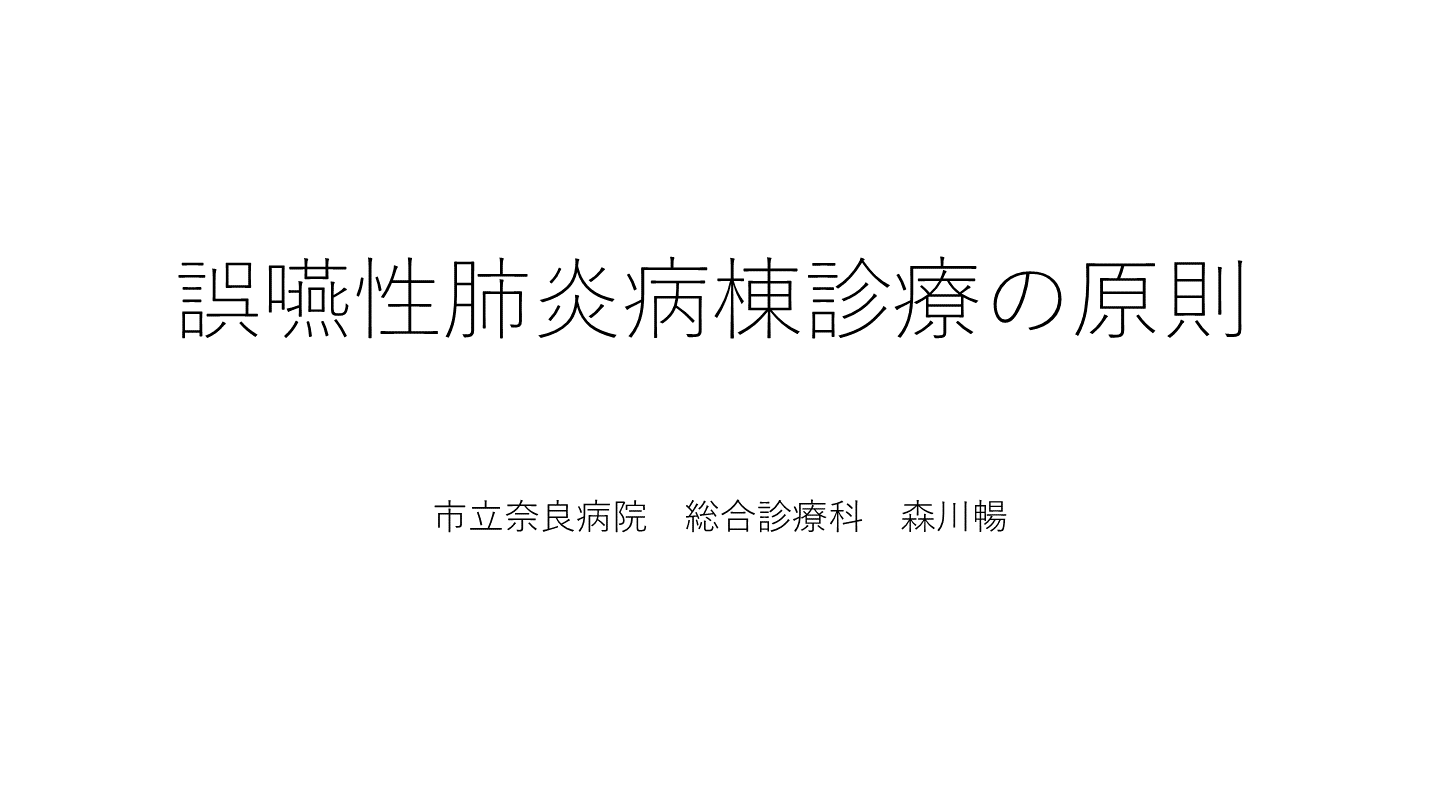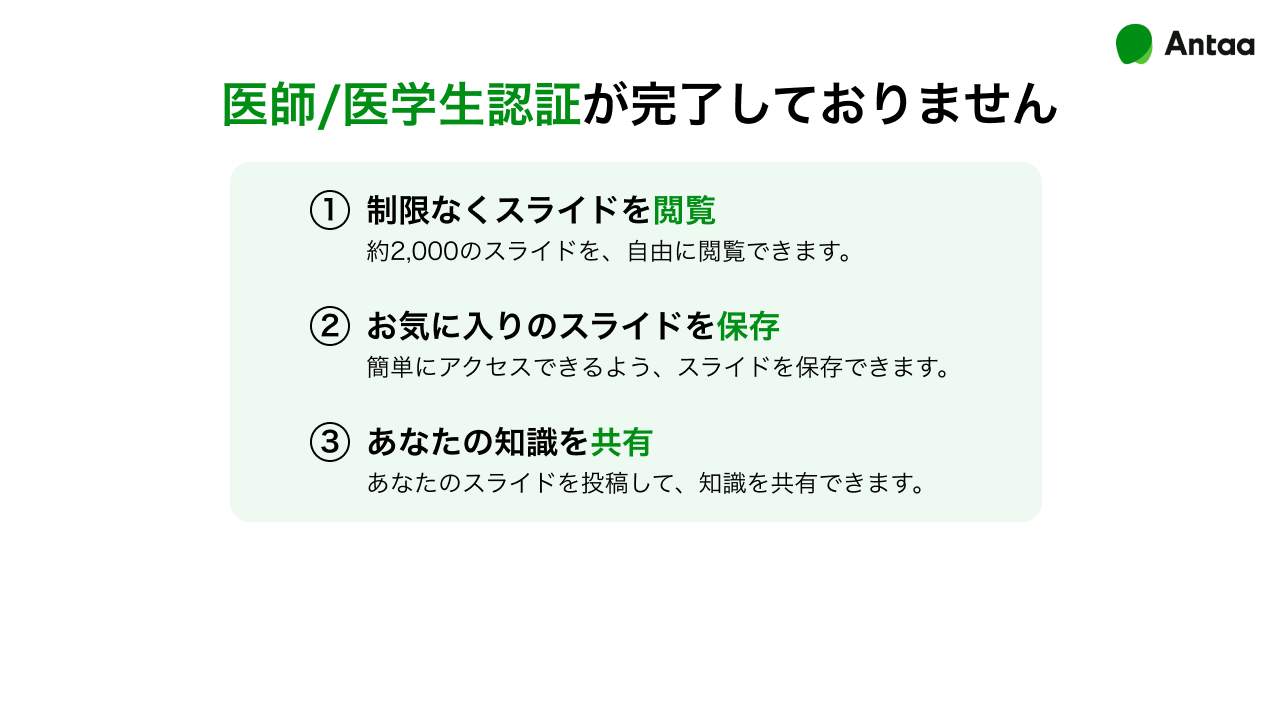このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/94
関連するスライド
ちゃんとできる!誤嚥性肺炎!
ガラパゴス伊藤
230588
538
2023.4.4更新 肺炎まとめ
新米ID
24617
396
誤嚥性肺炎診療の最前線
森川暢
130137
508
誤嚥性肺炎の主治医力【診断編】
吉松由貴
72358
251
誤嚥性肺炎病棟診療の原則
204,750
378
森川暢さんの他の投稿スライド
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。