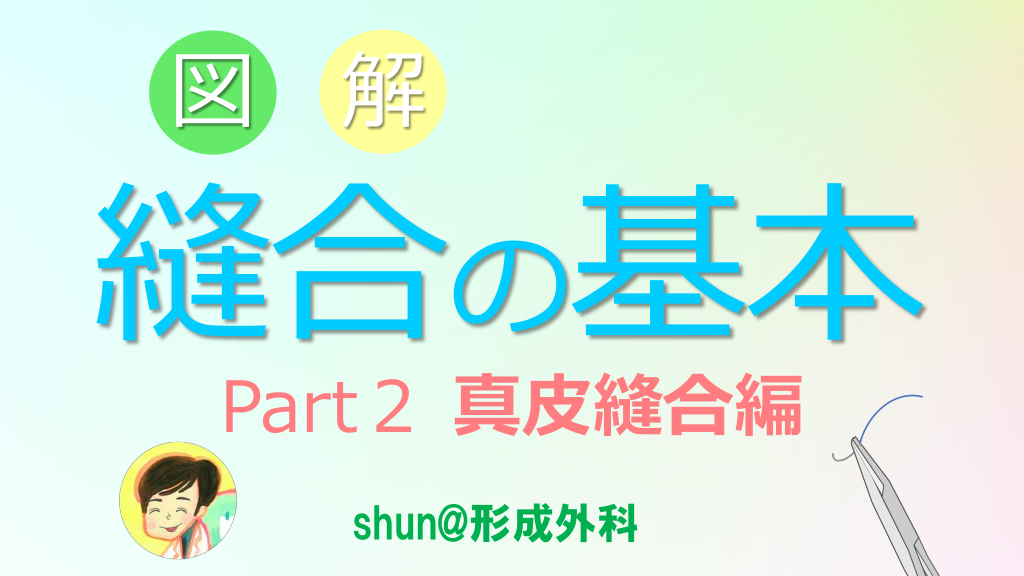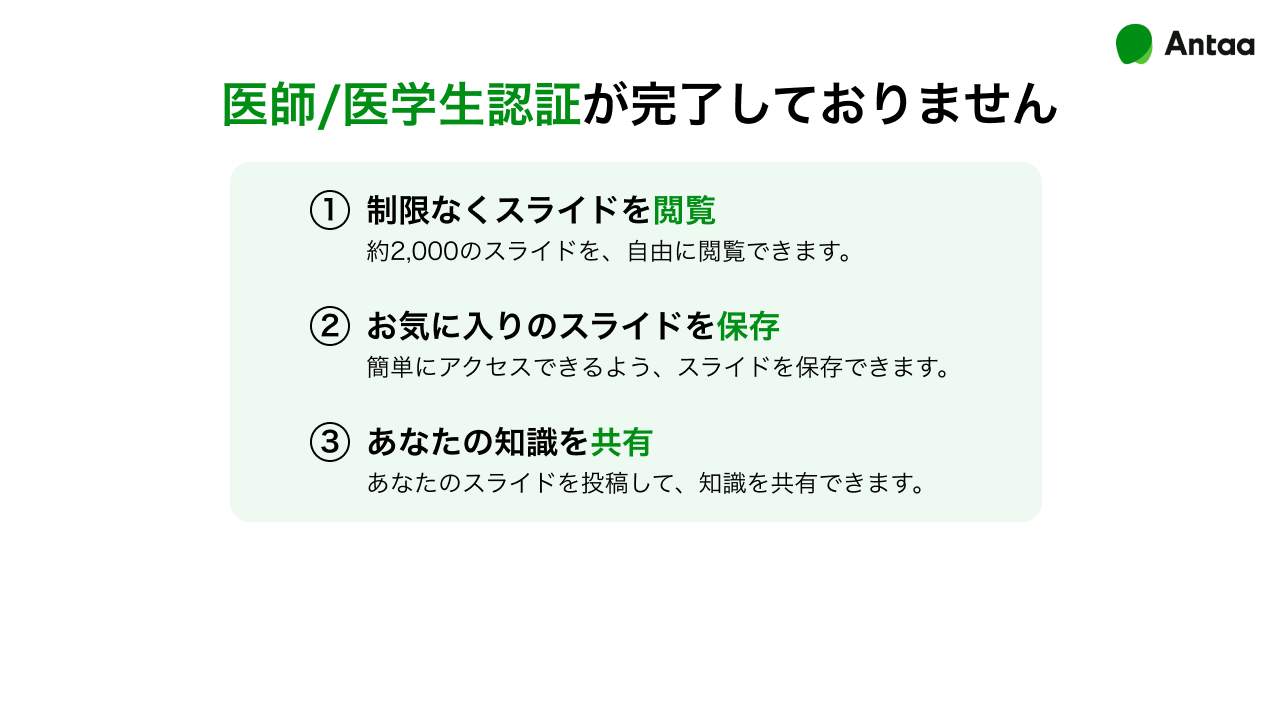このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/26
関連するスライド
きれいな傷と汚いきず 後編
shun@形成外科
15926
80
きれいな傷と汚いきず 前編
shun@形成外科
26850
129
局麻中毒 You must know
shun@形成外科
95345
744
図解 縫合の基本 Part3 いろいろな縫合編
shun@形成外科
203534
1172
図解 縫合の基本 Part2 真皮縫合編
shun@形成外科
Award 2023 受賞者
総合病院
229,381
1,188
shun@形成外科さんの他の投稿スライド
“眼窩底骨折”救外やるなら知っておきたいシリーズPart 5
shun@形成外科
127,492
591
局所麻酔時に痛みを減らすテクニック
shun@形成外科
88,428
347
図解 Screw と Plate Part1 基本知識 編
shun@形成外科
561,850
509
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。