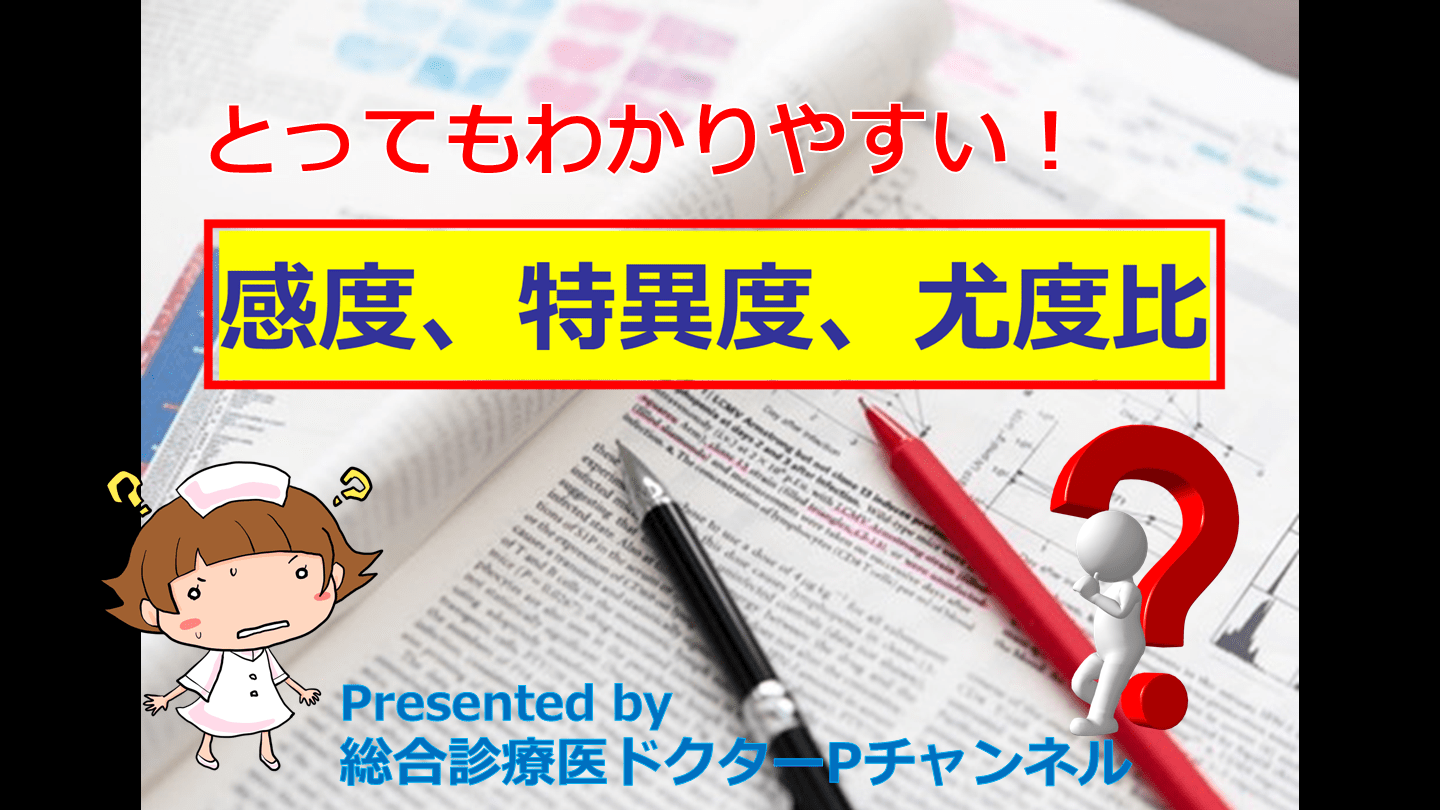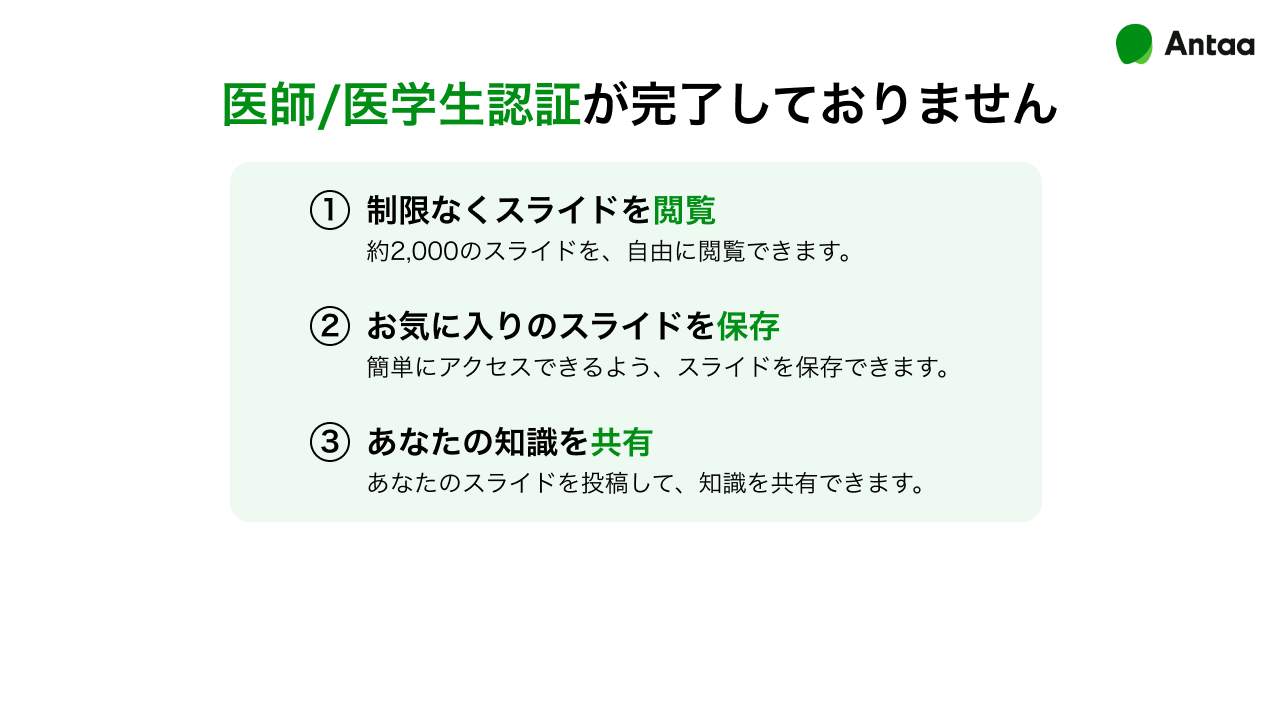このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/20
関連するスライド
尤度比の活用法
古川由己
7520
32
フローサイトメトリーの読み方 ~研修医からジェネラリストまで~
はらD
442303
508
想定外の「HIV検査陽性」をみたら.
塚田訓久
27820
141
検診でリウマトイド因子(RF)陽性でした。関節リウマチ(RA)ですか?
MajorTY@膠原病内科
19268
92
感度と特異度とは? 尤度比って何?【検査を正しく理解するために】
43,242
150
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。