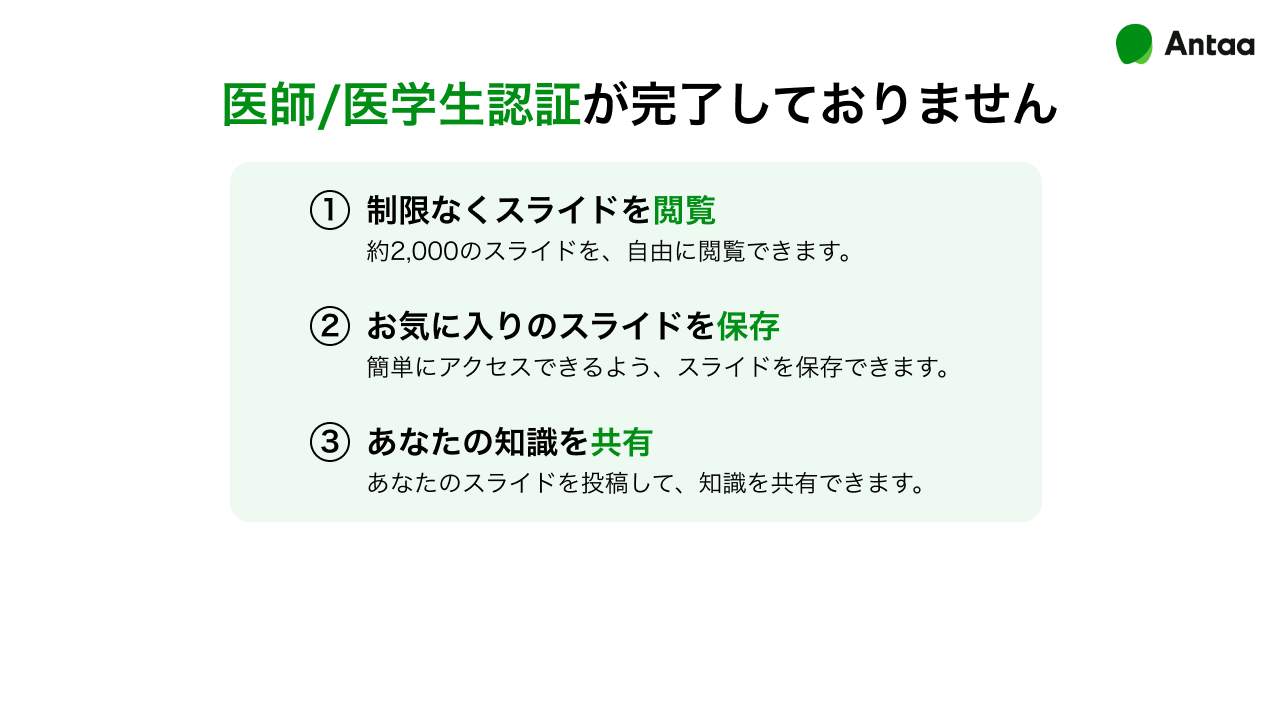このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/16
関連するスライド
【心不全診療ガイドライン解説】心不全診療の「なぜ」定義・予防・CKDのアップデート
岸拓弥
31970
188
痛風・高尿酸血症治療薬一覧
Antaa運営事務局
35033
182
症例報告 慢性腎臓病(CKD)
ミント@腎臓内科
34086
91
慢性腎臓病(CKD)と抗菌薬・抗ウイルス薬の使い方
アイジュ@海外勤務医
60682
146
CKDの合併症抑制におけるXOR(キサンチン酸化還元酵素)阻害の可能性
7,693
16
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。