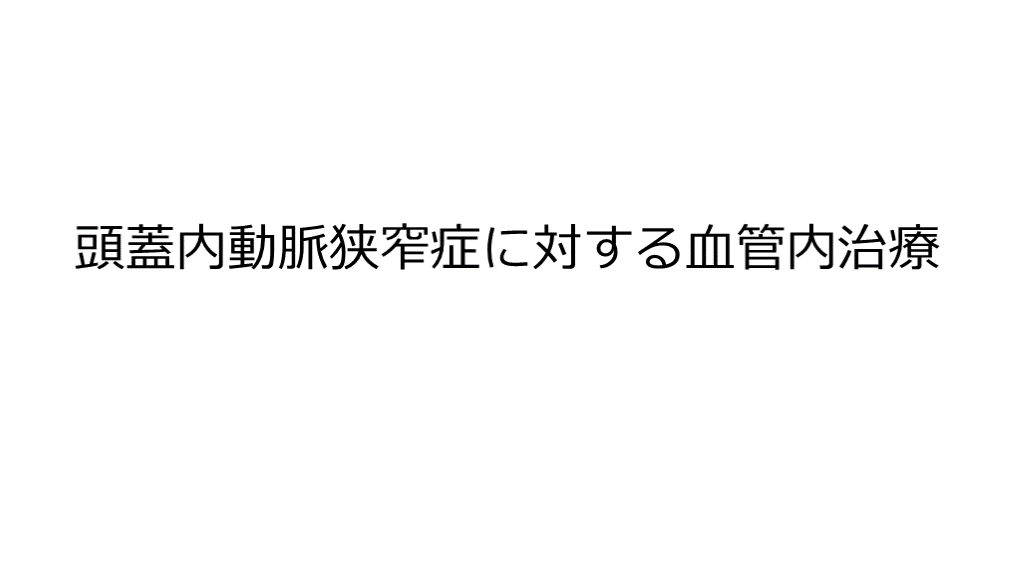1/40
関連するスライド
重症頭部外傷のまとめ【2024年ガイドラインを中心に】
三谷雄己
385770
577
紆余曲折を経て新規ALS治療薬が承認されました
和泉 唯信
4061
9
脳血管撮影 概論
菊野宗明
11247
36
フィールドを意識すれば脳波判読はもっと楽になる
ぼっちペンギン
4104
26
頭蓋内血管狭窄に対する血管内治療
52,879
48
概要
頭蓋内動脈狭窄に対する治療適応について
動画の部分は静止画になってしまってます。
本スライドの対象者
研修医/専攻医/専門医
投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!
0 件のコメント
このスライドと同じ診療科のスライド
テキスト全文
頭蓋内動脈狭窄症に対する治療の概要
#1.
頭蓋内動脈狭窄症に対する血管内治療
#2.
目次
#3.
目次
脳梗塞と頭蓋内動脈狭窄の関係
#4.
脳梗塞の主要な原因の一つであり脳梗塞患者の18%に頭蓋内動脈狭窄を認める(脳卒中データバンク2015) 植田 敏浩:症候性頭蓋内動脈狭窄の内科的治療と脳血管内治療の現状Jpn J Neurosurg(Tokyo)26:714‒720, 2017 井上 智弘;頭蓋内血管狭窄病変の手術治療の可能性(動脈硬化性病変) Jpn J Neurosurg(Tokyo)29:709‒715, 2020 右中大脳動脈(M1)狭窄 左内頚動脈(C4)狭窄 右椎骨動脈狭窄 頭蓋内動脈狭窄症(ICAS)とは
#5.
頚部頚動脈以外(頭蓋内動脈) 経皮血管形成術(PTA) ステント留置術 頚部頚動脈 頸動脈内膜剥離術(CEA) 頸動脈ステント留置術 血管内治療の適応 脳卒中ガイドライン2021 推奨度C 推奨度B
#6.
脳卒中ガイドライン2021 血管内治療の適応 内科治療のみでは脳梗塞の再発予防が困難な頭蓋内動脈狭窄症 経皮的血管形成術(PTA)、ステント留置術を検討
頭蓋内動脈狭窄症の治療法とガイドライン
#7.
目次
#8.
Kasner SE, et al;Warfarin Aspirin Symptomatic Intracranial Disease Trial Investigators:Predictors of ischemic stroke in the territory of a symptomatic intracranial arterial stenosis.Circulation 113:555‒563, 2006. 頭蓋内動脈に70%以上の狭窄を有する症候性頭蓋内動脈狭窄症例では1年後の狭窄血管領域の脳卒中再発率は23%と高率に認めた 頭蓋内動脈狭窄に対するワーファリンとアスピリンの効果を比較したRCT WASID trial
#9.
During a mean follow-up of 23.4 months, 38.2% of the patients had a stroke or a TIA in the same territory of the stenotic intracranial artery. The cerebrovascular events were a TIA in 25 patients (24.5%) and an IS in 14 patients (13.7%). Mazighi M, Tanasescu R, Ducrocq X, et al: Prospective study of symptomatic atherothrombotic intracranial stenoses: the GESI-CA study. Neurology 66: 1187–1191, 2006 APD=antiplatelet drug IS=ischemic stroke GESICA study 狭窄度50%以上の症候性頭蓋内動脈狭窄例に対して基礎疾患の管理と抗血栓療法を行ったところ、約2年で脳卒中の発症が32.8%にみられた
#10.
WASID trial、GESICA study 頭蓋内動脈高度狭窄症例に対し内科的治療には限界がある Wingspan Stent Systemが開発された
Wingspan Stent Systemと治療成績
#11.
Wingspan Stent System and Gateway PTA Balloon Catheter https://www.stryker.com/jp/ja/neurovascular/products/wingspan-stent-system.html 唯一薬事承認されている頭蓋内動脈狭窄症治療用自己拡張型ステント ステントは展開直前までシステム内に収納されており血管内を傷つけにくい ステントの自己拡張能によって拡張するため、低侵襲な拡張が得られ血管壁にかかる圧力は最小限に抑える 植田 敏浩:症候性頭蓋内動脈狭窄の内科的治療と脳血管内治療の現状Jpn J Neurosurg(Tokyo)26:714‒720, 2017
#12.
SAMMPRIS trial Derdeyn CP, Chimowitz MI, Lynn MJ, et al: Aggressive medi- cal treatment with or without stenting in high-risk patients with intracranial artery stenosis (SAMMPRIS): the final results of a randomised trial. Lancet 383: 333–341, 2014 30 日後の脳卒中発症率、死亡率は内科治療群が5.8%、内科治療+血管内治療群は14.7%であった→ステント留置群に有意に合併症が多かった 頭蓋内動脈に 高度狭窄がある患者に対して内科治療のみを行った群と内科治療に加えて狭窄部位への血管内治療を行った群を比較したRCT
#13.
ステント留置群に周術期合併症が多かった要因 ・ステントが自己拡張型だった ・発症してからステントを留置するまでの期間が短い SAMMPRIS trial
#14.
VISIT trial 頭蓋内動脈狭窄がある患者に対して内科治療のみを行った群と内科治療に加えて狭窄部位へのバルーン拡張型ステント留置を行った群を比較したRCT 吉村紳一ら:慢性期頭蓋内血管狭窄症に対する最良の治療選択 Jpn J Neurosurg(Tokyo)28:783‒788, 2019 1年後の脳卒中発症率はのバルーン拡張型ステント留置群のほうが内科治療群より高い →自己拡張型ステント、バルーン拡張型ステントのいずれも内科治療のみの症例より 予後が悪かった
SAMMPRIS trialの結果と考察
#15.
ステント留置群に周術期合併症が多かった要因 ・ステントが自己拡張型だった →バルーン拡張型ステントでも有効性を認めなかった ・発症してからステント留置するまでの期間が短い SAMMPRIS trial
#16.
Yasushi Takagi :Intracranial Atherosclerotic Disease:Pathophysiology and Treatment Yasushi Takagi, M.D., Ph.D. Jpn J Neurosurg(Tokyo)30:785‒792, 2021 SAMMPRISでは周術期合併症は14.7%であったのに対し10日以上の研究では2.0〜6.2%と低かった 最終発作から手術までの期間と周術期合併症リスクの関係
#17.
ステント留置群に周術期合併症が多かった要因 ・ステントが自己拡張型だった →バルーン拡張型ステントでも有効性を認めなかった ・発症してからステント留置するまでの期間が短い →ステント留置までの期間を長くすることで予後が改善する SAMMPRIS trial
#18.
血管形成術施行時に生じた血管解離、急性閉塞または切迫閉塞に対する緊急処置(いわゆる rescue stenting) 他に有効な治療法がないと判断される再治療 脳卒中 37 巻 4 号(2015:7) 年齢:22 ~ 80 歳 狭窄率:70%以上 内科的治療中の 2 回以上の stroke TIA は除く Stroke 後7日以上たっていること Stroke 後にmRS3以下に回復していること 米国での適応 本邦での適応
血管内治療の適応と合併症
#19.
WASID trial、GESICA study 頭蓋内動脈高度狭窄症例に対し内科的治療には限界がある Wingspan Stent Systemが開発された SAMMPRIS trial、VISIT trial 内科的治療群に比べてステント留置群に有意に合併症が多かった Wingspanの適応をレスキューと再狭窄例に限定した
#20.
目次
血管内治療の合併症と症例報告
#21.
治療手技 パーフェクトマスター 脳血管内治療 必須知識のアップデート 第3版
#22.
目次
#23.
血管穿孔・解離 ワイヤーが病変を通過する際、デバイスを入れ替える際に起こる 血栓形成 PTAを施行した狭窄部、ステント内に血栓が生じる 穿通枝や分枝の閉塞 穿通枝の多い中大脳動脈水平部や 脳底動脈で生じやすい 血管内治療の合併症 頭蓋内主幹動脈狭窄病変に対する血管内治療脳卒中 37: 241–247, 2015
#24.
血管穿孔 ・内頸動脈錐体部狭窄に対しPTAを施行した症例 バルーンカテーテルの交換する際に挿入したワイヤーで血管穿孔を起こした 止血は得られたが術後CTでは広範なくも膜下出血を認めた 宮地茂、浅井琢美:頭蓋内主幹動脈狭窄病変に対する血管内治療脳卒中 37: 241–247, 2015
症例研究:脳梗塞患者の治療経過
#25.
解離 宮地茂、浅井琢美:頭蓋内主幹動脈狭窄病変に対する血管内治療脳卒中 37: 241–247, 2015 ・脳底動脈狭窄に対しPTAを施行した症例 PTA施行後に解離を認め右上肢の麻痺が出現した ステント(wingspan)を留置したが症状は改善せず術後MRIで橋梗塞を認めた
#26.
目次
#27.
80代女性 脳梗塞の既往がありクロピドグレル75mgを内服中 X月18日 構音障害が出現し救急搬送された JCS1、NIHSS 2点 当院でPTAを施行した症例
#28.
拡散強調像 MRA X月18日
PTA施行後の経過と治療方針
#29.
X月18日 DAPT(バイアスピリン100mg、クロピドグレル75mg) アルガトロバン20ml の投与を開始 症状の増悪なくアルガトロバンを終了しヘパリンを開始した X月22日 右上肢麻痺が出現 TAPT(バイアスピリン100mg、クロピドグレル75mg+シロスタ ゾール200㎎)+ヘパリンでの加療を開始 X月25日 左顔面神経麻痺、右上下肢麻痺、左下肢麻痺 JCS10、NIHSS 11点 当院でPTAを施行した症例
#30.
拡散強調像 X月25日
#31.
X月18日 DAPT(バイアスピリン100mg、クロピドグレル75mg) アルガトロバン20ml の投与を開始 症状の増悪なくアルガトロバンを終了しヘパリンを開始した X月22日 右上肢麻痺が出現 TAPT(バイアスピリン100mg、クロピドグレル75mg+シロスタ ゾール200㎎)+ヘパリンでの加療を開始 X月25日 左顔面神経麻痺、右上下肢麻痺、左下肢麻痺 JCS10、NIHSS 11点 当院でPTAを施行した症例
#32.
X月18日 DAPT(バイアスピリン100mg、クロピドグレル75mg) アルガトロバン20ml の投与を開始 症状の増悪なくアルガトロバンを終了しヘパリンを開始した X月22日 右上肢麻痺が出現 TAPT(バイアスピリン100mg、クロピドグレル75mg+シロスタ ゾール200㎎)+ヘパリンでの加療を開始 X月25日 左顔面神経麻痺、右上下肢麻痺、左下肢麻痺 JCS10、NIHSS 11点 当院でPTAを施行した症例
治療の問題点と今後の展望
#33.
PTA施行前 PTA施行前:脳底動脈以遠はほぼ描出されなかった PTA施行後:脳底動脈以遠が術前より明瞭に描出されるようになった PTA施行後
#34.
脳底動脈から後大脳動脈にかけての血流は改善したが高度狭窄は残存した PTA 施行後 PTA 施行前
#35.
X月25日 PTAを施行 神経症状の増悪なく経過 TAPT+ヘパリンでの加療を継続 当院でPTAを施行した症例 約2週間後 X+1月13日 薬剤減量のため血管内治療を検討 ステント留置をするか否かが問題となった
#36.
・病変長が長い(10mm以上) ・病変は屈曲し偏在性の狭窄がある ・脳底動脈は穿通枝が多いため穿通枝閉塞を起こす危険性が高い ・特に前下小脳動脈近傍の脳底動脈に不安定プラークが多く、前下小脳動脈が閉塞 すると重篤になり得る ステント留置する上での問題点 前下小脳動脈 脳底動脈 不安定プラーク
#37.
血管造影に基づく頭蓋内動脈の病態形態分類(森分類) 山本慎司、森貴久ら:頭蓋内動脈硬化性病変に対する待機的ステント留置術の長期成績 脳卒中29:14-21,2007
#38.
X+1月13日 ステント留置術は合併症のリスクが高いため 経皮的血管形成術(PTA)のみ施行した 合併症無く経過しヘパリン、シロスタゾールの投与を終了した DAPT (バイアスピリン+クロピドグレル )で治療を継続 X+1月20日 DSAを施行し血流が改善しているのを確認した 当院でPTAを施行した症例
#39.