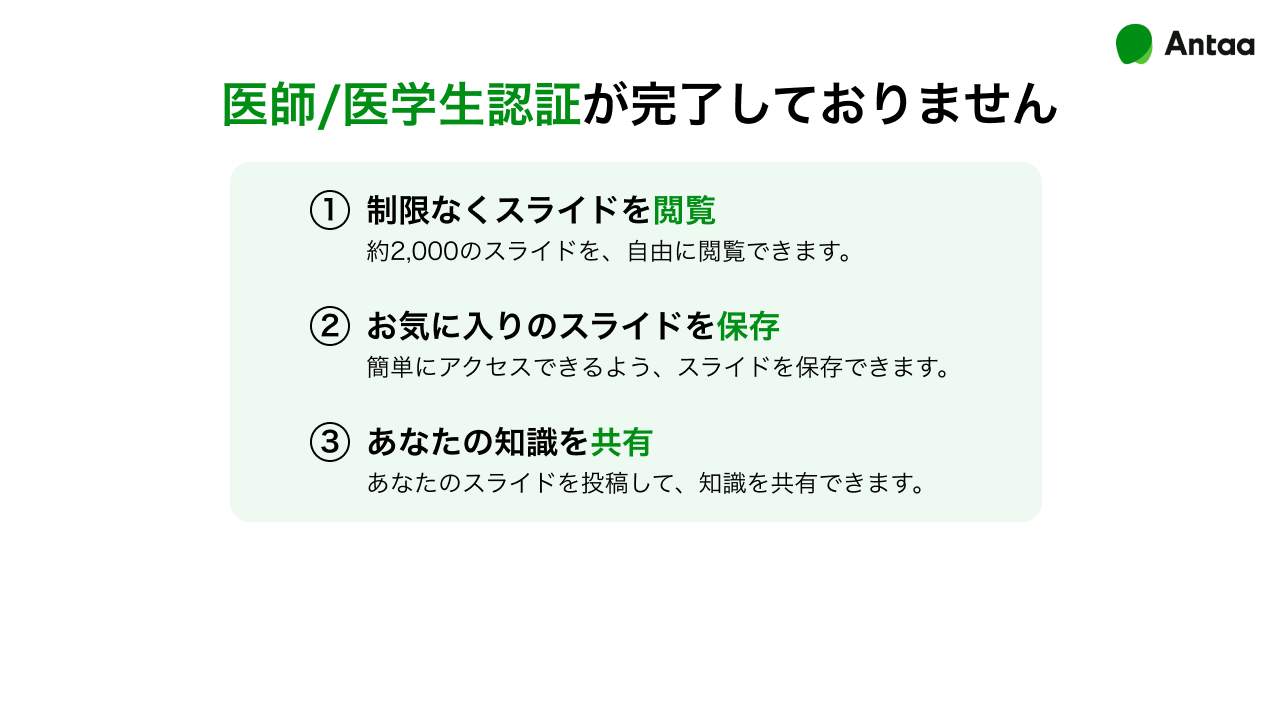このスライドは会員限定コンテンツです。
今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!
1/17
関連するスライド
Drゆみの Weekly Journal Scan vol.19
医療法人社団ゆみの
2015
1
冠動脈造影の見方とやり方
うし先生
32330
161
2025/12 オンラインレクチャー アーカイブスライド
常見勇太
32537
138
心不全管理の鍵 悪化の「なぜ?」を見つける探偵になろう
やまと診療所 AHC-ACADEMY OF HOME CARE-
4996
41
DAPT(抗血小板薬2剤併用療法)〜目的/薬剤選択/治療期間のポイント
496,358
1,066
三浦光太郎さんの他の投稿スライド
このスライドと同じ診療科のスライド
会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。